2歳で言葉を話さないと、心配になる親御さんもいることでしょう。
2歳で言葉を話さない原因や理由はさまざまで、必ずしも発達に問題がある、身体疾患があるというわけではありません。
しかし、さまざまな可能性があるからこそそのすべてを視野に入れ、多くの解決策や対策を知っておく必要がありますね。
今回は、2歳で言葉を話さないことでお悩みの親御さん向けに、考えられる原因から言葉の促し方、相談先まで解説していきます。

2歳で言葉を話さないのはなぜ?

2歳で言葉を話さないのは、さまざまな理由が隠れています。
注意深く見たいのは「口数が少ない」という点ではなく「言葉自体を習得しているかどうか」です。
言葉自体は習得していても、内向的な性格のためあまり話さない子どももいます。
その場合は、単に性格に起因しているだけですので、心配することはないでしょう。
しかし、言葉自体を習得していない場合には、以下の理由が考えられます。
話すことに興味を持っていない可能性
2歳で話さない理由は、話すこと自体に興味を持っていない可能性があります。
2歳児は字が読めないため、2歳児にとって「話す」というコミュニケーションは、耳で聞いた音と目で見えるものを結びつけるという仕組みです。
そのため「言葉を話す」「コミュニケーションをとる」という環境を「楽しい」と思わせてくれる相手がいないと、なかなか興味を持たないかもしれません。

たとえば、自宅保育よりも保育園に通っている2歳児さんのほうが言葉の発達が早かったりしますよね
いつも自宅などで静かに過ごしていると、言葉の発達がゆるやかになる可能性が高いようです。
子どもの話に積極的に反応したり、ものについて説明したりするコミュニケーションを意識することが大切ですね。
耳がよく聞こえていない可能性
2歳で話さない理由は、耳がよく聞こえていない可能性があります。
先にお伝えしたように、2歳児は耳から聞こえる音と目で見える情報を結び付けて言葉を習得します。
そのため、耳が聞こえにくい場合、言葉を習得する妨げになってしまうのです。
耳垢がつまっていて聞こえにくい場合には、小児科や耳鼻科で耳掃除をしてもらうことで解決するかもしれません。
しかし、遺伝などで生まれつき耳が聞こえにくい子どもや、中耳炎を繰り返して中度の難聴になる子どももいます。
聴力の問題がある可能性があるので、遠くから子どもの名前を呼んでみても反応がない場合には、一度受診してみると良いでしょう。
参考:日本耳鼻咽喉科学会
発達障害である可能性
2歳で話さない理由の中には、発達障害である可能性があります。
言葉の遅れがみられる発達障害は「ASD(自閉スペクトラム症)」で、言葉だけでなく総合的な社会性に困難さがみられます。
ASDの特徴は、以下の通りです。
参考:LITALICOジュニア
このように、ASDと一言でいってもさまざまな特性があり、数ある中の1~2つ当てはまっているだけでは「ASDである」とはいえない可能性も。
言葉の遅れもASDの特性の1つですが、言葉の遅れだけで発達障害と断定はできないでしょう。
また、言葉の遅れと発達障害を結びつけるには、ほかの成長過程も見てみましょう。
たとえば運動や食事などの動作、社会性の発達なども、言葉と同じく遅れがみられる可能性があります。
2歳で言葉を話さない場合には、発達障害の可能性も頭の隅に置いておきましょう。
参考:厚生労働省
レイトトーカーの可能性
2歳で言葉を話さないのは、レイトトーカーである可能性があります。
レイトトーカー(Late Talker)とは、話しはじめるのが遅い子を指す呼称。
日本小児耳鼻咽喉科学会によると、発達障害や知的障害などの原因がみられない場合に用いられます。
アメリカでは、2歳以下で語彙数が50以下、もしくは2語文が少ない場合を指すそうです。
わたしの友人の娘さんも典型的なレイトトーカーで、なんと3歳になるまで一言も話さなかったそう(!)。
しかし、ある日スイッチが入ったかのように突然話し出し、現在(小4)は発達の遅れなどもなく生活しています。
しかし、レイトトーカーの20~30%はのちに「ことばの遅れ」や「学習面のつまづき」につながることがわかっています。
参考:ことばの相談室ことり
2歳で話さない子の言葉を促すには?

2歳で言葉を話さない場合、さまざまな原因があることが分かりました。
聴覚の問題や発達障害、また「レイトトーカー」という聞き慣れない原因がある可能性もありましたね。
では、2歳で話さない子どもに対して「言葉を促す」ポイントを解説していきます。
聴覚に問題がなく、ただ単に言葉の習得が遅れている場合には、周囲のかかわりやコミュニケーションによって言葉の発達を促すことが期待できます。
日々の生活で、子どもの脳や心によい刺激を与えることが大切なので、ぜひ日常的に意識してみてくださいね。
同年代の子どもと交流させる
2歳で話さない子の言葉を促すには、同年代の子どもと交流させる機会を持ちましょう。
保育園に通っていれば、先生や大勢のお友達とかかわる機会に恵まれますが、自宅保育だとどうしても家族とだけ過ごすことになりますよね。
園庭開放や児童館など、同年代の子どもが集まる場所に足を運んでみてはいかがでしょうか。

わが家では、発達がゆっくりだと気づいた段階でこの対策を施しました。
目に見えて効果は感じませんでしたが、良い経験になったはず!
わが家のまめはASD(自閉スペクトラム症)の傾向が強かったため、同年代の子どもたちに興味を示さず、言葉の刺激はあまり受けられなかったように思います。
わが家のようにASDの要素を持つ子は、にぎやかな場に行っても結局1人で黙々と遊んでいるだけかもしれません。
それでも、同年代の子どもたちがたくさんいる中でおもちゃを貸し借りしたり、真似っこして遊んだりすることで、良い刺激にはなると思います。
新しい体験を増やす
2歳で話さない子の言葉を促すには、新しい体験を増やしましょう。
子どもは興味・関心を惹かれるものに対し、すさまじい集中力を発揮します。
普段とは違う公園や遊び場に行ってみたり、はじめてのアクティビティに参加してみたりすることで、子どもの「何これ!」「好き!」を増やせるかもしれません。
そして、子どもが興味を示すものが増えれば、それについて親御さんが楽しく説明してあげることができますね。
そのコミュニケーションが、子どもの言葉を促すきっかけになるでしょう。

相づちを打ったり説明したりする
2歳で話さない子の言葉を促すには、親御さんが相づちを打ったり、子どもが気になっていることを説明してあげたりするコミュニケーションが大切です。
今子どもが理解できる語彙や長さを意識し、実際のものを見せながら説明することで、伝わりやすくなるでしょう。
たとえば、保育園や幼稚園に行くときには通園バッグや靴を見せたり、車に乗るときには車の鍵を見せたりすることです。
そして、単語が分かるようになってきたらもう1語付け足して返してあげると、子どもは文章の組み立て方を少しずつ習得していきます。
参考:FUKU
一般的な2歳児の言葉の発達

一般的な2歳児の傾向でいうと、言葉の量は以下のようになります。
| 2歳0ヶ月 | 2歳6ヶ月 | ~3歳 | |
| 言葉の量 | 200~300語 | 400~500語 | 1,000語 |
| 特徴 | 2語文 (ママ だっこ、ワンワン いる等) | 2~3語文 (ママ だっこ して、あの ワンワン かわいい等) | 3語文以上、 質問文、疑問文 |
参考:ベビーパーク
厚生労働省が公開している乳幼児身体発育調査によると、1歳6~7ヶ月の子どもの94.7%が単語を話すそうです。
このデータを見る限り、以下に該当する場合は、なんらかの原因で言葉が遅れていると考えられるでしょう。
また、乳幼児が言葉を習得していくプロセスは以下の通りです。
- 自分から声が出ることを楽しむ(1~3ヶ月ごろ)
- 子音(パパ、ママなど)を発したり、唇を使って発声(んまんま、ブーなど)したりする(5~6ヶ月ごろ)
- 発声の強弱などを調節できるようになる(9ヶ月ごろ)
- 単語を覚えて話すようになる(1歳を過ぎてから)
すべて、子どもが耳で聞いたり目で見たりするものに興奮し、声に出して感情を表現しようとすることで言葉が増えていくのですね。

振り返ると、まめは話すことにもお友達にも興味を持っていなかったと思います。
それでは言葉が増えないのも納得…
一般的な2歳児の言葉の発達については、子ども家庭庁が公開している「子ども家庭総合評価表 記入の目安と一覧表」も参考にしてみてくださいね。
2歳で言葉を話さない場合の相談先

2歳で言葉を話さない場合、むやみに自宅で様子を見るよりも、専門機関に相談することで親御さんの安心にもつながります。
特に見落とされがちなのが、聴力の問題。
2歳で話さない場合には発達以外にも、きちんと聞こえているかを確認することがとても大切ですよ。
以下の相談先が適切ですので、ぜひ一度訪れてみてください。

わたしは毎日のように支援センターや児童館に行っていたので、そこの先生にいろいろ相談していました。
子どもの発達傾向や療育についての情報をたくさんもらえて、励ましてもらえて、心のよりどころになりました!
まとめ
2歳で言葉を話さないときの理由や相談先、またご家庭でできる言葉の促し方について解説しました。
2歳は、周囲のお友達がペラペラと話していたり、子どもによっては円滑にコミュニケーションができたりする子もいます。
個人差があると分かっていても、焦ったり不安になったりしますよね。
でも、専門機関に相談して原因が分かったり、やれることが分かったりするだけで、先行きは明るくなります。
親御さんだけで抱え込まず、いろんな情報や専門家の意見を聞きながら、子どものペースで言葉を習得できる環境を模索していきましょう!
よく読まれている記事

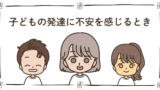
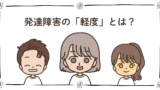
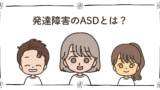
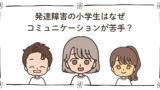
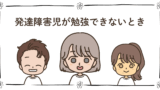


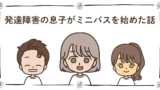
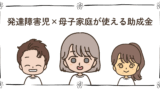
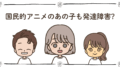


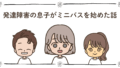
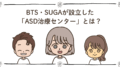

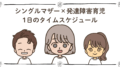
コメント