発達障害をもつ子どもを育てるご家庭では、幼稚園や療育先から支援学級への進学を勧められることがあるかもしれません。
「まさか自分の子が支援学級に通うことになるなんて…」
そんなふうに、先行き不安な思いをされているご家庭もあるのではないでしょうか。
この記事では、発達障害児が支援学級を勧められたときの選択肢について、わが家の体験談とともにお伝えしていきたいと思います。

発達障害があると支援学級に入る?

発達障害がある=支援学級に入るというわけではありません。
支援学級に入るかどうかは、以下の要素をもとに個別に判断されます。
厳密には、教育センターで審査にかけられ「本当に支援学級に在籍する必要があるのか」を判断されます。
そのため、以下のいずれかとなります。
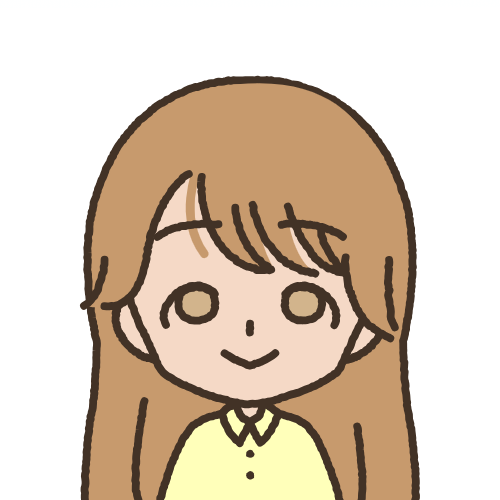
支援学級に入れたい場合は希望に沿うかどうかわからないけど、無理やり支援学級に入れられることもないんだね

形式上はそうなんですが、実際には半強制的に支援学級に行かされることがあります。
このあとくわしく解説しますね
支援学級以外の選択肢もある

発達障害がある場合、支援学級に入る以外にも選択肢があります。
支援学級を避けて方法を模索したいご家庭や、さまざまな方法を知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
通常学級で学ぶ
発達障害がある子どもで、通常学級に在籍し学び続けている児童が多くいます。
リタリコ発達ナビの情報によると、通常学級に在籍する生徒のうち8.8%に発達の特性があることが分かっています。
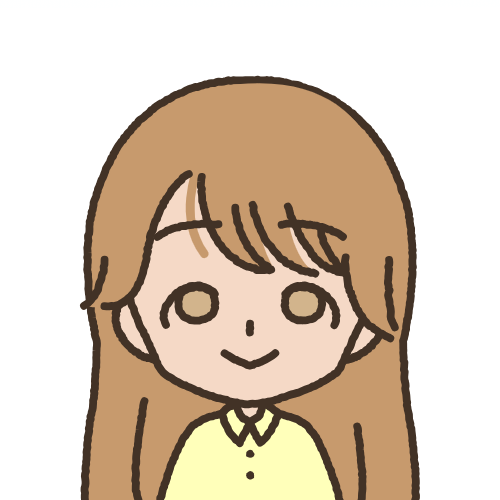
通常学級にも、発達特性を持った子どもが結構いるんだね!
発達障害がある=支援学級でないといけない、ということはありませんので、子どもの発達特性の程度によって適した場所を選びましょう。
通級に通う
通級は正式名称を「通級指導教室」といいます。
わかりやすく言うと、通常学級に在籍しながら部分的に特別な支援を受けられる制度のことです。
通常学級と支援学級の良いとこどりで、授業や支援は特別支援教育に精通した教員が担当するので、通常学級よりも個別に配慮してもらえます。

個人的に通級に魅力を感じたのは「転校しなくても良いこと」でした
支援学級に入るとなると、在籍している学校に支援学級が設置されていることが条件となります。
そのため、支援学級のない学校に在籍している場合、支援学級のある学校に転校する必要があるのです。
その点、通級はもとの学校に在籍したまま、通級のある学校に移動すればよいだけ。
通っている学校に通級があれば、教室を移動するだけで済みます。
支援学級に転籍するよりも身軽で、親子ともに負担の少ない方法でしょう。
個人的にわが家が、通級のデメリットとして感じたのは
往復の時間ロスが大きい
というものでした。
わが家の場合、在籍している小学校から通級のある小学校までは自転車で片道15分ほど。
そして、通級として利用できる時間は週に1コマ(45分)のみでした。
通常、通級は週に1~2回、1~2時間が目安となっていて、ほとんどの場合曜日によって決められます。
週に1度、たった45分のためだけに往復30分をかけて、場所を移動することが大きな時間的ロスに感じました。

毎日45分の通級を受けられれば、往復30分かけてでも行きたいけれど(それはそれで負担も大きいですが)週1回45分だけ通級を受けるなら、その分学校にいた方がよいのでは…?と感じました
通級も、支援学級と同じく設置している学校とそうでない学校があるため、移動距離や時間も加味して決めると良いでしょう。
まだお子さんが未就学児なら、最初から通級や支援学級のある学校に入学するのも手です!
通級と支援学級の違いについて、表にまとめてみましょう。
| 項目 | 通級 | 支援学級 |
|---|---|---|
| 所属 | 通常学級 | 支援学級(特別支援学級) |
| 支援時間 | 週1~2回程度 | 常時または一部教科を支援学級で受ける |
| 対象 | 知的な遅れがない児童 | 知的障害や発達障害が重い場合 |
これらの要素をふまえて、子どもの進学先や在籍する学級を決めてみてくださいね。
放課後等デイサービスを利用する
放課後等デイサービスは、放課後や長期休暇を利用する療育・支援施設です。
発達障害や知的障害のある子どもにとっての「学童保育+療育」のような場所と考えるとイメージしやすいでしょう。
放課後等デイサービスを利用するのは放課後のため、転校などの手続きは必要ありませんが、受給者証を取得する必要があります。
\ 受給者証についてはこちらを /
放課後等デイサービスでは、以下のようなプログラムを提供しています。
| プログラム | 内容(一例) |
|---|---|
| 学習支援 | 宿題のフォロー、読み書き練習、 タブレット学習など |
| ソーシャルスキル トレーニング | あいさつ、順番、会話練習、 感情表現の練習 |
| 運動療育 | バランス運動、 体幹トレーニング、ダンス |
| 創作活動 | 工作・絵画・音楽など、 表現力を育てる活動 |
| 集団活動 | ゲーム、遠足、季節行事 などを通じた協調性の育成 |
放課後等デイサービスでは、学習に特化した教室や運動療育に特化した教室など、さまざまな特色があります。
わが家では、学習フォローをしてくれる放課後等デイサービスを利用しています。
\ くわしくはこちら /
子どもの困りごとや保護者の意向に合わせて、適切な教室を探してみてくださいね。
支援学級に通うメリット・デメリット

支援学級に通うことでどのようなメリット・デメリットがあるのか見てみましょう。
支援学級のメリット
まずは、支援学級に通うことで得られるメリットを見てみましょう。
支援学級では、学習の進み具合や理解度に合わせて進めてもらうことができます。
通常学級の授業はクラス全体のペースで進むので、ついていけなかったり遅れが目立ったりすることがありますよね。
支援学級は少人数(5~8人程度)で学習するため、個々のペースに合わせて進められるのがメリットです。

特別支援教育の知識を持った先生が担当してくれるのも心強いよね
支援学級で学習することは、子どもの「できた!」を増やしてあげること、自己肯定感を保つことにつながります。
また、支援学級は1日じゅう支援学級のクラスにいるわけではなく、支援が必要な教科を選ぶことができます。
そのため、国語や算数は支援学級で受けて、図工や体育は通常学級で受けるという柔軟なスタイルも可能なんです。

ぼくは国語と算数が難しいから支援学級で受けて、運動会や行事は通常学級のみんなと一緒にやってるよ
どの科目で通常学級に行くのかは、先生と子どもで相談して決めて良いそうです。
子どもが少しでも過ごしやすい環境を整えようとしてくれているのが、伝わりますね。
支援学級のデメリット
それでは、支援学級のデメリットについて見てみましょう。
支援学級に入るとき、タイムリーに感じるであろうデメリットは、転校が必要になる可能性があることです。
支援学級に通うには、支援学級のある学校に在籍していることが条件です。
環境の変化に不安を感じる子にとっては大きな負担となるので、デメリットになる可能性があります。
また、支援学級に通うことで
みんなと同じ教室で授業を受けられない
ということに、居心地の悪さを感じてしまう可能性があります。

特に通常学級から突然支援学級に入ったり、中学年くらいになったりすると、自分がまわりと違う環境にいることに気づきやすくなりますよね
そして、進学先についてもデメリットや懸念点が生じます。
支援学級での学習は簡略化され、教科書よりも易しい内容になります。
そのため、中学校に進学したあとにギャップを感じることがあるかもしれません。
そして、中学卒業後に高校進学を視野に入れるとなると、一般入試が難しくなるため、進学先の選び方にも工夫が必要になるでしょう。

まめは支援学級に在籍しているので、おそらく中学校も支援学級のある学校を探すことになると思います。
支援学級を卒業して中学の通常学級に入るのは、ハードルが高いですからね…
まめは学習面で知的レベルが出ているため、この先の進学先についてもいろいろと検討しています。
支援学級に入るかはどのように決まる?

支援学級に入るかどうかは、以下のフローを経て総合的に判断されます。
- 学校での経過観察
- 教育相談の申し込み
- 判定会議
- 結果通知と同意
学校での経過観察
まずは、対象児童を学校でよく観察することから始まります。
先生が、その子の学習や集団生活での困難を把握し、合理的配慮をしながら様子を見ます。
場合によっては通級を利用したり、少人数教室で対応したりすることもあります。

ぼくの学校では算数だけ少人数制になっているよ
その中で、保護者と面談する機会を作り、今後の方向性について話し合いを始めます。
教育相談の申し込み
市の教育支援センターなどで実施している「就学相談」や「進級時の教育相談」や、特別支援コーディネーターとの面談を通して、今後の方向性を決めることがあります。
このとき、まだ診断名がついていなかったり、発達障害の特性がはっきりしていなかったりする場合には、知能検査(WISCなど)や行動観察、発達検査などを受けることも。
\ WISCについてはこちらを /
支援学級に入れるか入れないかというより、子どもにとって「支援学級のほうが合っているのか、そうでないのか」という判断をしてもらえる貴重な機会です。

支援学級に入れるかどうか迷われている場合には、親御さんだけで決めてしまわず教育相談の機会を活用することをおすすめします!
判定会議
教育相談で話し合われた内容や、発達検査を受けた場合の結果に応じて、支援が必要かどうか審査されます。
審査には、医師や心理士、教育関係者などの専門家がかかわり、知能指数(IQ)や発達特性が考慮されます。
しかし、それだけでなく本人の希望や保護者の意向、現在の学校生活の適応状況なども判断要素に入りますので、知能指数や発達特性だけで支援学級が決まるわけではありません。

まめは知的レベルの結果が出ましたが、本人が現在の学校を好んでいたため、支援学級への転籍は最終手段にしていました
結果通知と同意
最終的に、支援学級に入れるかどうかの結果通知が届き、それに保護者が同意すれば成立となります。
どのような結果になっても、最終的に保護者が同意しなければ支援学級に入ることはありません。
支援学級に入ることに同意しない場合、通常学級のまま継続することができます。
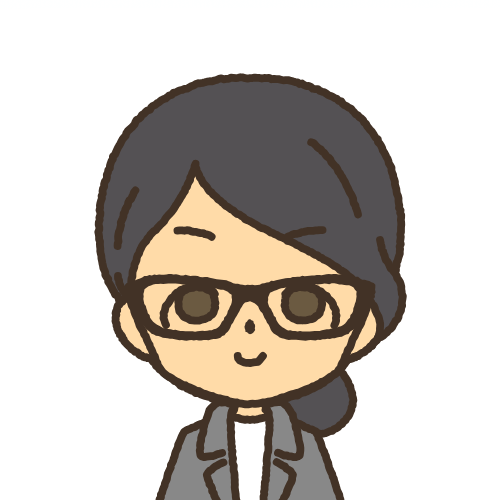
学校から、支援学級への転籍を強制することはありません
支援学級と通常学級で迷っている場合「一度審査にかけられたら支援学級に入ることになるのでは…」と心配している親御さんもいることでしょう。
しかし、最終的には親御さんに決定権がありますので、迷われている場合でも、気軽に相談してみるとよいでしょう。

支援学級に入る必要性があるかどうかを専門家に判断してもらえるので、貴重で有益な情報になると思います
発達っ子を育てるわが家の選択

わが家では発達障害をもつ子どもを育てていますが、結論からいうと小学校入学時は通常学級に入りました。
通常学級に入学することを決めるまでには、幼稚園の先生・療育の先生・小児科の先生と何度も話し合いをし、十分な時間をかけました。
わが家で通常学級に入学した理由は、次の通りです。
まめが年中のときにK式発達検査を受けたのですが、そのときの検査官の先生に
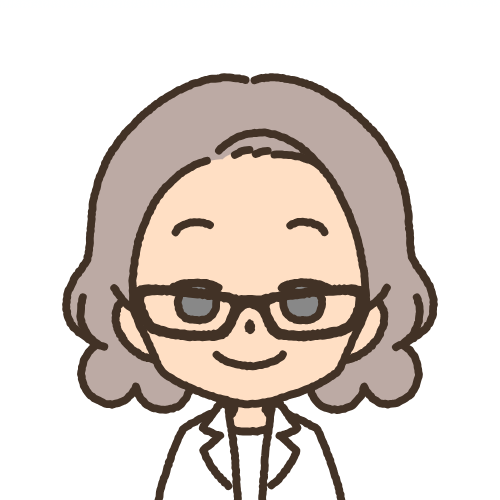
今のままで診断名をつけるのは難しいですね。
まめ君は圧倒的に知識と経験が不足しているだけで、通常学級で周囲から刺激されることで伸びていくと思いますよ
といわれたのが印象深かったです。

圧倒的な知識と経験不足で発達障害ではない…?
そんなことある…?とあっけにとられてしまいました(笑)
そして、その後1年をかけて療育を受けてきたまめ。
療育で進路相談に乗ってもらったときにも、同じようなことを言われました。
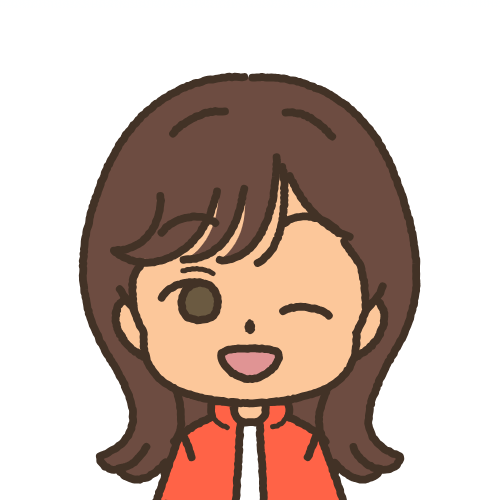
最終的に決めるのは親御さんだけど、療育でのまめ君を見てるといったん通常学級で様子見ても良いと思うよ
途中で変えられるし、支援学級→通常学級だと勉強についていくのが大変だけど、逆なら移りやすいしね
専門家の意見を聞くことができて、わたしも「自分1人で決断しなくて良いんだ…!」と思えました。

小児科や療育にお世話になって本当によかった…と思った瞬間でした
そして、幼稚園の3年間を見てきてわたしも「通常学級にいったん行ってみようかな」という決断に至ったのでした。
途中で支援学級に変えたり、通級を利用し始めたりできるので、究極の選択!!というほどではなかったのが救いでした。
現在小学校4年生になったまめですが、ここに来てまた違う選択を迫られることになります。
なんと先生から「支援学級に転籍してください」と言われてしまったのです。
このお話は長くなるので、こちらの記事にまとめました。
通常学級から支援学級への転籍(転校)の流れや過程について気になる方は、ぜひ読んでみてくださいね。
まとめ
発達障害のために支援学級を勧められた場合、どうすべきなのか解説しました。
発達障害があり支援学級を勧められた場合でも、最終的に支援学級に入れるか否かは、ご家庭の判断で決めることができます。
ご家庭の判断にはなりますが、子どもにとってどの環境が一番快適に学習でき、自信を損なわずその子のペースで進めることができるのかを考えましょう。
発達障害のために支援学級を勧められ、悩んでいる親御さんにとって、役立つ情報になれば幸いです。
よく読まれている記事


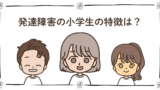


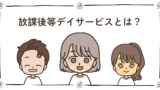



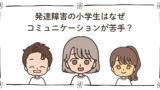
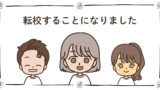
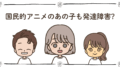


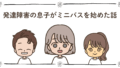
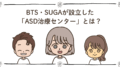
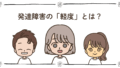
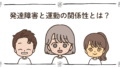
コメント