発達障害の特徴は、1歳でみられることがあります。
特に1歳で分かりやすい発達障害は「ASD(自閉スペクトラム症)」といわれています。
自我が芽生え始めるころから独特な行動をみせることもあり、親御さんや保育園の先生が気づくこともあるかもしれません。
わが家の体験談をもとに、発達障害の特徴が1歳でみられる場合の対処法や気を付けるべきことについて、まとめてみたいと思います。

発達障害の特徴は1歳でわかる?

発達障害の特徴は、1歳という幼い年齢でもわかることがあります。
特にASD(自閉スペクトラム症)の場合は、3歳までに診断が可能といわれており、1歳半検診で指摘されることもあります。

わが家のまめもASDが入っていますが、実は1歳半検診では指摘されませんでした。
3歳以降でASDの特性が強くなってきたので、個人差があることが分かりますね
1歳児の成長は個人差が大きい
1歳児の成長は個人差が大きく、2~3歳もしくは小学生以降の年齢と比べると「これがあるから発達障害だ」とは断定しにくい傾向があります。
たとえば、小学生になって次のような様子がみられる場合、発達障害の傾向があるとみられます。
小学生になると左脳が発達し、周囲を見ながら適切な行動を理解できるようになります。
そのため、発達が遅れていたり発達障害の特性があったりすると、より目立つようになるのです。
しかし、1歳はどの子も成長過程。
多少「おや?」と思うことがあっても、幼児期の成長で追いついたり、単なる個人差だったりする場合もあるでしょう。
そのため、1歳で発達障害の特性がみられる場合でも、断定するのは難しいのですね。
しかし、ASD(自閉スペクトラム症)の場合にはやや独特な特性を見せるので、1歳でも診断されることがあります。
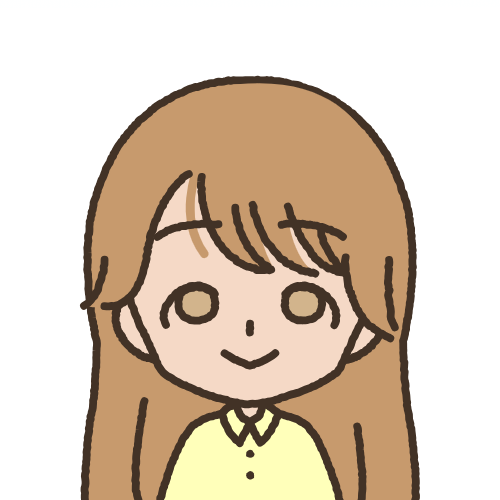
1歳でわかる発達障害は、ASD以外にもあるのかな?

1歳でわかるのは主にASDといわれています。
ほかにADHDという発達障害がありますが、この特性は…

…というように、ほとんどの1歳児にみられる特徴なんです。
そのため、ADHDは1歳児で判断するのが難しいといわれています
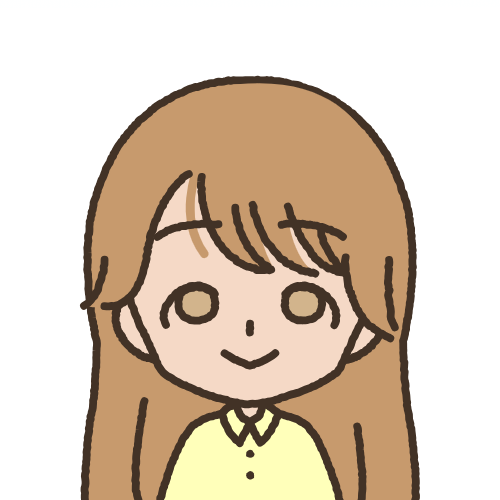
ASDの場合は、一般的な1歳児にみられない特徴があるということなんですね

ASDがある子は、1歳くらいから独特の行動を見せるので、親御さんや先生が気づきやすいんです
そのため、ASDを除く発達障害においては、専門機関を受診したり療育に通ってみたりして、知見のある人たちからのサポートを受けながら様子を見ていきましょう。
発達障害ではなく身体疾患の可能性も
1歳になると、少しずつ歩いたり階段の上り下りができるようになります。
もしそのような身体的発達が一切みられない場合、身体疾患の可能性も考えられます。
上記のような様子がみられる場合、小児科を受診してみるとよいでしょう。

子どもの発達には心配がつきものだけど、発達障害ではなくからだの病気という可能性もあるんだね…

園や学校が始まると「発達障害や身体疾患だと思っていたら心因性だった」など、あらゆる環境が原因となることも。
「〇〇=発達障害」と素人判断しないことが大切です!
一般的な1歳児の成長めやす

それではここから、一般的な1歳児の成長めやすについて見てみましょう。
前述の通り、1歳児の成長は個人差が大きい上に、1歳0ヶ月の子どもと1歳11ヶ月の子どもでは大きな違いがあります。
「うちの子は1歳だけどこれができないから発達障害なのかな?」
「1歳なのにまだこれができないっておかしいのかな?」
などと思わず、個人差があるという前提でのめやすとして、参考にしてみてくださいね。
ことばの発達
1歳児のことばの発達は、以下の通りです。
早い子は0歳のうちに喃語が出てきたり、1歳で単語を話したりするようになるでしょう。
わが家のまめも、1歳半で「だっこ」と意味する喃語のようなものを発するようになりました。

「だっこ」とはっきり言えたわけではないんですが、手を差し出しながら言うので「だっこ」だろうなと理解できました。
1歳児の言葉は親にしか理解できないところもまた、かわいらしいですよね!
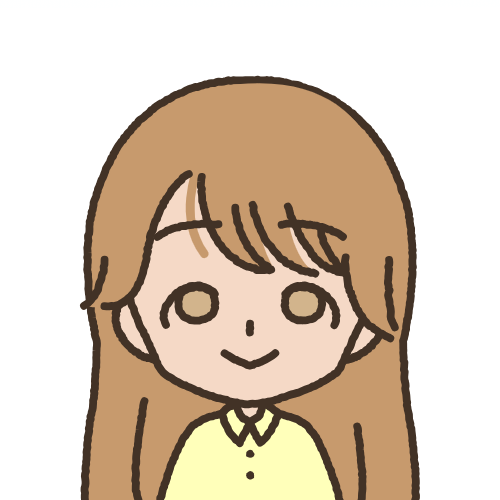
まめ君はASDの傾向があるということですが、それでも1歳で話し始めたんですね

そうなんです。
ASDの子は言葉が遅いといわれがちなんですが、まめの話し始めは早かったです。
なので、やっぱり1歳の段階でいろいろ判定するのは早すぎるということですね(笑)
1歳で言葉が出ないことに悩まれていたら、1歳半検診で相談してみるというのも手です。
まめは、親のわたしから見ると0歳から何らかの発達傾向を感じていて、実際に幼稚園入園後からASDの特性が出始めました。
しかし、1歳半検診では「発達が早いわけではないが、通常の範囲内」という判定で、指摘なしだったんです。
やはり1歳のときに発達障害と診断するのは、専門家にとっても難易度の高いことなんだと思います。
からだの発達
1歳児のからだの発達は、以下の通りです。
1歳になって歩いたりしゃがんだりできるようになると、外の世界が楽しくて仕方ない様子を見せてくれますよね。
同時に、何でも拾って口に入れたり、ささいなことで泣きわめいたりと、大変な時期でもあります。
1歳児の身体の発達には個人差があるため、発達障害を判断できる要素は少ないようです。
しかし、前述のように身体疾患である可能性も考えられるので、気になることがあれば小児科を受診してみてくださいね。

ちなみに、わが家のまめが歩き始めたのは1歳4ヶ月。
そこから走る・しゃがむ・上り下りをするなど、ゆっくりですが着実にできるようになりました
発達障害が疑われる1歳児の特徴

発達障害が疑われる1歳児の特徴は複数あります。
そのため、この中のほんのいくつか該当していても「発達障害である」と断定するのは早いでしょう。

本当にたくさんあるので、グループ分けして解説していきます!
性格編
以下の性格がみられる場合、発達障害が疑われる可能性があります。
当てはまるものが1つや2つであれば可能性は低くなりますが、多ければ多いほどその傾向があると考えられるでしょう。
1歳のときに気付くことの多い発達障害は「ASD(自閉スペクトラム症)」ですが、ASDの子が見せる特性は「子どもならでは」の天真爛漫な行動とは少し違います。
そのため、1歳の時点での性格でASDの傾向があると気づきやすく、この段階で保育園や1歳半検診などで話をされる親御さんも多くいます。
それでは、ASDの主な特性を見てみましょう。
- 表情が乏しい
- コミュニケーションを取ろうとしない
- 人に興味を示さない(懐くことも人見知りもしない)
- 特定のものや場所にこだわる
これらの特性が、1歳くらいから少しずつ始まる可能性があります。
感覚編
1歳でわかる発達障害では、本人の感覚(五感)にもヒントが隠れている可能性があります。
たとえば、以下のようなものです。
ASD(自閉スペクトラム症)には「感覚過敏」という症状があり、五感が一般的な子どもよりも敏感になるケースがあります。
実際にASDがあって、さらに感覚過敏の特性が出てくると、以下のような状態になることがあります。
- ちょっとした生活音が気になって集中できない
- 蛍光灯の光を嫌がる
- 洋服の素材やシャワーが痛く感じる
- 偏食になる
- 車内や飲食店などにおいがこもる場所を嫌う
1歳の段階で「身体に何かが触れるのを嫌がる」というそぶりを見せたら、注意深く様子を見るか、小児科に相談してみると良いでしょう。
しかし、感覚過敏=発達障害ではないというのもまた、トリッキーな部分なんです。
感覚過敏は、発達障害の特性の1つではあるものの、発達障害がなくても感覚過敏を持つ人はいます。

発達障害があってもなくても、感覚過敏という特性はそれはそれで大変そうだね

日常生活に支障があるケースもあるし、感覚過敏がない人は感覚過敏の人の苦しみが理解しづらいから、思いやりが大切になりますね
ちなみに、感覚過敏の反対で「感覚鈍麻」という特性もあります。
名前の通り、感覚が鈍くて痛みや味に気づきにくいことをいいます。

感覚過敏も大変だけど、感覚鈍麻は骨折に気付かなかったり、平気で激辛のものを食べてしまったりすることも!
感覚過敏も感覚鈍麻も、イコール発達障害ではありませんが、発達障害の特性のうちの1つなので、覚えておくとよいでしょう。
コミュニケーション編
1歳で以下のコミュニケーションがみられる場合、発達障害が疑われることがあります。
ASD(自閉スペクトラム症)はコミュニケーションに課題を持つケースが多く、対人関係やことばにおいて遅れがあります。

わが家のまめは、当時はあまり気づきませんでしたが、今思うと「人に興味を示さない」という部分があったのかも…
人をあまり気にしないマイペースな子、と前向きにとらえていたけど、実はASDの特性だったんだなぁ~
わが家で1歳児にみられた発達障害の特徴

わが家のまめにみられた発達障害の特徴は、以下のようなものでした。
発達障害を知る人の間では、よくこんな言葉が聞かれます。
乳幼児期に育てやすい子は発達障害の可能性がある

なんだか不吉な言い方だね…
わたしも、発達障害の子どもをもって初めてこの意味が分かった気がしました。
ASD(自閉スペクトラム症)を持つ子は、比較的乳幼児期に育てやすい傾向にあります。
もちろん個人差がありますし、癇癪がひどかったり抱っこを嫌がったりする子は大変な場面もあるでしょう。
でも、1歳でなんとなくASDの傾向がある子は、他者に興味を示しません。
そのためお友達とのトラブルが少なく、おもちゃの取り合いなどに発展しにくいんです。

わが家のまめもそうで、お友達におもちゃを取られても全然平気でした。
第1子ということもあり、ASDについての知識もなかったので「穏やかな子なのかな?」なんて思っていました(笑)
まめは、お友達におもちゃを取られても「悔しい」「僕のなのに」と思う社会性が発達していなかったんです。
そのため、まめは小学校に入学してから対人トラブルを起こすようになりました。
本来であれば乳幼児期に学ぶべきコミュニケーションだったのだろうと思いますが、発達特性によりそれが小学生に後ろ倒しされたようなイメージでしょう。
1歳児の発達障害の診断めやす

発達障害の特徴が1歳でみられる場合、診断の目安は厚生労働省が発表している「M-CHAT」というスクリーニング検査が推奨されています。
参考:厚生労働省
M-CHATは、子どもの日常的な行動や傾向を親御さんに聞き取りながら、質問紙に記入していく方法。
以下のような質問が用意されています。
M-CHATでは主に「非言語の対人コミュニケーション行動」を確認します。
非言語コミュニケーションは将来において、社会性の重要な基盤となるためです。
くり返しになりますが1歳児は発達に個人差の多い年齢のため、M-CHATを実施し「発達障害の傾向がある」とされた子どもの全員が、発達障害と診断されるわけではないそうです。
参考:LITALICO発達ナビ
発達障害の特徴が1歳でみられたらどうする?

発達障害の特徴が1歳でみられたときは、親御さんの不安を解消するためにも、いち早く専門機関にご相談されることをおすすめします。
自治体の発達センターや保健センターに問い合わせると、相談員を手配してくれたり、小児科を紹介してくれたりします。

でも、相談ってだけでハードルが高いよね…

相談すると悪い話になるのではないか…と心配になりますよね
でも、意外と陥りやすい落とし穴は「両親や友人に相談すること」です

両親や友人に相談するのはダメなの!?

もちろん気心知れた相手に相談できるのは良いことなのですが、専門家以外に発達障害のことを相談しても、良い結果は期待できないことが多いんです
発達障害は、2005年に「発達障害者支援法」という法律が施行されて以降、少しずつ知られるようになっていきました。
そのため、今発達障害児を育てている親御さんのさらに親御さん世代になると、発達障害について知識を持たれていない方が多くいます。
両親や友人に発達について相談しても、このような答えが返ってくるのではないでしょうか。
こういった言葉は、親御さんを安心させるために良かれと思ってかけてくれているものだと思います。
しかし、発達障害について知識を持たない人のこのような言葉を鵜吞みにし、適切な支援につながらなかった子どもが多くいます。

「そんなの発達障害じゃないよ」といわれて安心する気持ちも分かるし「そうだよね、違うよね!」と、無理やりポジティブに考えたい気持ちも分かります
でも、発達障害を持っていた場合、そのまま大きくなった子どもはどうなるでしょうか?
幼稚園や学校などの集団生活が始まると、まわりの子との差に圧倒されてしまうかもしれません。
それが「学校に行きたくない」「友達を作りたくない」「出かけたくない」と、ふさぎ込んでしまうきっかけになるかもしれません。
発達障害の特徴に気づいた段階で、何らかの支援につなげてあげることで、子どもが生きやすい環境を見つけることができます。

相談するハードルが高く感じるのは仕方ない。
でも、周囲の「そんなの発達障害じゃないよ」という声は鵜呑みにしないでほしい、と切実に思います
わが家でやってよかったこと

わが家で発達障害の特徴がみられた際、第1子だったためわたし自身も手探りでした。
そんな中でも「やってよかった」と思っていることがあります。
現在まめは小学4年生になりましたが、彼が1歳だった頃を思い返しても「こうしていてよかった」「こう考えていてよかった」と思っていることなので、シェアしてみたいと思います。
周囲の声に耳を傾けたこと
まめあが「発達障害かもしれない」と思ったとき、わたしはとっさに「いろいろと独断で決めないようにしよう」と思いました。
わたしは完璧主義で独りよがりなところがあるので(MBTIはINTJ)、1人であれこれ考えて突っ走ってしまう危険性がありました。
でもなぜかまめの発達障害に関しては、子どもを守りたい本能のようなものなのか、
自分で考えるよりもまわりの意見を聞いて、なにごとも慎重に決めよう
と最初から決めていました。
発達障害に関する知識もないし、発達障害や知的障害の子どもとかかわったこともない人生。
素人である自分を良い意味で信用していなかった(笑)というのが、功を奏したかもしれません。
その結果、わたしは支援センターや児童館、幼稚園の園庭開放などいろんな場所へまめを連れて行って、いろんな先生に関わっていただきました。

その都度「発達に心配な点があって…」と世間話のごとく、まめの成長について話しました
まめが1歳の頃は、個人差の大きい年齢だったこともあり、どの先生からも療育や支援をすすめられることはありませんでした。
先生方は、発達が気になる今の段階でわたしにできることを提案してくれました。
たとえば、次のようなものです。
発達障害であってもなくても、上記のような親のかかわりによって子どもの”困り感”が軽くなることがあります。
発達障害は完治するものではありませんが、より生きやすくすることはできます。
かかわり方を意識するだけで、親子でストレスが軽減されるでしょう。
また、わたしが周囲の意見を聞く中で印象的だったのは、どの先生も決して
それは発達障害ではないと思う
という言葉を口にしなかったことです。
プロなので、安易にそのような言葉を発さないのかもしれません。
でも、専門家ではないママさんや友人、両親からは何度も聞いていた言葉だったので、
「プロであればあるほど安直な言葉は使わないんだ」
と再確認し、先生方を信用するきっかけにもなりました。
「発達障害かも」をすぐ受け入れたこと
わたしは、まめが0歳児で「発達障害の傾向があるのではないか…」と感じてから、うっすらその可能性を頭の隅に置きながら育ててきました。
だからか「発達障害かも」を受け入れる準備期間がじゅうぶんにあった気がします。
子どもが発達障害である事実を受け入れるのって、一般的に考えられているよりずっとずっと難しいものなんです。
具体的には、以下の2つがあると考えられています。
| 段階説 | 子どもが発達障害だと発覚してから、段階を辿って少しずつ受け入れられる |
| 慢性的悲観説 | 子どもが発達障害だと発覚すると、その後絶え間なく悲しみが続く |
この「段階説」とは、以下の①~⑤を行ったり来たりしながら、何年もかけて受容していくという考えです。
- ショック
- 否定
- 悲しみ・怒り・不安
- 適応
- 受容
わたしは①②を感じることはほとんどありませんでした。
0歳の、何もできない時期になんとなく勘づき始めたので、ショックを受けたり「うちの子が発達障害なわけない!」と思ったりするタイミングを完全に逃したという感じでした。
③~⑤を何度も行ったり来たりして、調子の良い時期と悪い時期を経験して、少しずつ⑤の時期が長くなってきました。
現在は終わりなき悩みに頭を抱えつつも、⑤受容に振り切ることができたと思います。
子どもの発達障害を受け入れるスピード感は、もちろん親御さんの性格によると思いますが、個人的には
受け入れるしか方法はない
と言いたいです。
「発達障害を受け入れなければ発達障害ではなくなる」のなら、誰も受け入れないと思いますが、受け入れても受け入れなくても、子どもの気質は変わりません。
それなら、さっさと受け入れてできることを始めなきゃ!と思いました。

効率重視の性格なので、落ち込んだりして無駄な時間を過ごしたくなかったんですよね
結果、子どもに無理させることが限りなく少なかったと思います。
幼稚園選びにしても、習いごと選びにしても、子どもの発達の特性を一番に考えて選別することができました。
のびのび遊ばせたこと
わたしは、まめが発達障害かもしれないと思ってから、とにかく外で元気いっぱい遊ばせることを一番に考えてきました。
もともと完璧主義で、子どもの知育や教育にも興味があったわたし。
もしまめが発達障害でなければ、幼児教室に通わせたり今ごろ「お受験が」なんて言っていたかもしれません。
でも、まめを育てていると「それは違うな」と思うようになりました。
まめに必要なのは、
こういうことではないかと考えたからです。

そして、その基盤になるのが「外遊び」という結論に行き着きました
当時から在宅で仕事をしていましたが、曜日限定だったこともあり、1日空いている日は朝から晩まで公園で遊びました。
滑り台やブランコでアクティブに遊ぶよりは、黙々と砂遊びをするのが好きだったまめ。
お料理っぽいものを作ってくれたり、砂や石、葉っぱなどをぐちゃぐちゃに混ぜるのが好きでした。
「ものづくり系」が好きなのかな~
なんて思っていましたが、小4になった今でも工作が大好きで、プログラミングも習うようになりました。

のびのび遊ばせたことで、まめの好きなものや傾向を観察できたことも、わが家で「やってよかった」と思っていることの1つです
特性を活かして就学準備をしたこと
まめの発達障害の傾向としては、視覚優位なタイプです。
目から入ってくる情報は受け取って行動に移しやすいのですが、耳から入ってくる情報を頭の中で整理するのが苦手なんです。
最初は「耳からの情報整理が苦手ならそこを特訓しなくちゃ」と思っていたのですが、5歳で療育を受け始めて、考えが変わっていきました。
苦手な部分を頑張って克服するのではなく、今得意な部分を活かそう!
と思うようになったのです。

発達障害児を育てるからこそ、この考えに行き着いたのは本当に大正解でした◎
それから、まめの特性である「視覚優位」な性質を活かして、読み書きを早めに取り入れることにしました。
視覚優位の子は、先生の話や指示を聞くことが得意ではないため、貼り紙やイラストを見せる合理的配慮がなされることがあります。
小学校に入って先生の指示が全部聞き取れなくても、貼り紙の文字を読めれば理解できるかもしれない。
そう思って、年長さんから公文の国語をスタートしました。

就学前にお勉強はまったく考えていなかったのですが、まめの特性を活かすならコレだ!と思って読み書きをみっちり学びました
公文の先生はやや厳しかったですが(笑)頑張って続けた結果、小学校入学時にはじゅうぶんなほどの読み書きスキルが身についていました。
わたしが目指していた通り、小学校では貼り紙や黒板に書かれた文字を読んで、周囲を見ながら行動できるように。
入学後、思った以上に学校が「居づらい」「ついていけない」「つらい」という場所にはならず、本人なりにゆっくりと成長することができました。

まめのように視覚優位の子もいれば、お話が得意ではなくカードで意思疎通を取りたい子、クラスのざわざわが気になってしまう子など、いろんなタイプがいます。
個々の特性に合わせて、ゆっくり成長を見守っていきましょう!
わが家で後悔していること

では、わが家でまめの発達障害に関して「後悔していること」をお話してみたいと思います。
まめは第1子だったので、わたしは子育てそのものが初体験。
そのサンプル1が発達障害児なので、なかなかハードルは高かったです。
なので「後悔していること」といっても、当時の自分を責めるつもりはまったくありません。

もし同じように行動した人がいても、当時100%の力で子育てをしていた自分を褒めてあげましょう!
療育につなげるのが遅かったこと
わたしがまめを見て「発達障害かも」と思ったのは、まめがまだ首もすわらない0歳児の頃でした。
それから、頭の隅にはいつも発達遅延や発達障害のことがありながら、ゆっくりマイペースに子育てをしてきました。
そんな日々を振り返ると、いつ療育につなげるべきか分からなかった部分があります。
まめのことを「発達障害かも」と思った時点では成長に遅れはなく、それから10ヶ月検診や1歳半検診、さらには3歳児健診でも、指摘されませんでした。
そのため、幼稚園に入園し先生から「発達検査に行かれてみては」と言われて、はじめて支援につながりました。

こればかりは今振り返っても、もっと早いタイミングで療育に行っていれば良かったのか、そうだとすればいつがベストだったのか、考えても考えても分かりません(笑)
わが家のように「なんか発達に不安があるけど、何も指摘されない」という状態が続いている場合、なかなか支援を依頼するタイミングが掴めないですよね。
でも実際に療育を利用して分かったのは、専門機関に相談すれば、診断名がついていなくても支援につながれる可能性があるということ。
診断名がつかない、小児科や保健師さんから発達について何も指摘されないということは、今すぐに療育につながらなくても問題ない状態なのかもしれません。
親御さんが「心配だから今から療育に行かせておきたい」と思う場合、その旨を相談すれば希望が通る可能性があります。
「治るかも」と思っていたこと
まめの発達障害は、ゆるやかに特性があらわれていきました。
0歳のときにわたしが何となく勘づき始めたのは事実ですが、1歳半検診でも3歳児健診でも指摘されたことはなく、周囲からは「考えすぎじゃない?」と言われたことも。
幼稚園に入ってASDの傾向が少しずつみられるようにはなりましたが「手に負えないほどの特性」ではなかったため、
「小学校に入ったら落ち着くかな?」
と思っていたところがあります。
それでも療育には週4~5日行っていましたし、常に専門家とつながる体勢を整えていたので、決して「発達障害を放置していた」というわけではありません。
でも、今考えると「治るかも」と思っていた当時の自分には、少なからず誤った認識があったと思います。
心のどこかで「治るかも」と思っていると、どうしてもそれが態度やしつけに出てしまっていたのではないかなと、反省することも。
「治るかも」とわずかな希望に光を見出そうとしていたのは、わたしがまめの発達障害を受け入れる「段階説」を行ったり来たりしていた時期だったのだろうと思います。

それでも、当時はベストを尽くしていたので本当に自分はよく頑張りました!笑
まとめ
発達障害の特徴が1歳でみられる場合のようすや、親御さんができることについてまとめました。
発達障害は、ASD(自閉スペクトラム症)という種類の特性が、1歳児にみられやすいといわれています。
この記事でご紹介した特徴に当てはまるものがあれば、注意深くご家庭で様子を見たり、専門機関に相談したりしてみてください。
発達障害であっても、国や自治体の絶え間ない支援や福祉サービスを受けることができます。
受け入れるのは簡単ではありませんが、子どもが少しでも生きやすくハッピーな人生になるよう、前向きな選択をしていきましょう!
よく読まれている記事




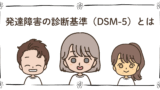
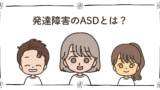
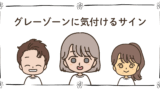
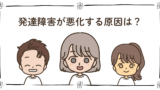

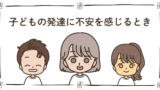
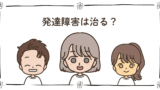
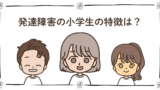
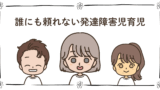
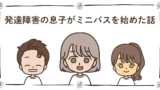
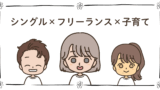
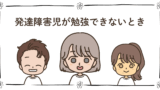
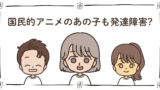

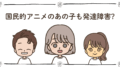


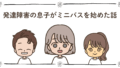
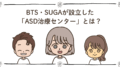
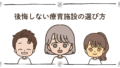
コメント