発達障害のある子どもを育てる母子家庭では、療育や通院、教育のサポートにかかる費用が大きな負担となることがあります。
医療費や療育費に加え、学童や放課後等デイサービスなどの利用料も重なり「家計が追いつかない」と感じる方も少なくないでしょう。
そんなときに支えになるのが、国や自治体が用意している各種助成金や制度です。
この記事では、母子家庭が利用できる代表的な助成金の種類や申請の流れを、実際の体験談を交えながらわかりやすく解説します。

発達障害児×母子家庭の経済的負担

発達障害のある子どもを育てる母子家庭では、通常の子育てに加えて特有の経済的課題を抱えることがありますよね。
教育や医療の選択肢が広がる一方、その分費用も増えます。
家計への影響は大きくなりますよね。
では、具体的な負担の種類を整理してみましょう。
医療費・療育費の負担
発達障害の診断や治療、療育のために、定期的な通院や専門的な支援が必要なことがあります。
発達検査、リハビリ、療育施設の利用などは自己負担額が積み重なり、経済的な負担となりやすい部分ではないでしょうか。
自治体の医療費助成があっても、交通費や付き添いのための時間的コストも含めると、大きな負担になるでしょう。

母子家庭だとママは仕事も大忙し!
時間はお金で買えないし、毎日てんてこ舞いだよ~💦
教育費の増加
支援学級や特別支援学校、民間の療育機関などを利用する場合、通常の教育費以外に教材費や通所費用が発生します。
また、学習塾や家庭教師などの学習サポートを検討する家庭もあるかもしれません。
子どもの特性に合わせた教育支出は、母子家庭にとって大きな出費となり得ます。

発達障害児の学習サポートなら、普通の塾よりも放課後等デイサービスの塾がおすすめ!

ぼくも通ってるよ~!
就労との両立による収入制限
母子家庭では、母親が生計を支える中心となりますよね。
しかし、発達障害児の育児や療育のためにフルタイム勤務が難しいケースもあるでしょう。
短時間勤務や在宅ワークに限られることで、収入が制限されている人もいるのではないでしょうか。
結果的に、家計の安定が難しくなる状況が生じます。
日常生活費への影響
発達障害のある子どもは、感覚過敏や食事のこだわりが強い場合があります。
そのため、日常生活において特別な食べ物や生活用品を選ばなければいけないこともありますよね。
また、学童や放課後等デイサービスを利用する際の費用も加わり、日常生活にかかるコストが一般家庭より高くなる傾向があります。
発達障害児×母子家庭で使える助成金一覧

発達障害児を育てる母子家庭で、申し込み可能な助成金をまとめてみました。
まずは一覧表でご紹介しますので、該当する助成金があるかどうかチェックしてみてくださいね。
| 制度名 | 母子家庭 | 障害児家庭 | 両方に該当時の申請可否・優先度 |
|---|---|---|---|
| 児童手当 | ○ | ○ | 重複可。 障害有無や家庭状況問わず受給可能 |
| 児童扶養手当 | ○ | △ (ひとり親の場合のみ) | 母子家庭かつ障害児なら 支給額は変わらず受給可能 |
| 特別児童扶養手当 | × | ○ | 重複可。 障害の等級により支給額変動 |
| 障害児福祉手当 | × | ○ | 重複可。 常時介護が必要な場合対象 |
| 医療費助成(子ども医療費) | ○ | ○ | 重複可。 自治体ごとに年齢上限や負担額異なる |
| 自立支援医療 (育成医療・更生医療・精神通院医療) | × | ○ | 重複可。 医療費自己負担を軽減 |
| 特別支援学校就学奨励費 | × | ○ | 重複可。 通学・給食・学用品等を補助 |
| 就学援助制度 | ○ | ○ | 重複可。 学用品費や給食費等を補助 |
| 高等学校等就学支援金 | ○ | ○ | 重複可。 所得に応じ授業料無償化 |
| 補装具費支給 | × | ○ | 重複可。 車椅子・補聴器など対象 |
| 日常生活用具給付 | × | ○ | 重複可。 入浴補助用具・意思伝達装置など |
| 公営住宅優先入居・家賃減免 | ○ | ○ | 重複可。 自治体による優先度の上乗せあり |
| 放課後等デイサービス利用料軽減 | × | ○ | 重複可。 受給者証により上限月額設定 |
| 出産育児一時金 | ○ | ○ | 重複可。 出産時に健康保険から支給 |
| 乳幼児おむつ・ミルク代助成 | △ (自治体による) | △ (重度障害乳幼児対象) | 重複可。 自治体独自制度のため要確認 |
では、ここから「母子家庭で申請できる助成金」と「障害児を育てる家庭で申請できる助成金」に分けて、ご紹介していきます。
母子家庭で申請できる助成金まとめ

それでは、上記の一覧表から母子家庭で申請できる助成金に絞って、くわしくご紹介します。
児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)などで、18歳に達する年度末までの子どもを養育している場合に支給されます。
支給額は所得によって変動し、満額の場合は子ども1人あたり月44,140円(2025年度現在)程度です。
第2子以降は加算がありますが、所得制限を超えると全額停止または一部支給となります。
申請は市区町村役場で行い、離婚や死別、認知、未婚出産などの事情を証明する書類が必要。

「児童手当」と似た名前ですが「児童扶養手当」はひとり親に限った制度です。
ひとり親の場合、児童手当と児童扶養手当を両方受け取ることができます!
児童手当
児童手当は、0歳から中学校卒業までの子どもを養育している家庭に支給される助成金です。
母子家庭であるかどうかは関係なく支給されますが、所得制限があります。
支給額は以下の通りです。
- 3歳未満:月15,000円
- 3歳以上〜小学校修了前:月10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生:月10,000円
所得制限を超える場合は、特例給付として月5,000円が支給されます。
申請は市区町村役場で行い、原則として子どもの出生や転入から15日以内の申請が必要です。
医療費助成
医療費助成制度は、18歳(または高校卒業)までの子どもの医療費自己負担分を、自治体が助成する制度です。
多くの自治体では、入院・通院・薬代を含め、無料または自己負担数百円で受診できます。
さらに母子家庭であれば、所得制限の基準が緩和される場合もあります。
対象年齢や負担額は自治体ごとに異なるため、問い合わせてみてくださいね。
利用には健康保険証のほか、医療証が交付されます。
経済的負担を大幅に軽減できるため、必ず申請しておきたい制度です。
就学援助制度
就学援助制度は、経済的に困難な家庭の小中学生に対して、学用品費、給食費、修学旅行費、通学用品費などを援助する制度です。
母子家庭は対象となることが多く、申請すれば受給できる可能性が高いでしょう。
支給額や対象経費は自治体によって異なりますが、給食費や学用品費の実費補助が中心となります。
申請は学校または教育委員会を通じて行い、所得証明書などが必要です。
年度途中でも家計状況が変わった場合に申請できるため、状況に応じて活用することが可能ですよ。

ひとり親になったことを学校に報告すると、学校側から就学援助制度の案内用紙が配布されると思います!
高等学校等就学支援金
高等学校等就学支援金は、公立・私立問わず高校や高等専門学校に通う生徒の授業料を、国が支援する制度です。
母子家庭の場合、所得制限に引っかかるケースは少なく、授業料の全額または一部が免除されることが多いようです。
公立高校では授業料が実質無償になり、私立高校では年間最大39万6,000円(2025年度)まで支給されます。
申請は学校を通じて行い、保護者の所得証明や課税証明書が必要となります。
教育費負担を大幅に減らせるため、必ず確認しておくべき制度ですね!
高等職業訓練促進給付金
母子家庭や父子家庭の親が、高等職業訓練校や専門学校、資格取得のための訓練に通う際に支給される給付金です。
受講中の生活費や学費を補助する目的で、原則として世帯の所得制限があります。
支給額は月額制で、通学交通費や教材費を含む場合もあるようです。
受講者は就職やスキルアップを目指すことが条件で、給付金は返済不要。
キャリア形成支援と、経済的負担軽減の両方を兼ね備えた制度ですね。
母子・寡婦福祉資金貸付金
母子家庭や父子家庭、寡婦が生活の安定や自立を目的に利用できる貸付金制度です。
住宅費、就学費、就職準備費など幅広い用途に対応しています。
低金利または無利子で貸し付けられ、返済期間や条件は貸付目的によって異なりますので、自治体にご確認くださいね。
自治体や日本政策金融公庫を通じて申請し、所得制限や資産制限があります。
経済的支援だけでなく、生活再建や自立支援の観点でも活用されていますよ。
入学祝い金・就学準備金
小学校、中学校、高校入学時に母子家庭や父子家庭の子どもを対象として支給される、祝い金や準備金です。
学用品や制服、通学用具の購入費用の補助を目的としています。
支給額は自治体によって異なり、1回限りの場合が多いようです。
申請するには、児童の在学証明書や保護者の世帯状況の確認書類が必要。
入学時の経済的負担を軽減し、子どもが安心して新学期を迎えられる支援です。
放課後児童クラブ(学童)利用料の減免
母子家庭や父子家庭を対象に、放課後児童クラブ(学童)の利用料を減免する制度があります。
減免率は自治体ごとに異なりますが、所得に応じて全額または一部が免除されることがあります。
学童保育は、共働き家庭やひとり親家庭の子どもの居場所を提供するために存在します。
その学童の利用料が軽減されることは、経済的負担の軽減と子どもの安全確保の両面で役立つでしょう。
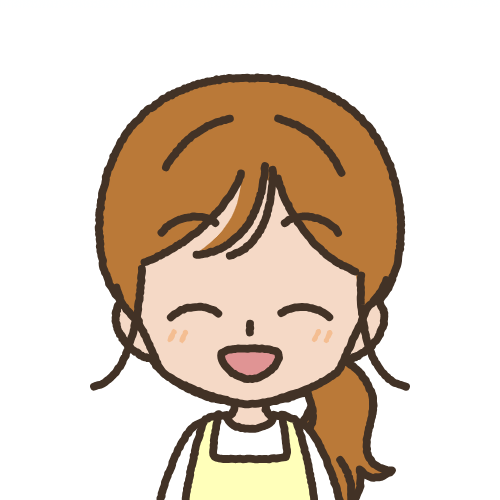
母子家庭は母親がフルタイムだから、学童はマスト。
利用料が減免されたら助かる~!
交通機関割引(バス・電車・定期券など)
母子家庭や父子家庭の保護者・子どもを対象に、公共交通機関の利用料金を割引する制度です。
通学・通勤用の定期券、バスや鉄道の運賃に適用されることがあります。
割引率や対象路線は自治体や、交通事業者によって異なります。
申請には母子家庭であることを証明する書類が必要で、日常の通勤・通学費用の負担を軽減する効果があります。

わが家のまめはまだ小4ですが、中学校は支援学級のある少し遠い学校を検討しているため、この制度を活用したい!
公営住宅の優先入居・家賃減額
母子家庭向けに、自治体の公営住宅で優先入居が認められる場合があります。
また、家賃減免制度がある自治体では、収入に応じて家賃の一部が免除されることも。
入居条件や減免額は自治体ごとに異なりますが、母子家庭は優先的に申込資格が与えられることが多いようです。
経済的負担を軽減する有効な手段となるでしょう。
申請は市区町村の住宅担当窓口で行い、所得証明や母子家庭であることを示す書類の提出が必要となります。
水道料金の減免
母子家庭や父子家庭が住む自治体で、水道料金の減免制度を利用できる場合があります。
世帯の所得に応じて、全額免除または一部免除されることも。
申請には母子家庭であることを証明する書類や、世帯の所得証明が必要となります。
生活に欠かせない水道料金の負担を軽減できるため、日常生活の安定に役立ちますね!

わたしたちの住む自治体では、この制度がなかった~(泣)
保育料の減免
母子家庭や父子家庭の子どもを対象に、保育園・認定こども園・幼稚園の保育料を軽減する制度です。
自治体によって減免率や対象年齢は異なりますが、全額または一部減免される場合があります。
申請には、所得証明書や母子家庭であることを示す書類が必要です。
保育料の軽減は、働く親の経済的負担を和らげ、就労支援にもつながりますね。
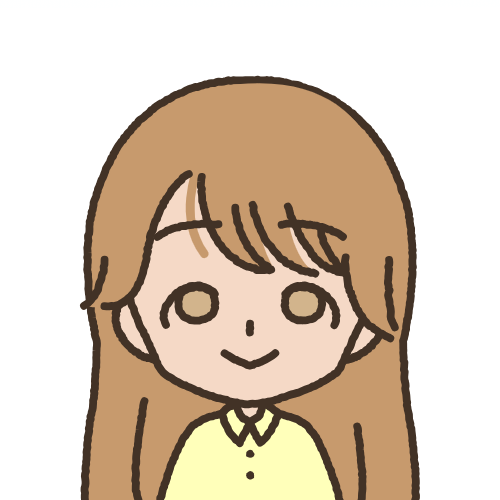
無償化にはなったけど私立だと少し足が出るから、さらに減免されるならありがたいね
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費助成制度は、母子家庭や父子家庭の子どもの医療費を自治体が助成する制度です。
自己負担分の医療費が無料または一部負担で済むため、通院や入院の負担が軽減されます。
所得制限はありますが、母子家庭は比較的利用しやすい条件が設定されていることが多いでしょう。
申請は自治体の窓口で行い、医療証が交付されます。

医療費の心配なく子どもの健康管理ができるため、早めに申請しましょう!
生活福祉資金貸付制度(母子家庭向け)
生活福祉資金貸付制度は、母子家庭が生活費や教育費、住宅費などの緊急・臨時的な支出に対応するための無利子または低利の貸付制度です。
通常、市区町村の社会福祉協議会が窓口となり、返済期間や金額は融資目的によって異なります。
母子家庭に特別枠がある場合があり、返済負担を軽減しつつ生活支援を受けられる点が特徴です。
緊急時の資金確保として、必要な場合には早めに相談しておきましょう。
障害児を育てる家庭で申請できる助成金まとめ

行政には、障害のある子どもや家庭の負担を軽減するための助成制度が用意されています。
制度を知り、正しく申請することで、大きな支援を受けることができるかもしれません。
ここからは、障害児を育てる家庭で申請できる助成金についてまとめてみましょう。
※一部、母子家庭の助成金と重複しているものがあります。
特別児童扶養手当
障害のある20歳未満の子どもを育てる家庭に支給される手当です。
障害の程度に応じて月額が決まり、所得制限があります。
生活費や教育費の補助として活用でき、子どもが日常生活で必要な支援を受けるための経済的基盤を整える役割があります。
申請は市区町村の窓口で行い、医師の診断書などが必要です。
障害児福祉手当
20歳未満の「重度障害児」を育てる家庭に支給される手当です。
特別児童扶養手当と併給可能で、日常生活の補助や医療・介護にかかる費用の補助として活用されます。
所得制限があり、申請は自治体で行います。
障害の程度に応じて金額が決まるため、生活支援として重要な制度となるでしょう。
児童育成手当(障害児育成手当)
児童育成手当は、母子家庭や父子家庭、または障害児を育てる家庭を対象に、子どもの養育費を支援するために自治体が支給する手当です。
通常、0歳から18歳未満の子どもを養育している世帯が対象となります。
支給額は自治体によって異なりますが、母子家庭の場合は月額数千円~数万円程度が一般的だそう。
また障害児育成手当として、障害のある子どもを育てる家庭には通常の児童育成手当に加え、加算や特別支給が行われることがあります。
申請は市区町村役場の福祉担当窓口で行い、所得証明書や障害を証明する書類が必要です。
経済的支援を通して、日常生活や教育環境を安定させられるのが大きなメリットですね!
児童手当(※母子家庭助成金と重複)
0歳~中学生までの子どもを育てる家庭に支給される手当です。
所得制限がありますが、子ども1人あたり月額が決まっており、教育費や生活費の補助として活用できます。
障害の有無に関係なく受給可能で、申請は自治体で行います。
障害基礎年金(子の加算)
障害基礎年金を受給している親が、18歳未満の子どもを育てている場合に加算される制度です。
母子家庭・父子家庭の生活支援や、教育費補助として役立ちます。
所得や年金加入状況に応じて、金額が変わる場合があります。
申請は日本年金機構を通じて行い、手当と併用可能です。
自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)
障害児や障害者が必要な医療を受ける際、自己負担を軽減する制度です。
精神科や心療内科などで継続的に医療を受ける場合、自己負担を原則1割に抑えることができます。
発達障害のある子どもにも適用されるケースがあり、多くの家庭で利用されています。
育成医療は18歳未満の障害児向け、更生医療は身体障害者向け、精神通院医療は精神障害者向けです。
医療費助成(重度心身障害者医療費助成制度)
重度心身障害のある子どもを対象に、医療費の自己負担を助成する制度です。
自治体によって名称や内容が異なるため、くわしくは自治体窓口で問い合わせてみてくださいね。
「マル障」と呼ばれる制度では、子どもの医療費自己負担分が助成されることがあります。
所得制限がある場合もありますが、医療費が全額または一部免除されます。
申請するには、医師の診断書や障害者手帳などが必要です。
特別支援学校就学奨励費
特別支援学校に在籍する児童・生徒に対して、学用品や通学費、学校生活に必要な費用を補助する制度です。
自治体により対象範囲や金額が異なりますので、くわしくは自治体窓口に問い合わせてみてください。
生活費や教育費の負担軽減を目的としており、申請は学校や自治体窓口で行います。

特別支援学校に在籍している子どもが対象なので、多くの場合学校から案内されるようです!
高等学校等就学支援金
高校や高等専門学校に通う子どもを持つ家庭に支給される支援金です。
授業料や教材費の一部を補助し、所得制限があるので注意が必要でしょう。
母子家庭の場合は減免措置と組み合わせて受給できる場合があります。
申請は学校経由で行い、就学継続の経済的支援として活用されています。
補装具費の支給
身体障害のある子どもが使用する義肢、装具、車椅子などの購入・修理費を補助する制度です。
障害の程度や種類によって支給内容が決ま、所得制限がある場合もあります。
生活の自立支援や学習・移動の補助として重要な制度ですね。
日常生活用具給付
障害のある子どもが日常生活を送るために必要な用具(手すり、歩行補助具など)を自治体が給付、または貸与する制度です。
家庭の経済負担を軽減し、生活の自立や安全確保をサポートしてくれます。
申請は、自治体の福祉窓口で行います。
通学・通所交通費助成
障害児が、学校や療育施設に通う際の交通費を補助する制度です。
対象は通学距離や所得によって異なり、バス・電車・タクシー利用の費用が支給される場合があります。
生活の負担軽減や、教育機会の確保に役立ちます。

障害があると近隣の学校に通えないこともあるから、交通費補助があると助かるね
放課後等デイサービスの利用料軽減
障害児が放課後や長期休暇に通う、デイサービスの利用料を減免する制度です。
所得に応じて、全額または一部免除される場合があります。
申請は自治体や施設で行い、保護者の就労支援や子どもの居場所確保に貢献しています。
療育手帳・身体障害者手帳所持者向け割引
療育手帳や身体障害者手帳を持つ子どもを対象に、公共施設・交通機関・イベントなどで割引が適用される制度です。
学習・余暇・移動の負担軽減に役立ち、原則、所得制限はありません。
申請は、自治体で療育手帳や身体障害者手帳を取得したときに行います。
公営住宅の優先入居・家賃減免
母子家庭や障害児家庭が対象で、公営住宅への優先入居や家賃減免が受けられる制度です。
所得制限があり、入居条件や減免率は自治体によって異なります。
生活費負担の軽減や、住環境の安定を目的として活用されています。
紙おむつ・ミルク代の助成
障害児家庭や母子家庭向けに、紙おむつや粉ミルクの購入費用を補助する制度です。
所得や障害の程度に応じて支給されます。
申請は自治体で行い、日常生活にかかる消耗品費の負担を軽減するための支援です。
【体験談】わが家で申請した助成金

ここからは、私が実際に利用した医療費助成の申請体験をお伝えします。
わが家では当初、まめに診断名がついていませんでした。
そのため、まず母子家庭で受けられる助成金を申請。
その後まめに診断名がついてから、障害児育児の助成金を申請したという順です。
\ 申請した助成金はこちら /
- 児童扶養手当
- ひとり親家庭等医療費助成制度
- 就学援助制度
- 入学祝い金
一番大きいのは、児童扶養手当と医療費助成制度です。
児童扶養手当は隔月で助成を受けられるので、わが家では貯蓄にまわしています。
医療費助成は、もともと中学校卒業まで数百円はかかる自治体なので、それが無料になるのはありがたいこと。
子どもの診察料や薬代がかからないので、体調やケガが心配なときいつでも病院に行くことができて、本当に助かっています。
ひとり親家庭等医療費助成制度は、親の医療費も無料になります。
わたしは健康だけが取り柄なのであまり病院には行かないのですが、ひとり親である以上、わたしが倒れるわけにはいかない!
そんなシングルマザーの心強いお守りになっています。

現在申請中の助成金もあるので、随時追記していきます!
これから申請する方へ

上記でご紹介してきたように、発達障害児を育てる母子家庭で申請できる助成金は多くの種類があります。
自分たちにどの制度が適用されるのか、どの助成金にどの制限があるのかわからないものもあるでしょう。
これから助成申請を考えている方へ、いくつかのポイントをご紹介します。
まずは相談窓口に行ってみよう
全国で多くの助成金を提供していますが、自治体によって適用されるものとそうでないものがあったり、制限が異なったりします。
そのため、自分で申請できる助成金を絞り込むのではなく、まずは市区町村の福祉課や子育て支援センターに相談してみましょう。
窓口で詳しい家庭の状況(母子家庭であることや、所得状況など)を説明すると、申請に必要な制度や書類を教えてもらえるでしょう。

本格的に相談したい人は、事前予約して席を確保しておいてもらおう!
早めの準備で損を避けよう
各助成金を申請するには、医師の診断書や住民票、所得証明書などが必要な場合があります。
取得までに時間がかかることもあるので、早めの準備を心がけましょう。
受けられる助成金の存在に気が付かず、数年過ごしてしまった…というパターンも少なくありません。
数年遡って申請できるものもありますが、早いに越したことはありませんよね。
この記事でご紹介している助成金をメモして、自分の家庭にどれが適用されるのかさっそく確認しましょう!
書類の控えはコピーしておこう
提出した書類が紛失されるリスクもあるため、必ず控えを手元に残しておきましょう。
特に「発達障害児×母子家庭」の場合は、適用される助成金が多くなる可能性があります。
どの助成金を申請したのかあとで整理できるよう、コピーを揃えておくことをおすすめします。

発達障害児×母子家庭は毎日がバタバタ!
正直、書類を整理している暇もないよね…
コピーを取っておくだけでも、のちのち楽ですよ
まとめ|助成制度を活用して負担を減らそう
発達障害児を育てる母子家庭にとって、各助成制度は大きな支えになります。
わたし自身、制度を知ってから経済的にも精神的にもかなり救われました。
申請は少し手間がかかりますが、知っているか知らないかで数万円以上の差が生まれることもあります。
ぜひ一度、お住まいの自治体の制度を確認してみてくださいね!

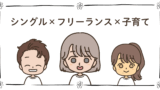
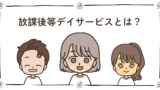
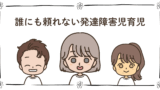

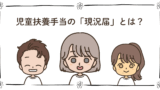
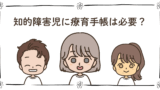
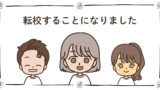

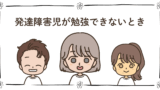
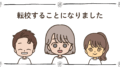
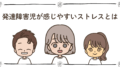
コメント