発達障害のある小学生の中には、集団生活の中でコミュニケーションにつまずく子が少なくありません。
友達とうまく話せない、会話がかみ合わない、孤立してしまう…
親御さんはそんな子どもをどう支えたらいいか悩んだり、本人が傷つかないか心配したり…
胸が張り裂けそうになることがありますよね。
この記事では、発達障害・知的障害をもつわが子がコミュニケーションでつまずいた経験をもとに、家庭でできるかかわり方や、学校・支援機関の活用法をご紹介します。
コミュニケーションが苦手な小学生、発達障害をもつ小学生が、少しでも快適に学校生活を送れるよう、さまざまな方法を模索していきましょう!

発達障害の小学生はなぜコミュニケーションが苦手?

発達障害のある子どもは、対人関係や会話のやりとりに苦手意識を持つことがあります。
特に小学生になると、集団生活が本格化します。
単なる「コミュニケーション」ではなく、係の仕事や複雑な友達関係が絡んでくることもありますよね。
徐々にコミュニケーションの難易度が上がり、友達ができなかったり、話しかけられなかったりすることが増えるかもしれません。
コミュニケーションの難しさが、思わぬトラブルにつながることもあるでしょう。
会話のキャッチボールが難しい
発達障害をもつ小学生は、相手の言葉に反応できなかったり、一方的に話してしまったりすることがあります。
いわゆる「会話のキャッチボール」がうまくいかず、ボールをキャッチできなかったり、まったく違う方向にボールを投げてしまったりすることがあるのです。
「話す・聞く・返す」というやりとりのテンポが合わず、周囲から「変な子」と誤解されてしまうこともあるでしょう。
特にASD(自閉スペクトラム症)を持つ子、またそれに知的障害が伴う子は、会話のキャッチボールが苦手である傾向があります。
わが家のまめも、幼児期からASD傾向が強かったので、特に同年代のお友達とのやりとりが難しかったようです。

発達検査をしてもらったとき「先生とのやりとりは問題ないが、同年代のお友達とのコミュニケーションが難しい」という指摘をされました
先生とのやりとりができているということで安心しがちですが、そこが盲点だったりします。
なぜかというと、先生は子どもとのやりとりが上手だからです。
「子どもの発達が正常だから先生とスムーズにやりとりができる」のではなく、先生が器用に汲み取ってくださっていることが理由になっているケースがあります。
それを「先生とのやりとりが問題ないなら大丈夫」と判断しないことが大切だと感じました。
同年代のお友達とのやりとりは、発達障害の有無にかかわらず、難しいものがあると思います。
特に小学生の場合、まだ心も未発達で、スムーズなコミュニケーションができないこともあるでしょう。
それでも、年齢相応のコミュニケーションや「お友達にかかわろうとする姿勢」がみられないのが、発達障害の特性です。
たとえば、以下のような特徴です。
もちろん、この中には個性の範囲であるものもあります。
しかし発達障害の特性により、会話のキャッチボールが成り立たないケースも多く発生します。
空気が読めず誤解される
発達障害をもつ小学生は、空気が読めずに誤解されることがあります。
たとえば、ふざけてはいけない場面で笑ってしまったり、相手の気持ちに気づかずに発言してしまったり…。
その結果、意図しない形で相手を怒らせてしまうこともあるかもしれません。
この特性は、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如多動症)などにみられるもので、本人に悪気はありません。
ASDの場合は、他人の気持ちをくみ取ったり想像したりするのが苦手で、思ったことを正直に言ってしまうことがあります。
上記のような、発言の前に考えるべきことを想像するのが苦手なため、思いついたことをポンポンを発言してしまう傾向があるのです。
また、ADHD(注意欠如多動症)の場合は、多動性や衝動性という特性があるために、考える前に口から言葉が出てしまうこともあるでしょう。

言葉にする前に一瞬でも「これは言っていい言葉かな?」と考えられれば良いのですが、それが難しいのが発達障害の特性なんですね
このため、発達障害をもつ小学生は「空気が読めない発言をする」というイメージを抱かれることがあるのです。
友達との距離感がわからない
発達障害をもつ小学生は、友達との適切な距離感がわからないことがあります。
たとえば、相手が嫌がっているのにスキンシップを取ろうとしたり、まったく仲良くないグループに無理やり加入しようとしたり…
小学生のうちは物理的な距離感、思春期以降には精神的な距離感でも課題が見えてくるそうです
一見、子どもらしい無邪気な行動のようにも見えますが、された側の気持ちになると不愉快であるケースも。
相手も同じ距離感を好む場合は仲良くなれますが、急にハグされるのを嫌う人もいますし、友達同士で手をつなぎたくない子もいるでしょう。
特に昨今は「性犯罪」に関する教育にも注目が集まっており、小学生のうちから他者との距離感について学ぶ機会が多くあると思います。

ぼくのクラスでも「肩を叩いて友達を呼ぶとき以外は、人に触らない」というルールがあるよ
発達障害があると、相手の気持ちを考えた行動が難しいため、自分が「この子が好きだからハグをしたい!」と思ったらすぐに行動に出てしまったりするのですね。
わが家でも、お友達との適切な距離感に関しては長く課題になっていました。

現在小学4年生になって、少しずつ学んでいるかな…という感じです
発達障害のある小学生が学校で困りやすいこと

小学校では、勉強以外にも多くのコミュニケーションの場面があります。
そこで生じるストレスやトラブルは、子どもにとって大きな負担となることも。
わが家のまめは、現在小4。
小学校に入学してから経験した困りごとについて、シェアしていきたいと思います。
休み時間に孤立する
まめは、幼児期から小学校に上がってもなお、友達が少ないままです。
もともとわたしは「友達は多い方がいい」と考えていたわけではないので、自分の好きなように過ごしていれば良いと思っています。
それでも、やはり友達が少ないのは発達障害の特性ゆえだろうな、と思うことがあります。
同年代のお友達と遊ぶのが難しかったり、周囲から誘ってもらえなかったり、自分からも誘えなかったり…

発達障害の特性があると、周囲からも「変わった子」と思われることがあり、なかなか集団になじめないことがあります。
本人がそれで良ければ、まったく問題はないでしょう。
しかし、もし
「自分も友達の輪に入りたい」
「なぜ自分だけ誘ってもらえないのだろう」
と思っていたら、それが原因で自己肯定感が下がったり、学校生活が楽しくなくなったりするかもしれませんよね。

友達とのかかわり方は、発達障害云々ではなく実際に学校で経験して学ぶべきだ、という考えもあると思うので、わたしは何でもかんでもお膳立てしたくはないと思っているのですが…
グループ活動で孤立する
学校でグループ活動をする際、発達障害があって輪に入りにくい子は、孤立することがあります。
小学校1~2年生くらいまでは、ペアを作るにも先生がフォローしてくれたり、出席番号順など指定をしてくれたりするかもしれません。
しかし、学年が上がると「自分でグループを作る」「自分でペアを探す」というやり方を採用する先生も増えてきます。
ペア探し、苦手な人も多いのではないでしょうか。
わたしも苦手でした。
しかし、わたしの場合は発達障害ではなく「わたしと組むの嫌だったらどうしよう」と気にしすぎて、なかなか声をかけることができなかったタイプ。

どちらかというとわたしは、HSC傾向のある子どもだったかもしれません

発達障害の特性によっては、グループ活動で孤立する理由が本人にもわからなかったり、悪気はなくても他のグループに入ろうとしてしまったり、独特の解釈をすることがあるでしょう。
まめは基本的に「自分も友達も仲間はずれはよくない」と思うタイプなので、友達を避けたりすることもありませんでしたが、同じように自分も友達から避けられることがないと信じていました。
しかし小学生の友達関係って、そう簡単ではないですよね。
まめは、自分も入れてもらえると思ってほかのグループの遊びに勝手に加わり「何?」「なんであなたがいるの?」という扱いを受けてしまうことがありました。

まめ本人は「楽しそうだから入れてもらおう!」という純粋な気持ちで飛び込んでいくのですが、相手グループからすれば「なんか急に入ってきた…」と困惑しますよね
発達障害には、このように人との距離感が掴みにくいという特性があります。
そのため、絶妙に空気を読み「その場で適切な行動をとらなければいけない」集団生活においては、ハードルが高いこともあるでしょう。
からかわれる
発達障害の特性により、発言や行動が周囲とズレてしまうがあります。
それが原因でいじられたり、からかわれたりすることがあるかもしれません。
周囲の子には、悪気がない場合もありますし、ミスコミュニケーションが原因でふとした言葉に傷ついたりすることもあるでしょう。

過度なからかいはいじめにつながるので、決してふざけ半分であっても許されることではないと思います。
しかし、からかいが始まるきっかけが、発達障害児の問題行動であるケースも多くありました。
そのため、必ずしも「健常児が発達障害児をからかっている」という構図なのではなく、最初に発達障害児が問題行動をしたために、健常児が怒りをあらわにしたというパターンもあるのだと、頭に入れておかなければならないな、と感じました。
発達障害の有無は関係なく、小学生のコミュニケーションはまだ未熟な部分もあり「からかい」「注意」「いじめ」などの区別がつきにくいことも。

結局そういうコミュニケーションも、学校で実際に体験して学ぶしかないとわたしは考えています
友達トラブルが起こる
発達障害の特性が、思わぬ友達トラブルを起こしてしまうことがあります。
現在、まめが小4になり、わが家では少しずつトラブルが減っているような気がします。
しかし、小学校1~2年の頃はしょっちゅう学校から電話があり、トラブル相手に謝罪行脚に出向くという日常でした。

当時のまめは自分のやりたいように振る舞っていましたが、現在はだいぶ空気を読んで行動できるようになった気がします
友達トラブルは、親御さんが未然に防げるものではありません。
正直、何かが起こったあとの対応をするというかたちになってしまうのは、仕方ないことなのだと学びました。
日ごろのかかわり方や声かけ、習慣づけなどが功を奏し、適切なコミュニケーションを習得できることはありますが、そううまくはいきません。
学校でも、先生がずっとついているわけではないので、完全に防ぐことは難しいのです。
友達トラブルについては、家庭でフォローできることが限られているというのも、まだまだわが家の課題です。
先生との相性が悪い場合がある
発達障害がありコミュニケーションが苦手だと、先生との相性もよくチェックしたいところ。
特に公立小学校だったり、通常学級だったりすると、発達障害に理解のない先生もいます(正直な話)。
指示の意味が分かりづらかったり、曖昧な表現を理解できなかったりすると、先生がきつく当たることも。
発達障害をもつ子ども本人は叱られる理由がわからず混乱し、かえってパニックになることもあるかもしれません。

公立小学校の先生って、意外に発達障害のことをご存じない人が多いんです。
専門外なのでそれは全然良いんですが、子どもとは向き合ってほしいですよね
まめはこれまで、運が良いのかどうなのか、ずっと女性の先生が受け持ってくれています。
先生のタイプをまとめると、以下のような感じです。
それぞれの先生に魅力があり、まめの苦手なことよりも得意なこと、好きなことに目を向けてくれる方ばかりでした。
そのため、コミュニケーションが得意ではないまめも、安心して学校生活を送ることができています。
発達障害の小学生が安心できるかかわり方とは

発達障害を持ちコミュニケーションを苦手とする小学生は、対人関係の失敗やトラブルへの恐怖心を感じやすくなります。
「コミュニケーションが苦手だから人に話しかけないでおこう」
「どうせトラブルになるから友達はいらない」
というふうに、学校や友達関係を心地悪く感じてしまうことがあるかもしれません。
周囲の大人は、そんな子どものできないことを責めるのではなく「どうすればやりやすくなるか」を一緒に考えてみましょう。
子どもにコミュニケーションを教えるのは、発達障害があってもなくても大変なことですよね。
でも、親御さんが「常に味方をしてくれている」と子どもが感じられれば、少しずつ自信をつけて前に進めるかもしれません。
もちろん、無理に明るく元気な性格になる必要はありません。
しかし、人は1人では生きていけませんから、生きるためのコミュニケーションは必要なのです。
子どもと一緒に一歩一歩進んでいくつもりで、寄り添うことを意識しましょう。
間違えても大丈夫と伝え続ける
発達障害のある子どもは、過去の失敗経験や指摘に敏感です。
「また間違えたらどうしよう」と萎縮してしまうことがよくあるかもしれません。
特にコミュニケーションは明確な正解がないので、難しいですよね。
言葉の選び方やタイミングに自信が持てず、話すこと自体を避けてしまうこともあるでしょう。
そんなときは「間違えても大丈夫」「ゆっくりでいいよ」と、安心できる言葉を繰り返し伝えてあげましょう。
失敗しても受け入れてもらえるという実感が、少しずつ挑戦する気持ちにつながっていきます。

療育でよく先生たちがしてくださっていた対応です。
小学生になると、コミュニケーションの失敗で怒る先生も出てくるから、その場合は対応を改めてもらえるようお願いしてみるといいかも
本人の得意なことから話題を広げる
発達障害のある子どもは、自分の好きなこと・得意なことになると驚くほど集中力を発揮します。
特にASDは得意分野と苦手分野がはっきりしていますし、ADHDは好きなことに過集中することもありますよね。
それは、本人が安心して話せる話題として大切な情報です。
本人の得意なことから対話をスタートすれば、自信を持ちやすくなるでしょう。
また、大人がその興味に関心を示すことで「聞いてくれている」と感じやすく、通じ合える喜びも実感できますね。
そこから少しずつ、学校生活や友達関係といった別の話題にも広げていくと、自然なコミュニケーション練習にもつながりますよ。
非言語コミュニケーションを練習する
発達障害を持つ子どもの中には、表情や身ぶりなどの「非言語コミュニケーション」が苦手な場合があります。
たとえば、相手の表情を読み取るのが難しかったり、自分の気持ちを表情でうまく伝えられなかったり…。
そんなときは、絵カードや鏡を使って「この顔はどんな気持ちかな?」「今、どんな表情しているかな?」と遊びながら練習してみましょう。
負担なく遊びながら取り組めますし、大人がオーバーに表情やジェスチャーを見せるのも、理解の手助けになります。

お母さんと絵カードで遊んだやつだ!お母さんが変顔ばっかりして面白かったよ(笑)
学校や支援機関と連携がマスト

発達障害のある子どもへの支援には、家庭だけで抱え込まず、学校や支援機関との連携が欠かせません。
子どもが安心して過ごすためには、家庭と学校、支援者の間で情報を共有し、環境を整えていくことが大切です。
複数のサポートが用意されていますので、適切なものをつなぎながら、子どもに合った支援体制をつくっていきましょう。
通級指導や特別支援学級の活用
通級とは、通常学級に在籍しながら、専門の先生がコミュニケーションに関する支援を個別に行ってくれる制度。
特別支援学級は少人数で丁寧に、より手厚い支援を受けられる学級のことです(特別支援学級が用意されていない学校もあります)。
発達障害のある子どもには、通常学級だけでは支援が行き届きにくいことがありますよね。
いずれも子どもに合った学び方を支える制度なので、学校や教育委員会と相談しながら、最適な方法を検討してみてくださいね。
学校との情報共有で安心感をつくる
担任の先生に子どもの特性をくわしく共有することや、自宅で実践している対応やかかわり方を共有するのも大切です。
トラブルの予防につながりやすく、また先生が子どもにかかわる際に安心する要素にもなるでしょう。

先生も、発達障害を持つ子の性格も何も知らないよりは、情報収集してから関われば仲良くなりやすいし、子どもも先生に心を開きやすいですよね
学校での様子と家庭での様子が異なることは、発達障害のある子どもにとってよくあることです。
そのため、家庭と学校の情報を共有し合うことはとても重要なんですね。
たとえば「朝なかなか登校できない」「苦手な教科で混乱してしまう」といった家庭での気づきは、学校生活への支援につながります。

また、学校での出来事を保護者が把握していると、子どもも安心するでしょう。
連絡帳や個別面談を活用して、先生とこまめにコミュニケーションを取るようにしましょう。
放課後等デイサービスを活用する
放課後等デイサービスは、発達に課題のある子どもが利用できる福祉サービスです。
放課後等デイサービスではSST(ソーシャルスキルトレーニング)や運動療育、学習支援など、事業所ごとにさまざまなプログラムが用意されています。
発達障害を持つ子の社会的自立を促すだけでなく、家庭や学校以外の居場所としての役割も果たします。
また、専門職による支援を受けながら、人との関わり方を少しずつ身につけられる施設もあります。

すべての放課後等デイサービスでSSTを提供しているわけではないので、必ず見学に行ってプログラムを確認してくださいね!
自治体で「受給者証」を申請すれば利用可能になるので、検討してみる価値は十分あるでしょう!
まとめ
発達障害を持つ小学生のコミュニケーションについて解説しました。
発達障害は脳機能の障害で、日常生活や習慣、そして対人コミュニケーションに影響することがあります。
小学生という繊細な年齢だと、コミュニケーションが苦手なことでどんどん自分の中に閉じこもってしまうこともあるでしょう。
無理に明るく振る舞う必要はありませんが、生きるためのコミュニケーションを学べるよう、周囲の大人が環境を整えたり、サポートしてあげることが大切ですね。

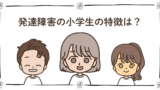


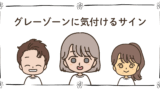

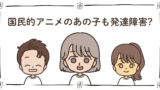
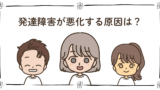


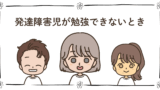

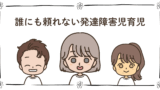
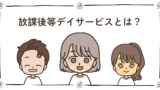
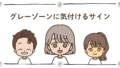
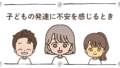
コメント