「下校の時間になっても帰ってこない」
「学校から“いなくなった”と連絡があった」
そんな経験がある親御さんは、どれほどの不安を感じたことでしょうか。
わたし自身、発達障害のある息子・まめが集団下校中に行方不明になったという出来事を経験しました。
一瞬で頭が真っ白になり「もし事故に遭っていたら…」という恐怖に支配された数十分は、今でも忘れられません。
この記事では、そのときの状況と、なぜそうなったのか、そして二度と同じことが起きないために私が取った対策についてお伝えします。
小学校入学前のお子さんをもつ親御さんが、このエピソードで少しでも安全への意識を高めてくだされば幸いです。

わが家で起きた「下校中の行方不明事件」まとめ

わが家の息子・まめは発達障害を抱えています。
そんなまめが小学校に入学し、わたしは毎日ヒヤヒヤ。
それでも、娘・ナツの幼稚園もあるし、仕事もあるしで、なんやかんや忙しい日々を送っていました。
そんな中、小学校入学から2年足らずで3回もの行方不明騒動が起きています。

その都度対策をとっても、繰り返される子どもの奇行。
わが家に起きた3回の行方不明騒動をシェアしたいと思います
入学早々「集団下校」で行方不明に
まめとナツが通う小学校では、入学後しばらく集団下校があります。
地域柄、登校班がなく各自で学校に行かなければならないので、朝は親が送り、帰りは集団下校(先生の引率つき)で帰ってくる。
それが2週間ほど続きます。
まめの行方不明騒動第1回目は、そんな集団下校の最中に起こりました。

集団下校初日、わたしはまめの指定通学路である「あかコース」の待ち合わせ場所で帰りを待っていました。
しかし、下校時間から30分以上経っても誰も来ません。
まめはおろか、集団下校のグループ自体が待ち合わせ場所に来ないのです。
わが家は学区の端の方に住んでいたので、その待ち合わせ場所にはわたししかいませんでした。
そのため、わたしの想像としては、ほかの生徒たちが続々と親御さんの待つ場所に送り届けられたあと、まめと先生だけで歩いてくるものだと思っていました。
しかし、誰も来ない。
いよいよ不安になり学校に問い合わせてみると…
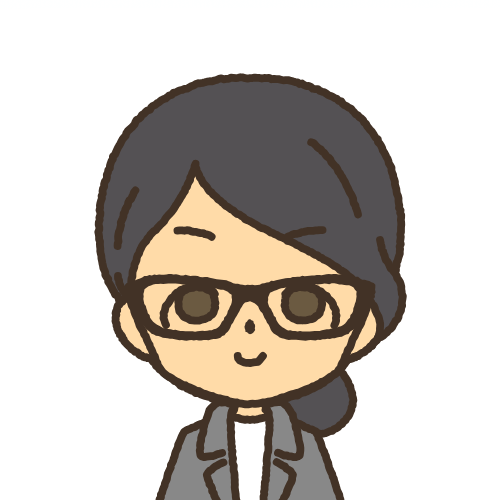
まめ君のグループは、まめ君以外全員が親御さんの元へ帰ったので、〇〇交差点で解散となりました

はい???解散…???
うちの子がまだ送り届けられてないのに、ですか?
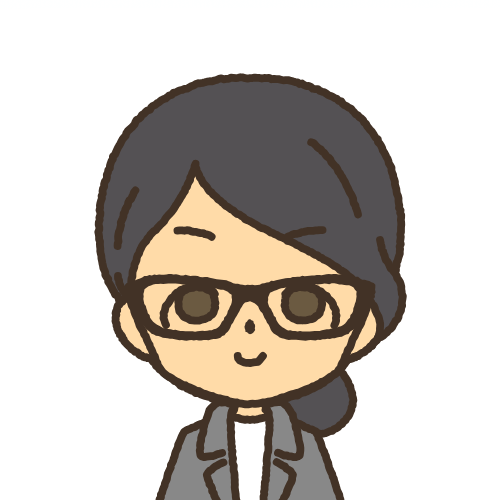
教員が「ここから1人で帰れる?」と聞いたら「うん」というので、そこで教員は引き返しました
なんということでしょう…!!!
集団下校のはずなのに、まめは親元に送り届けられないまま1人にさせられていたそうなんです。
いろいろ言いたいことはありましたが、まずはまめを探すのが最優先なので、それから1~2時間捜索活動。
最終的に家に戻ると、ドアの前でわたしの帰りを待つまめを発見したのでした。

そんなこんなで、まめは集団下校という安全であるはずの状況下で、迷子になってしまいました。

結果論でしかありませんが、小学校入学後初のヒヤリハット案件でした…
初めてのお友達と寄り道して行方不明に
2度目の行方不明騒動は、1年生の1学期。
まだまだ学校に慣れず、登下校もヒヤヒヤ(わたしが)が残る時期でした。
いつものように学校が終わり、帰りを待っていましたが、一向に帰ってきません。

あまりに遅いので学校に問い合わせてみると、担任の先生が一緒に探してくれるとのこと。
近所のコンビニで待ち合わせをし、手分けしてまめを探すこと30分ほど…
学校に「まめが見つかった」と連絡が入ったそうで、先生と一緒に学校に向かいました。
すると、隣のクラスのお友達と、そのママさんと一緒に待っているまめの姿が。

何かあったら…という思いで探していたので、元気そうな姿を見て安堵したのを覚えています
何があったのか聞いたところ、そのお友達とまめは一緒に帰っていて、お友達の家に行こうという話になったそう。
そのお友達の家に到着すると、ママさんが「まめ君のママがここに来ることを知らないなら、来てはいけないよ」と言ってくれたのです。
そして、そのママはまめが1人で帰れないかもしれないと考え、学校に連絡してくれたのでした。

平謝りしかできないわたしでしたが、そのママさんも

いえいえ、うちの子が「俺んち行こう」って誘ったみたいで…こちらこそすみませんでした
と、穏便に対応してくださいました。
そのお友達とは今も同じクラスで、ママさんとも

宿題の〇〇ファイルって何のこと?うち一度も持ち帰ってきたことないんだけど

私は〇〇ファイルっていう名前すら知らないwww
この間学校支給のタブレット壊して怒られたばかりだから、これ以上ダメージ負わせないでwww
と、男児ママ同士ため息をつく仲になりました。笑
GPSを置いたまま行方不明に
さて、まめの3度目の行方不明騒動は、小学校2年生になってからです。
小2になると、毎日まっすぐ帰れるようになり、時々学校併設の保育クラブで遊んでくることもありました。
2度目の行方不明騒動で懲りたわたしは、まめにGPSを持たせ、居場所はしっかり把握していました。
通学路から逸れたのを確認すると、自転車で様子を見に行くこともありました。

そんなこんなで、GPSのおかげで平和な毎日を過ごせていたある日、まめのGPSが見知らぬマンションで止まっていることに気づきました。

心配性な人ほど、この時点で冷や汗かきませんか?
わたしは心臓止まりました
そのマンションまで行くも、GPS情報だけでは階数などがわからないので何もできず。
「いよいよ警察に通報か?」と思った矢先、なんとまめのGPSからわたしのスマホに音声連絡が入りました。
相手はまめ…ではなく、お友達のママ。

すみません…まめ君とうちの子が、マンションのエントランスにランドセルを置いて虫捕りに行ってしまったみたいで…

そうでしたか…!
ご迷惑をおかけしてすみません。
虫捕りということは〇〇公園でしょうか?

私もそうだと思って見に行ったのですが、いませんでした
どこの公園に行ったのかわからないんです
まさかの、GPSを置いたまま行方不明に。
そして、わたしにはもう1つ懸念点がありました。
それはそのときに一緒にいたお友達が、重度のADHDだったことです。
そう、まめもその子も発達障害をもっていて、下手したら正常な判断ができない可能性があったのです。
まめにはASDとADHDがあり、虫捕りに夢中になるとどこへ行ってしまうか分からない。
お友達はADHDの傾向が非常に強く、1人で走ってどこかへ行ってしまい、3kmほど離れたスーパーで見つかったこともありました。
そんな2人が虫捕りに行ったら、行方不明になるに決まっています。

発達障害児ママであるわたしたちは、手分けして町中を探しました。
すると、いかにも虫がいそうな草原で、顔じゅう蚊にさされた状態で虫捕りに励む2人を発見。
何事もなく、2人とも家に帰ることができました。

当時を思い出すだけで5歳くらい老けそうです…
なぜ行方不明になったのか?振り返ってみた

ご紹介したように、わが家では3回もの行方不明トラブルが起きています。
これだけ聞くと、読者のみなさんは思うでしょう。
なぜ3回も起きるまで対策をしなかったのか?
しかし、わが家では1度目の行方不明トラブルから、しっかりと対策をしていました。
それでも、その抜け穴をするりを抜けていくように、子どもは次々に問題を起こしていきます。
発達障害児であるがゆえ、なおさら予想外の行動をとったのかもしれませんが、とにかく子どもが起こすトラブルは想像を軽く超えてきますよね。
わが家で行ってきた対策やその都度学んだ教訓とともに、1度目の件から振り返ってみたいと思います。
1度目:学校との連携が不十分だった
1度目は、まさかの「集団下校中」の行方不明案件でした。
集団下校というということで、わたしは「待ち合わせ場所まで先生が送り届けてくれる」と思い込んでいました。
しかし、実際は親との待ち合わせ場所よりもはるか前で、先生は学校に引き返していました。
わたしはそんなことも知らず、のん気に待ち合わせ場所で待っていた。
そうしたら、子どもが帰ってこなかった。
このとき、わたしは「待ち合わせ場所まで先生も来てくれる」と完全に思い込んでいたので、事前に先生がどこまで来てくださるかを確認しませんでした。
そして、学校側としては「集団下校は、毎回待ち合わせ場所まで行くわけではありませんよ」というスタンスでした。
これはどちらが悪いというのではなく、学校は当然のように「待ち合わせ場所までは送らない」と、わたしは当然のように「待ち合わせ場所まで来てくれる」と認識していたことが原因だったと思います。

これは学校や地域差があったり、それぞれが思う常識が違うと思うので、心配な方は学校に聞いてみてくださいね!
なにより申し訳なかったのは、学校とわたしの不十分な連携により迷子にさせてしまった息子・まめに対してでした。
ただでさえ新しい環境で多少なりともストレスがあるのに、下校中に迷子になるのは相当こたえただろうと思います。
2度目:GPSの選択を誤った
2度目は、はじめてできたお友達と一緒に下校中、寄り道をして行方不明になりました。
このとき行方不明になった根本的な原因は、まめがお友達と寄り道をしたことに他なりませんが、わたしがすぐに探し出すことができなかったのは、GPSの選択を誤ったことだったと思います。
このとき使っていたGPSは、学校から支給される「ツイタもん」でした。

このツイタもんは、学校の門をくぐると保護者に連絡が行くという位置情報システム。
そう…このツイタもんでは、子どもが「学校の門をくぐったかどうか」しかわからないのです!!!
しかし、よく考えてみればまめの心配要素は、学校の門を出たあと。

完全にツイタもんの管轄外だね(笑)
ツイタもんを持ち歩いていたので、安心して家で待機していたわたし。
しかしその日は、やけにツイタもんの通知が鳴っていました。
メールを見ると、
「まめさんが学校の正門を通過しました。」
という通知がやたらと来ているんです。
この時点でわたしは、

まめ、学校の門を出たり入ったりしているんだ…
と、嫌な予感がしました。
だって、何もなければ一度だけ正門をくぐって帰ってくるわけで、出たり入ったりしているということは、何か困っているか遊んでいるかのどちらかだからです。
そして、ツイタもんの通知が止まると「やっと門を出たか…そろそろ帰ってくるかな」と思い、待つこと数十分。
帰ってこない!!!!!
まずいと思い、学校に電話して帰宅していない旨を報告。
担任の先生が学校から飛び出してきて、一緒に探してくださった…という経緯でした。
2度目の騒動で、わたしは「わが家にはツイタもんではダメだ」と気がつき、即解約。
より正確に位置情報がわかるGPS【みてねみまもりGPS】を導入しました。

みてねみまもりGPSは安価なのに優秀で、妹・ナツのときも重宝しました!
3度目:ルールの徹底が不十分だった
3度目は、せっかく導入した【みてねみまもりGPS】をランドセルに入れたまま、ランドセルを放置して遊びに行ってしまい、そのまま行方不明になった件です。
ランドセルにGPSが入っていることで安心しきってしまい、まさかそのランドセルと身体が下校中に離ればなれになるとは思っていませんでした。
このとき、まめは小学校2年生。
通常であれば下校時のルールも認識している年齢かもしれません。
しかし、まめはADHDの特性で衝動的な行動をする子だったので、気をそらさず真っすぐ帰ることがなかなかできませんでした。

毎日迎えに行ければよかったんですが、ナツの幼稚園の送迎もあるし…さすがにわたし1人では無理でした…
まめはいつも途中で石を探したり、木の枝を拾ったり、気分転換をしながら帰ってきていました。
学校で頑張っている分、下校中にそれぐらいは良いだろうと目をつむっていましたが、本当はここで「帰り道の石も木の枝も禁止」し、まっすぐ帰るよう言うべきだったのかもしれません。
お友達と虫探しに夢中になり「あっちの方も探してみようぜ」となり、そのままランドセルを置いて、本格的に虫捕りを始めてしまった…という経緯でした。
そして、3度目の件では行方不明になっただけではなく、下水道の近くに子どもだけで行っていたことが発覚したため、担任の先生に報告しました。
子どもが行方不明になってわかったこと

まめによる、3回にもわたる行方不明騒動。
1回目から都度対策をとり、同じことが起きないよう備えてきたつもりですが、それをゆうに超えてくるのが子ども。
特にまめは発達特性があり、こちらが説明しても全然理解していなかったり、忘れてしまったりすることがあります。
そして、全然別の要因から2度目、3度目が起こってしまいました。
小4になった今はGPSも持っておらず、学校が終われば帰ってきて、宿題をやってから遊びに行くように。
特に3度目の、GPSを置いて勝手に虫捕りに行ったときの件が大きく影響したのか、同じことはしなくなりました。
まめの行方不明騒動を経てわたしが学習したのは、以下のことです。
まず、学校側に発達特性があることを伝えるだけでなく、今回の件でいえば
道がまだわからないので必ず親が待つ場所まで送ってほしい。それが無理なら学校に迎えに行かせてほしい
などと、学校に事前相談すべきだったということ。

まめの発達障害に関しては、療育から小学校に引き継ぎが行われているはずだったので、油断していました…
そして、親と学校が連携していたとしても、子どもは予想外の行動に出ます。
そのため、子どもの突拍子もない行動に対し、いかに備えられるかというところが大事だと感じました。
今回の件を経験し、わが家では以下の対策を取りました。
- ランドセルに「緊急連絡先カード」を入れる
- キッズフォンを持たせる
- 「家に帰るまで遊ばない」というたった1つを約束させる
- もし迷子になったら、必ずコンビニやファミレスに入って店員さんに緊急連絡先カードを渡すよう伝える
- ↑このとき入るコンビニやファミレスには、日ごろから何度も足を運んで慣れさせておく

本当は公衆電話の使い方を教えることも検討しましたが、いざというときに使い方を覚えているとも限らないし、発達障害児には向かないと判断しました
結果、上記③「家に帰るまで遊ばない」という約束を守ってくれたことで、それ以降はなにごともなく平和になりました。
まとめ
以上が、わが家に起こった小学生の行方不明騒動です。
発達障害をもった子どもは、下校中の判断において独自の困難があります。
何かが起きたら即教訓を得て、次回に活かすことが、1つずつトラブルを潰していける方法です。
親御さんは24時間見守れるわけではないので、時には想定外のハプニングが起こるかもしれません。
ある程度は仕方ないにしても、なるべくそうならないよう、あらゆる手段で「備え」を用意しておきましょう。
よく読まれている記事






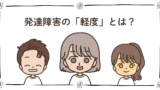
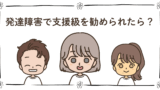

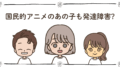


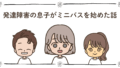
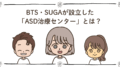
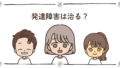
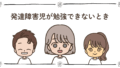
コメント