
こんにちは、はちみつ大好き「はち」です。
息子・まめが通っている小学校から「転校してください」と遠回しに言われたときのお話です。
発達障害や知的障害を持ったお子さんを育てていると、通常学級か支援学級か迷ったり、学校でトラブルがあったりして、頭を抱える親御さんがいるかもしれません。
発達障害や知的障害が原因となった、唐突な転校というエピソードについてシェアしたいと思います。
当時の正直な気持ちを思い出しながら、心の中を整理するつもりで書いてみました。

転校に至った経緯

わが家が転校に至った経緯を簡潔に説明すると、
通常学級で適切な教育を受け続けるのが難しく、支援学級に転籍することになったから
という理由です。
発達障害や知的障害が発覚したタイミングで小学校4年生に上がり、勉強の難易度や本人の学習態度を総合的にみて、支援学級への転籍が最適であるという結論に至りました。
以下にて、細かく経緯を振り返ってみたいと思います。
小学校3年生で知的障害が発覚する
当ブログを読んでくださっている方はご存知だと思いますが、わが家には発達障害の息子・まめがいます。
まめは小学校3年生のとき、WISCという発達検査を受け、知的障害が発覚しました。
\ WISCを受けたときのお話はこちら /
そもそもWISCを受けようと思ったのは、わたしの直感がきっかけでした。
幼児期から発達障害の傾向はあったものの、知的レベルではなかったまめ。
しかし、小学校に入学し低学年、中学年と上がっていくうちに
もしかして知的障害なのかな…?
と感じるようになりました。
そして検査を受けたところ、主に学習面での知的レベルが目立つという結果に。
心理士の先生とまめが1対1で面談を行いましたが、先生は
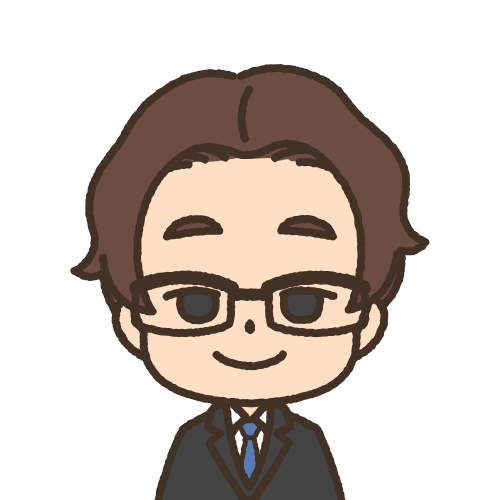
会話がのんびりで考える時間が長いという特徴はあるけれど、コミュニケーションに問題はありません。
こちらの質問の意図も理解しているし、終始落ち着いて面談できました。
というフィードバックをくださいました。
結果としては【コミュニケーションは知的レベルではないけれど、学習面では綿密なフォローが必要】というものでした。
この頃から「知的障害が発覚したからには、支援学級への転籍も視野に入れなくては」と考えるようになります。
しかし、問題点は
まめが現在通っている学校に支援学級が設置されていないこと
でした。
支援学級に転籍するには、イコール転校という道しかなくなってしまったのです。

でも今思えば、この段階で少しずつ心の準備をしていて良かったと思いました
近隣の小学校に支援学級が設置される
あいにく、まめが在籍している小学校には支援学級がありません。
そのため、支援学級に転籍するには転校が伴うことになってしまいます。
そんな中、とてもラッキーなことに、徒歩15分ほどで通える小学校に支援学級が設置されたのです!

わたしたちの住んでいる地域は子どもが多く、500m~1km圏内に小学校が密集している街。
越境すれば、学校の選択肢が常に2~3校はあるというありがたい住環境なんです
まめは、住んでいるマンションの学区内にある公立小学校に入学しました。
しかし、マンションの逆側に15分ほど歩くと、また別の小学校があるんです。
そこに支援学級が設置されたということで、転籍(転校)を視野に入れていたわたしは「助かった~!」という気持ちでいっぱいでした。

そうでなければ、バスを使って遠方の小学校に通わなければならなかったので…
支援学級といっても「知的」「情緒」「難聴」など目的が異なるので、子どもに適した学級を選ぶ必要があります。
わが家は知的障害児を対象とした支援学級を希望しており、その近隣の小学校に設置されたのも知的学級だったので、本当にラッキーでした。
この時点で、わが家にとって支援学級への転籍(転校)のハードルがグッと下がりました。
通常学級 + 放デイで様子を見る
いつでも支援学級に転籍できる準備はできていたものの、肝心なのは子どもの意思。
まめは今の小学校(通常学級)を楽しんでいて、学校が大好きだったので、転校は避けたかったというのも正直な気持ちでした。
発達外来の先生と面談した際にも
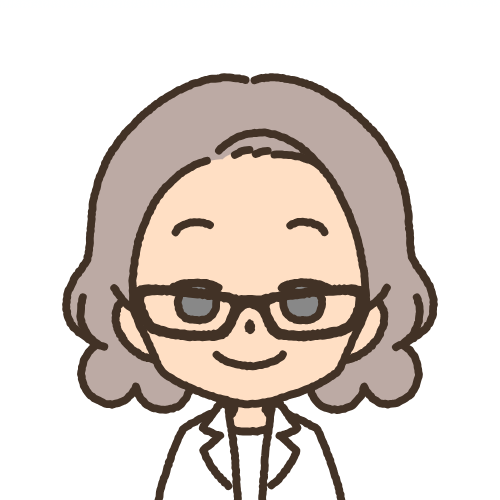
本人が今の学校を楽しんでいるならば、転校は最終手段にしましょう
という結論に落ち着いていたため、すぐには転籍する予定もありませんでした。
まずは療育の受給者証を取得し、放課後等デイサービスに通うことから始めました。
\ 受給者証についてはこちらを /
通常学級で学習を続けながら、フォローすべき部分を放課後等デイサービスで学んでもらうという形で、小学校4年生がスタート。
わたしは、まめが学校を楽しんでいることで満足していましたが、蓋を開けてみると学習面で心配ごとが膨らんでいたようでした。
学校から支援学級への転校を打診される
小学校4年生がスタートし担任の先生と面談をすると、やはり学習面での懸念事項が多いという話をされました。
しかし、わたしの中では学習面よりも友達とのコミュニケーションのほうが心配だったんです。

正直勉強は二の次で、友達に不快な思いをさせていないかとか、コミュニケーションがとれているかとか、対人関係の心配ごとのほうが大きかったんです
しかし、そんなわたしの思いとは裏腹に、学校の先生がもっとも懸念されていたのは学習面でした。
担任の先生との面談で「引き続き支援学級への転籍は考えているが、最終手段にするつもりでいる」という話をしました。
しかし、その面談の直後に校長先生から呼び出されてしまいます。

校長先生から直々の呼び出しなら、まぁ…そういうことだろうな…とは思いましたけどね…笑
そして、校長先生から言われた話は、想像以上にショッキングなものでした。(以下、閲覧注意)
学校の様子は授業参観のときぐらいしか見たことがありませんでしたし、ここまで言われるほと酷いとは思っていませんでした。
「義務教育が機能しない」とまで言われてしまっては、転校の選択肢を排除する理由はもうありません。
まめはしばらく転校を渋っていましたが、話し合いを重ねようやく決まりました。
「転校してください」と言われたときの正直な気持ち

学校から転校を打診されたときは、正直「あ、そうですか…」というため息まじりの気持ちでした。
顔文字にすると、こんな感じです。→(´-ω-`)
選択肢の1つとして提示していたものなので、そこまで驚くことはありませんでしたが、一応「最終手段にしよう」という方向でいたので、ちょっと急だったというか…
当時の思いを吐き出してみたいと思います。
学校から追い出されたような気持ち
転校を打診されたときは、なんだか学校から追い出されたような気持ちになりました。
「追い出された」というとかなり語弊があるのですが、感覚的には「出て行ってください」といわれているような、リアル窓際のトットちゃん状態のような…

転籍にともない転校も余儀なくされたのは、単純に今の学校に支援学級が設置されていないからです。
もし今の学校に支援学級があれば、クラスだけ変えて解決したことでしょう。
しかし、それができないので「転籍(転校)してください」という結果になりました。
転校は隣の学校なので物理的な負担も少なく、恵まれた環境変化だとは思いましたが、やはり「学校ごと変える」という現実を突きつけられると、
まめはこの学校にいてはいけない生徒なんだなぁ
なんていう気持ちが押し寄せてきて、なんだかブルーな気持ちになったものでした。
しかし、切り替えの早さが強みであるわたしにとってこの気持ちは一時的なもので、面談からの帰り道には手続きの段取りなどを調べていました(笑)

いろいろ思うことはありましたが、悩んでたって何も始まりませんからね
こちらの意見が無視された気持ち
学校から転校を打診されたときは、わたしやまめの気持ちをすべて無視されたような気持ちになりました。
というのも、発達外来の先生と支援学級の話をした際、
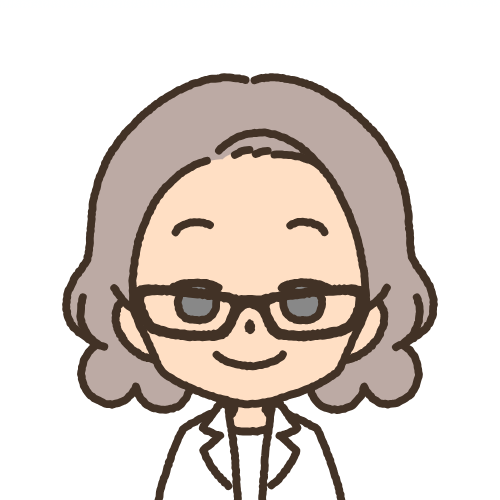
支援学級への転籍を学校から強要されることはありません。最終的に決めるのは保護者です
といわれていたからです。
「最終的な決定権は保護者にある」という安心感から、こんなにも急に転校が決まるとは思っていませんでした。
先生と転校について相談を重ね、少しずつ現実的になっていき…という段階を踏むものだと思っていました。
そのため「転校は最終手段として考えている」と伝えた直後に「今すぐに転校してください」といわれ、そのまま話が進んでいくことは少し想定外だったんです。
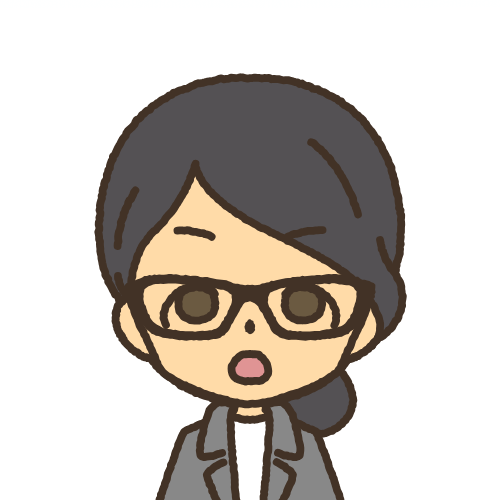
支援学級への転籍についてはどうお考えですか?
と聞かれ、

選択肢には入れていましたが、息子本人が今の学校にいたいという思いがあるので、すぐには難しいと思っています。小児科の先生にも「無理やり転校させて学校に行かなくなってしまうリスクもある」とお話がありました
と、今の気持ちや意向を伝えたのですが、こちらサイドが「選択肢に入れている」と言ったためか、先生はその後まくし立てるように転校の話を進めました。
最後のほうなんて、もはや学校が言う「いじめはありません」的な決めつけのように思えて、なんだか素直に話を聞く気をなくしてしまいました。

支援学級に移って生き生きしている子をたくさん知っている、という話も「いやそれはうちの子の話じゃないから全然関係ないのでは…」と思いながら聞いていました
冒頭で「顔文字にすると、こんな感じです。→(´-ω-`)」と言ったのは、このためです。笑
最終的には学校に押されるような形で、転校の話が決まっていきました。
客観的に見れば学校側の意見が正しいのはよくわかりますし、うちの子が通常学級に適さないから支援学級に移るだけのこと。
それでも、やり方が強引だった点は、発達障害児を育てる親からすればデリケートな問題です。
わたしは屈強メンタルなので、ガビーン!!!(死語)ときてもすぐに切り替えられましたが、このようなやり方では泣いてしまう親御さんも多いはず、と思いました。
最終的には「ベストな選択」と理解
学校から転校を打診された件について、思うところはたくさんあります。
しかし、最終的にはまめにとってベストな選択だと理解することができました。
支援学級への転籍は、わが家の場合転校を伴うもの。
そのため、2歳差の兄妹が別々の小学校に通うことになり、シングルマザーであるわたしの負担も大きくなります。
両学校は基本的に運動会などの行事が同日に行われるので「来年からどうしよう」という思いもあります。

しかし、それは命や将来にかかわることではないので、いったん置いておこうと思いました
今しなければいけないのは、まめの学習環境や学校生活を整えること。
まめが義務教育にふさわしい学びを受けられて、好きなことができて、楽しく充実した毎日を送れること。
そのためには、支援学級への転籍はマストだったのかもしれません。
学校のやり方には不信感を感じたものの、新たな道へ進む背中を押されたと思えば、ポジティブに考えることができます。
今できること、未来を見据えてベストだと思えることを、着々とやっていくだけです。
通常学級から支援学級への転籍について

通常学級から支援学級への転籍は、発達障害児を育てる親御さんにとって気になるポイントだと思います。
乳幼児のときに発達障害や知的障害の診断が下りていなくても、小学校入学後に「おや?」と思い始めるケースもあります。
わが家のように最初は通常学級に入れて、様子を見ながら支援学級への在籍を検討するご家庭も少なくないでしょう。
そこで、通常学級から支援学級への転籍についての流れや仕組みをご紹介します。
必ず「転校」が伴う?
支援学級への転籍は、必ず転校が伴うわけではありません。
転校する必要のあるケースは、通っている小学校に支援学級が設置されていない場合です。
支援学級はすべての学校にあるわけではないため、その子の特性やニーズに合った学級が設置されている学校に転校しなければならないケースも存在します。
支援学級とひとくちにいっても、以下のようにさまざまな種類が存在します。
そのため、通っている学校にある学級が子どもに適したものでない場合、転校の必要が出てくるでしょう。

まめの通う小学校には、難聴の支援学級があります。
でもまめは難聴ではないので、同じ「支援学級」でもここではお世話になれないのです…
もし未就学児のうちから「いずれ支援学級に行くかもしれない」と考えている場合には、最初から支援学級のある学校へ入学するのも1つの手段です。
学区をまたいでいれば越境が可能な自治体もありますし、お目当ての学校がある学区に引っ越すのも良いですね。
もし支援学級のある学校に最初から通わせるのが難しければ、せめて通いやすい距離に引っ越しておくのもおすすめです。

学校に通い出してから、徒歩では通えない学校の支援学級に移ることになってしまうと、いろいろと手間がかかるので…

下の子も入学しちゃってたら、もう引っ越しも難しいかもしれないしね…
少しでも支援学級に行く可能性があるならば、通える範囲内に支援学級があるかどうかもチェックしておきましょう。
学校からの強制力はある?
支援学級のために近隣に引っ越したり、未就学児のうちから支援学級を調べておくというと
そこまでしなくても良いのでは?
もし支援学級に通えない距離だったら、そのまま通常学級に在籍していればいいよね?
と思う人もいるかもしれません。
表向きはそうなのですが、実際にはそうもいかないんです。
それはわたしが経験済みで、学校から半強制的に転校をすすめられることがあるからです。
本来、転校を伴う支援学級への転籍は、保護者側が最終的に決断するものです。
学校や小児科などの専門機関と保護者が相談することはできますが、最終的な決定権は保護者にあります。
しかし、わが家の場合はやや学校の強制力がはたらいたように感じました。
学校から半強制的に…というより、そこまでして支援学級に転籍したほうがいい(しなければならない)状態だったのだと思います。

確かにちょっとやり方は強引でした。
でもまめのために提案してくれたことだと、今は感謝しています
わが家のように、先生が危機感を感じて「この学校では義務教育を全うできない」と判断した場合には、学校からの強制力があるケースも存在すると頭に入れておいていただければと思います。
支援学級に転籍するメリット・デメリット
支援学級に転籍するメリットとデメリットを見てみましょう。
メリット
まず、支援学級に転籍するメリットは、その子に合ったペースで学びが提供されることです。
通常学級にいて苦痛に感じていたり、勉強についていけず手持ち無沙汰になっていたりした子が、支援学級に転籍すると、特に気持ちが楽になるのではないかと思います。
わが家の場合、まめが究極のマイペースだったがために、まめは「授業が理解できない」ことにまったく違和感を感じていませんでした。
それどころか「勉強めんどくさい」「眠いな~」ぐらいに考えていたと思います。
そのため、わたしはまめの学校の様子に気付くことができませんでした。

もし本人が学校に行き渋ったりすれば「もしかして勉強についていけなくてつらいのかな…」と勘繰ったと思いますが、毎日めちゃくちゃ楽しそうに登校していたので…(笑)
しかし、実際にまめは「義務教育が成立しない」と言われてしまうほど、学習が進んでいませんでした。
そのため、支援学級に転籍しまめに合った学びが提供されることは、メリットでしかないと感じています。
これから中学校や高校と進んでいくにあたり、小学生のうちから支援学級で丁寧に学んでおくことで、つまずきを早めにクリアすることができるでしょう。

中学生や高校生になってから「小学校の内容がわからない…」となるより、小学生のうちから少しずつギャップを埋めていければ、のちのち楽かなと思います
まめの支援学級転籍を提案してくださった校長先生は、このような経験があったそうです。
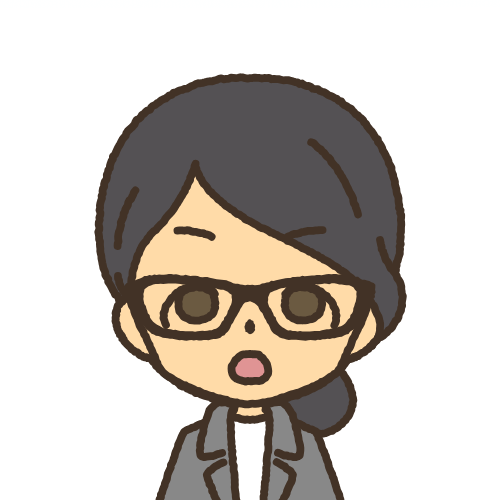
小学校までは通常学級にいて、中学から支援学級に変える生徒が一定数いました。
でも、それでは遅すぎるんです。
「なぜ小学生のうちから適切な支援に繋げなかったのだろう」と思う生徒をたくさん見てきました。
校長先生いわく、中学生になると就労を考えて進学先を検討することになるため、義務教育で習う内容をしっかり定着させ、高校へ送り出す必要があるそう。
そのため、小学校6年間を無駄に過ごし、中学生から支援学級でのんびり追いつくという考えは、うちの校長先生としては賛成できないとのことでした。
このお話を伺って、やはりまめが支援学級に転籍するのはメリットが大きいなと感じました。
デメリット
支援学級に転籍するにあたり、総合的にはデメリットが少ないと感じています。
しかし、ベストな選択とは言い切れない理由も。
それは、以下のような点です。
まず、支援学級に入ると小学校6年間の単元は終わりません。
支援学級では、子どもの理解度やペースに合わせて学習内容を進めます。
そのため通常学級よりも学習速度がゆっくりになり、小学校6年間で教科書の全単元を終えられないことも。
小学校で支援学級に在籍していると、中学校進学後も必然的に支援学級に進むことが望ましくなるでしょう。

学区内の中学校だけでなく、通える範囲に支援学級のある中学校があるかどうかもチェックする必要があります
支援学級に入った場合、よほど学習ペースが速くない限りは、通常学級の学習に追いつくのは難しいと考えておきましょう。
そして、子どもの発達障害や知的障害の程度によっては、自分がまわりと違う学級に在籍していることに気が付くケースもあります。
周囲の視線や発言を気にしたり、高学年になるほど友達との違いや他者の反応に敏感になり、自己肯定感や人間関係に影響するかもしれません。
支援学級に転籍する場合には、子どものメンタルケアも大切にしたいですね。
通常学級に在籍し続けるメリット・デメリット
それでは、支援学級に転籍せず通常学級に在籍し続けることのメリットとデメリットを見てみましょう。
メリット
通常学級に在籍するメリットは、同年代の学習進度を維持できることです。
通常学級では全国共通のカリキュラムに沿って授業が進むため、学習内容の遅れが生じにくいでしょう。
中学や高校への進学時に必要な学力を、確保しやすいのがメリットです。
また、支援学級に転籍しないことで、それまでのクラスメイトとの友人関係を維持しやすいでしょう。
また、子どもによっては「支援学級=特別扱い」と感じることが、ストレスになることも。
通常学級でクラスメイトと同じ環境下に置かれることで、心理的負担を減らせることも期待できます。
デメリット
通常学級に在籍するデメリットは、授業についていけない可能性があることです。
通常学級は、先生1人が30人近くの生徒を教えるので、個別サポートは受けられないことがあります。

学習の遅れや理解不足があっても、1人ひとりをフォローする余裕は、通常学級にはないんです…
授業内容がわからない場合、子ども本人もその場にいるのがつらくなったり、先生やほかの生徒にも負担がかかったりすることがあります。

学習の遅れだけでなく、人間関係にも影響が出る可能性があるんだね
このような二次的課題が出ると、自己肯定感の低下や不登校などにつながるおそれもあります。
通常学級か支援学級かという判断基準ではなく、子どもに合った学級を選ぶことが大切ですね。
小学校入学時どちらに入るべき?
現在子どもが未就学児のご家庭では、小学校に入学する際に「通常学級か支援学級のどちらに入れるか」迷っているかもしれません。
小学校入学前に、以下のポイントをふまえて入学先を決めると良いでしょう。
学習面でのつまずきやすさ
入学前に、文字や数の理解、集中力が持続するかどうか、指示の理解がスムーズかどうかを確認します。
授業についていくための基礎力がまだ不十分な場合、支援学級の方が無理なく学べることがあります。
幼稚園の場合、年長クラスで小学校準備のために読み書きを教えてくれたり、小学校の生活をイメージした活動が行われることがあります。
通常学級か支援学級か迷ったら、年長クラスでの活動のようすを先生から聞くようにしましょう。

あらかじめ先生に通常学級か支援学級か迷っていることを伝えておくと、面談などでフィードバックをくれるかもしれません
集団生活への適応力
友達とのやりとりやルールの理解、トラブルへの対処など、集団での振る舞いが安定しているかを見ておきましょう。
環境の変化に不安が強い子や、刺激に敏感な子は支援学級の方が落ち着いて過ごせる場合があります。
小学生になると、幼児期のコミュニケーションよりも抽象的で、空気や表情を察知して会話することが求められるようになります。
幼児同士のコミュニケーションでは問題なくても、小学生になって友達関係が苦手になってくるケースがあります
支援の必要度
学習や生活をする中で「常時」支援が必要なのか「一部の時間」だけなのかで、選択肢が変わります。
支援が一部の時間だけでよい場合、通常学級と合理的配慮を組み合わせて過ごせる可能性があります。
もしくは、通常学級+通級(週に数時間など)を組み合わせるという選択肢もありますよ。
もちろん、就学前は通常学級で良いと判断しても、小学校入学後に支援が必要になる可能性もあります。
通常学級から支援学級に移籍できるように、はじめから支援学級のある小学校に入学しておくのも手ですね。

お住まいの学区内で、支援学級が設置されている学校をチェックしておきましょう!
本人と保護者の希望
子ども自身がどう感じているか、保護者が何を重視するかは、大事な判断材料になります。
学力維持や環境の安定、友人関係などを総合的に見て、最終的には親子で話し合ってみましょう。
未就学児にとって、小学校の通常学級と支援学級の違いは明確にはわからないと思います。
そのため、子ども本人の希望というよりは、子どものことを一番よくわかっている保護者が判断するのが良いでしょう。
ただ、幼稚園や保育園の先生、療育の先生たちが「支援学級のほうが良い」と判断すれば、その意見も参考にしてみてください。

わたしの経験上ですが、やっぱり教育や発達の専門知識を持った人の意見は積極的に取り入れたほうが良いと思います
迷ったときの相談窓口
通常学級か支援学級かで迷ったら、以下の相談窓口に行ってみることもおすすめします。
| 市区町村の教育委員会 (特別支援教育課など) | 就学相談会や教育相談室で、 支援学級や通常学級の適性を アドバイスします。 |
| 小学校の校長 特別支援コーディネーター | 学校見学や事前面談で、 具体的な支援体制やクラスの雰囲気を 知ることができます。 |
| 児童発達支援センター 療育施設 | 専門職(心理士・言語聴覚士など)が 就学後の見通しを含めてアドバイスします。 |
| 医療機関 (発達外来・小児科) | 診断や発達検査結果をもとに、 学校での配慮の必要性を助言します。 |
わが家のように、小学校入学後に「支援学級に行った方がいい」と提案されたのであれば、選択肢はだいぶ狭まってきますが、就学前だと迷ってしまいますよね。
子どもはこれから成長するかもしれないし、周囲に追いつくかもしれないし…
親御さんだけで決めかねるときには、専門スタッフのいる窓口に相談してみましょう。
まとめ
わが家が、通常学級から支援学級にのある小学校に「転校してください」と言われたときのお話でした。
もともと支援学級への転校を視野に入れていたわが家でしたが、現実になるのはまだ先だろうと思っていました。
しかし小学校高学年になり、本格的に学習サポートをしたほうが良いという結論に至りました。
転校には少なからず負担やストレスが伴うので、最初は抵抗感のある選択でしたが、ポジティブに考えられるようになったところで、記事化を決めました。
転校後の生活については、また別記事にまとめてみたいと思います。
通常学級か支援学級か迷われているご家庭、そしてわが家のように、学校から転籍・転校を提案されたご家庭にとって、なにか参考になる情報であれば良いなと思います。


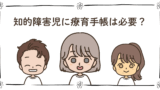


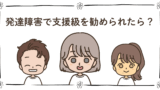
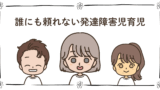


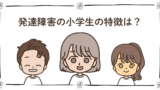
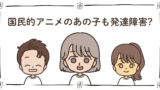
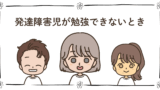
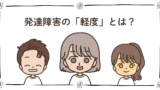


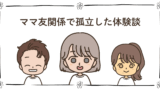
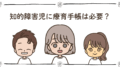
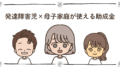
コメント