この記事では、発達障害の種類を一覧で分かりやすく解説します。
発達障害とひとくちで言っても、大きく分けると3種類の障害があります。
そのすべてでまったく違う性格傾向があり、困りごとや悩みもそれぞれ異なります。
お子さまの発達障害やその可能性でお悩みの方向けに、それぞれの発達障害について詳しく解説しましょう。

発達障害の種類を一覧で解説

それでは、発達障害の種類を一覧で解説します。
発達障害にはさまざまな種類がありますが、大きく分けると以下の3つです。
| ASD (自閉スペクトラム症) | ADHD (注意欠如多動症) | LD (学習障害) | |
| 特性 | 人に興味を持たない 特定の行動や習慣にこだわる 言葉の遅れがある | 落ち着きがない 衝動的に行動する 授業中に立ち歩く | 読み書きが極端に苦手 文字を書くと鏡文字になる 文章が理解できない |
| 困りごと | コミュニケーションが難しい 人の気持ちを察するのが難しい 環境の変化に弱い | 他害をしてしまう 一方的にしゃべってしまう じっとしていられない | 学習についていけない 暗記ができない 簡単な計算ができない |
| 発症する時期 | 3歳まで | 12歳まで | 就学後 |
| 知的な遅れ | 可能性あり | 可能性あり | なし |
発達障害の3種類はそれぞれ大きく違っていますが、この3つのうち複数の特性が出現することがあります。
また、LD(学習障害)を除いては、知的障害も併存することがあります。
「発達障害だからこう」と一概にはいえない、微妙な違いがたくさんあるんです。
次の項目から、それぞれを掘り下げて詳しく説明していきましょう。
発達障害の種類をくわしく解説

発達障害の種類を一覧でご紹介しました。
ここからは、それぞれの発達障害をくわしく解説していきましょう。
わが家のまめは、ASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如多動症)が混合で出現するタイプの発達障害です。
発達障害と知的障害は併存しやすいといわれており、わが家のまめも学習面で知的障害の診断が下りました。
程度によっては、療育や支援学級で適切なサポートを受けるのも良いでしょう。
成長にしたがって発達障害の特性が消えたり、また新たに出現したりすることもあります。

良くも悪くも先行きが見えにくい発達障害。
それぞれの特性を知って、就学後や将来の準備をコツコツ進めましょう!
それでは、発達障害の大きな3種類をくわしくご紹介します。
ASD(自閉スペクトラム症)

発達障害の種類1つ目は、ASD(自閉スペクトラム症)です。
ASDはかつて「自閉症」や「アスペルガー症候群」などと呼ばれていました。
そのため、診断された時期によっては上記の名前で憶えている人も多いかもしれません。

有名人だと、イチロー選手やイーロン・マスク氏もアスペルガー症候群を公表していますよね
現在はASD(自閉スペクトラム症)という名称に変わり、上記アスペルガー症候群など複数の障害が集約されました。
ASDの特性や性格は?
ASDの特性は、以下のものがあります。
ASDは、発達障害の中でも定型発達児(一般的な発達をしている子ども)とはかけ離れた行動や特性を見せるため、比較的周囲が気づきやすいといわれています。
上記に挙げた「ものの位置や習慣に強いこだわりがある」という点では、ミニカーを一定に並べて見つめるという行動がよくみられるようです。

ミニカーを並べたらASDだなんて、最初は「でまかせじゃないの?」と思っていたのですが、実際にミニカーやフィギュアを自分のこだわりの順序に並べて満足する、という特性があるそうです
子どものかんしゃくでお悩みの方、またかんしゃくが「発達障害と関係あるのでは?」と心配されている方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
ASDの困りごとは?
ASDの子どもにみられる困りごとは、主に社会性や対人関係です。
ASDは「社会性の障害」ともいわれ、周囲とのコミュニケーションや距離感の掴み方がわからず、トラブルに発展することがあります。
主な困りごとを挙げてみましょう。
自宅の場合、家族の理解が得られれば過ごしやすいですが、困りごとが発生しやすいのは園や学校などです。
お友達と思わぬトラブルに発展したり、運動会や発表会など普段と違う日にパニックを起こしたり、日常生活に支障があることも。

まめはASDの傾向がありますが、すべての特性が出現したわけではありませんでした。
お友達との適切なコミュニケーションは難しいことがありますが、運動会や発表会はルールに従って参加することができていました
わが家のように複数の発達障害が併存している子は、それぞれの発達障害の特性が少しずつ現れたり、消えたり、また新たに出現したりするかもしれません。
また、成長にしたがって特性が出たり消えたりすることもあります。
そのため、今現在みられる特徴が一生続くわけではありませんし、特性が消えるとも増えるとも言い切れないところが、発達障害の難しい部分ですね。
ASDの子どもへの接し方は?
ASDの子どもへの接し方のポイントは、以下の通りです。
ASDの子どもは、定型発達の子どもとは違う方法で理解したり納得したりするので、特性に合わせたかかわり方を心がけることが大切。
ASDの子がすべきなのは「みんなと同じ方法でできるようになる」ための特訓ではありません。
あくまでASDの子が無理をせず、何でも前向きに取り組めるような方法を採用しましょう。
ASDはいつ診断される?
ASDは、3歳までに発症するといわれています。
独特の表情や遊び方をみせるため、0~1歳という低年齢のうちに保育士さんや親御さんが気づくこともあれば、3歳児健診などで指摘されることもあるでしょう。
しかし、わが家のように3歳になっても診断されないケースがあるのも事実です。
まめはASDとADHDの混合型ですが、幼児期はASDの傾向が色濃く出ていました。
幼稚園児の頃、まめにみられていた特性は以下の通りです。
今振り返れば、一発で「ASDっぽいな」と分かる項目一覧みたいな当てはまり方…!
しかし、まめは1歳半検診でも3歳児健診でも指摘されることはありませんでした。
「発達に不安がある」とわたしから話を切り出したのに、です。
そして、4歳でK式発達検査を受けたときにも「発達障害とはいえない」という判定が出ました。

これだけ根拠が出揃っていて、親のわたしが「発達障害の可能性」と言い出していても、診断が下りませんでした
もちろん、専門家が「発達障害ではない」というのなら従うしかありませんし「発達障害でなければそれはそれでよかった」と思ったのも正直なところです。
でも、発達障害ではないからといって困りごとがなくなるわけではありません。
発達障害の傾向を持つ子どもを育てる親にとっては、診断がつく・つかないよりも、
今現在の困りごとを何とかしたい…
という切実な思いに翻弄されているのです。
ADHD(注意欠如多動症)
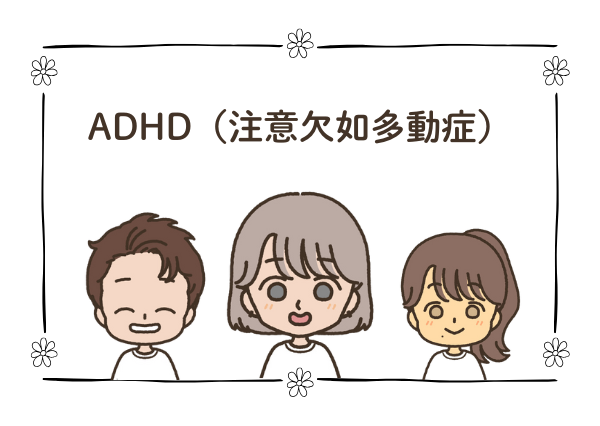
発達障害の種類2つ目は、ADHD(注意欠如多動症)です。
ADHDは、子どもから大人まで診断されることの多い発達障害で、最近では有名人もADHDを公表することが増えましたよね。
以前は「注意欠如多動症」ではなく、以下のように呼ばれていました。

かなりインパクトのある名称だったんだね
しかし「欠陥」という言葉が差別的であることが問題視され、現在の「注意欠如多動症」という名称に変わりました。
「破壊的行動障害」という響きが何とも過激ですよね。
現在ADHDは「行動障害ではない」とされていますが、程度によっては破壊的行動に出ることもあるため、注意深くかかわる必要があります。
まめはADHDも入っているので、過去には迷子騒動も起こしています。
ADHDの特性や性格は?
ADHDの特性は、以下のものがあります。
このように、ADHDの特性は一見、幼い子どもによくみられる傾向であることが多いんです。
そのため、幼児期ではADHDだと判断するのが難しいことがあります。
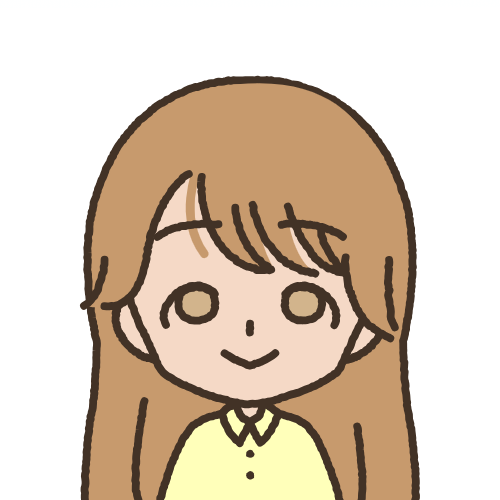
確かに子どもって衝動的に行動するし、危険を顧みない生き物っていうイメージがあるよね

2~3歳児に衝動性や多動性がみられてもまったく不思議ではないし、子どもらしくて元気だな~と思ってしまいますよね
大人のADHDも最近多くみられるようで、集中力のなさや「余計なことを言ってしまう」という性格も、ADHDに起因していることがあるそうですよ。
ADHDを公表する有名人も増えてきていますよね。
ADHDの困りごとは?
ADHDの困りごとは、主に衝動性や多動性などによる集団行動の困難さです。
幼児期のうちは「子どもらしく元気で良い」と言われるかもしれませんが、ADHDの困りごとは小学校に入学してから顕著化することがあります。
このように、学校生活が始まると「じっと座っている」「静かに先生の話を聞く」「まわりを見て適切な行動をする」ということが求められるようになります。
同時に、自分のことを自分でしなければいけなかったり、抽象的な指示や複数の指示を受けることも増えてきます。
たとえば、以下のようなものです。
教科書とノートを出して、これを書いたら教科書をしまって、ノートは出したままにしておいてください
それをいつものところにしまっておいてくれる?
次の授業が始まる前にトイレに行っておいてね
これらの指示の、どの部分がADHDにとって難しいのでしょうか?
1つずつ解説していきましょう。
教科書とノートを出して、これを書いたら教科書をしまって、ノートは出したままにしておいてください
▶ ココが分かりづらい!
- 複数の指示が1つの文章に詰め込まれている
- 「これ」が何を指しているのかわからない
- 「これ」を書くのが教科書なのかノートなのかわからない
- 教科書とノートのどちらを出してどちらをしまうのか混乱する
それをいつものところにしまっておいてくれる?
▶ ココが分かりづらい!
- 「それ」が何を指しているのかわからない
- 「いつものところ」がどこかわからない
- 「しまう」という動作が抽象的でわかりづらい(箱にポイッと入れるだけなのか、細かいケースに整理して入れるべきなのか)
次の授業が始まる前にトイレに行っておいてね
▶ ココが分かりづらい!
- 「次の授業が始まる前に」という時間の概念がわからない
- なぜ授業が始まる前にトイレに行くべきなのかわからない
- あと何分なのかわからない
- 遊んでいると次の授業が始まる時間になってしまう
ADHDの要素を持たない人にとっては「そんなの考えれば分かるのでは?」と思うかもしれません。
しかし、大人の方でも「細かく指示してもらわないと分からない」と共感できる方がいるのではないでしょうか?

確かに「アレをアレしといて」みたいに言う上司いるよね…

大人でもあまりにわかりづらい指示だと、日本語でも理解できないことがありますよね。ADHDの場合はその困り感が特に強く出るんです

そうなると、怒られる回数が増えて「学校が嫌だな」と感じてしまうこともあるかも…
ADHDの子は単に落ち着きがない、わがままな子だと思われることが多くあります。
周囲からの理解が得られず学校で怒られたり失敗したりする経験が積み重なり、どんどん自信をなくしていくことも。
次の項目で、ADHDの子に対する接し方のポイントを見てみましょう。
ADHDの子どもへの接し方は?
ADHDの子どもへの接し方のポイントは、以下の通りです。
ADHDを持つ子どもは、失敗体験や恥ずかしい思いを繰り返して自己肯定感が下がるか、思いきり褒められて自己肯定感が上がるかが分かれやすい発達障害です。
まめは、小学校に上がってからADHDの傾向が強くなったのですが、スクールカウンセラーの先生に
できないことには目を瞑る。できることは思いきり褒める。
というアドバイスをいただきました。
ADHDの子には目立つ特性がありますが、本人は周囲のお友達のことを気にしていたり、できないことを悔やんでいたりすることがあるそうです。
そのため、できないことを叱っているとどんどん自信のない子になってしまうのだとか。
ADHDを持つ子こそ、できることに着目して思いきり伸ばしてあげるよう助言されました。

ADHDの子は興味の差が激しいので、興味のあることを得意分野にしてあげるのも良いそうです!
ADHDはいつ診断される?
ADHDは12歳までに発症するといわれています。
早いと4歳ごろまでにその兆候に気付かれることもありますが、幼児期特有の「落ち着きのなさ」や「衝動性」と判別がつかないこともあり、診断しにくい発達障害です。
また、中学生くらいになるまで目立った特性が現れず、学業や学校生活に大きな影響を及ぼさないケースもあります。
子どもの頃はそうでもなくて、大人になり顕著化するケースもありますね。
学校や集団生活などの制約がある生活の中では、ADHDの特性が問題化する場面が出てくるでしょう。

まめも、制約のない家庭内ではそこまで困りごとはありませんでした。
しかし学校のルールに従うのが難しく、ADHDの傾向があることが発覚しました
また、ADHDは大人になってから診断される人も多くいます。
有名人でも、元タレントの木下優樹菜さんやコムドットのリーダー・やまとさんがADHDであることを公表していますね。

成人のADHDの症状は、不安症や気分障害などの精神障害と似ていて、判別がつきにくいのだそうです。
そのため、成人のADHDを診断するためには「子どもの頃の記録」が必要になることがあります。
参考:MSDマニュアル家庭版
LD(学習障害)

発達障害の種類3つ目は、LD(学習障害)です。
特定の学習において著しい困難や遅れが生じるのが特徴です。
LDは、発達障害の中で唯一「知的障害を伴わない」ことが診断の条件になっています。
LDの特性や性格は?
LDの特性は、以下のものがあります。
LDは、主に文字や計算など特定の学習において著しい遅れがみられる発達障害です。
目安としては、学校の学習に1~2学年程度の遅れがある状態をいうそうです。
LDの困りごとは?
LDの困りごとは、主に学校の授業や基礎的な学習が理解できない点です。
特に、LDは知的障害を伴わないにもかかわらず学習面での理解が追い付かず、劣等感を抱きやすいといわれています。
主な困りごとは、以下の通りです。
LDを公表している有名人はミッツマングローブさんがいますが、ミッツさんは「暗記ができない」という困りごとがあるそう。
そのため、芸能界で仕事をする今は自分で覚えやすいように台本をアレンジしたり、覚えられるよう落書きをしたりして、絵と音で頭に入れるようにしているそうですよ。
参考:週刊女性プライム
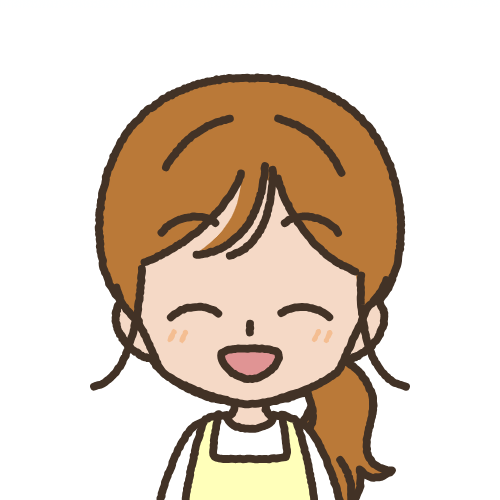
自分の特性を理解し、工夫を凝らしているのは素晴らしいですね!
LDの子どもへの接し方は?
LDの子どもへの接し方のポイントは、以下の通りです。
LDの子どもは、定型発達の子どもと同じ学習法では定着しないことがあります。
勉強不足だと判断してしまうと、どうしても大人は勉強を習わせたり学習量を増やしたりしてしまうかもしれません。
しかし、LDも発達障害の1つであり、脳機能の障害により特定の学習が理解できないのです。
LDの子ども、そしてその子に合った方法でゆっくりと学習を進めることがポイントです。

支援級でゆっくり学習するのも良いし、苦手分野が明確なら、その授業だけ通級(※1)を活用するのも◎
※1:通級…通常学級に在籍しながら、特定の授業のみ少人数教室や特別指導を受ける制度のこと
LDはいつ診断される?
LDは学習障害のため、学習が本格化する就学後に診断されることが多いとされています。
まれに就学前に兆候に気付かれることもありますが、就学前にはひらがなや計算などの学習が本格化していないことが多いため、小学校に上がってから発覚することが多いようです。
しかし、書いたり計算したりするために必要な基礎的な身体の動きや、ことばの遅れ、数を数える際の困難さがみられる場合、就学前に分かることもあります。
参考:LITALICOジュニア
わが家のまめも、LDが疑われたことがあったのですが、結局学習面で知的障害の診断が下りたので、LDではないことが明らかになりました。
※LDは知的障害を伴わないため
意外と知らない!コレも発達障害の仲間

発達障害の種類は、上記でご紹介した3種類です。
しかし、意外と知られていない「発達障害に近い」種類もあります。
発達障害の種類一覧には含まれないけれど、発達障害として分類されることのあるものをご紹介します。
軽度発達障害
軽度発達障害は、厳密にいうと「発達障害」の1つです。
名前の通り、発達障害のうち程度が軽度である人のことをいいます。
発達障害者かそうでないかといったら、発達障害者になりますが、軽度なので発達障害者とは認識されないこともあります。
また、軽度発達障害と発達障害の明確な違いは「知的障害を伴わないこと」という見方もされています。
しかし現在では「軽度」という言葉が誤解を招くおそれがあるとして「軽度発達障害」という呼称自体が使われなくなっているそうです(参考:厚生労働省)
発達障害のグレーゾーン
発達障害のグレーゾーンとは、発達障害の傾向がありながらも、診断基準を満たさない人のことをいいます。
軽度発達障害と似ていますが、明確な違いは、軽度発達障害が「発達障害」である一方、グレーゾーンは「発達障害ではない」という点です。

あくまで発達障害の傾向があるだけで、診断はされない状態をいいます
しかし、グレーゾーンの子どもにも発達障害の特性や困りごとがみられます。
ただ、調子が良いときと悪いときの差があるため、発達検査をした日にたまたま調子が良かったりすると、診断が下りないことがあるのです。
グレーゾーンも軽度発達障害のように「程度が軽い」「ほぼ健常児と同じ」と誤解されることがありますが、グレーゾーンにはグレーゾーンの壁があるのですね。
DCD(協調運動症)
DCD(協調運動症)は、運動スキルの獲得や使用が困難で、学校生活、遊びなどの日常生活や活動に弊害がある状態をいいます。
DCDの特性は以下の通りです。
DCDの特性は運動の練習不足ではなく、中枢神経系の機能障害によって起こるとされています。
DCDは、ASDやADHDと併存する可能性が高く、日常生活の行動に加えて運動面でも困りごとが増える要因に。
休み時間にお友達と外で遊ぶ気になれなかったり、体育の時間が嫌いになったりと、劣等感や疎外感を感じやすいのも特徴です。
参考:発達障害ナビポータル

まめはDCDの診断は下りていませんが、身体の動かし方を見ているとかなり傾向は強いと思います。でも、幸い身体を動かすことは好きで、現在はスポーツクラブにも所属しています!
チック症(トゥレット症候群)
チック症には「運動チック」と「音声チック」があり、その両方が1年以上続く場合「トゥレット症候群」と呼ばれます。
それぞれの症状は以下の通りです。
| 運動チック | 音声チック |
| まばたきする 口をゆがめる 唇をとがらせる 舌を突き出す 首を左右に振る 肩をすくめる 腕を振る・まわす 地団太する 跳び上がる 足をバタンとする | 咳払い 「あっ」「うっ」などの単純な音声 特定の言葉を繰り返す複雑な発声 汚言、卑猥な言葉 「あー」などの甲高い奇声 鼻をすする 叫び声 聞いた言葉を無意識に復唱する「反響言語」 |
チック症はADHDやLD、また精神障害である不安症や強迫症などと併存することがあります。
参考:MSDマニュアル
チック症は遺伝性が多いとされており、トゥレット症候群と診断されると「精神神経疾患」扱いとなります。
参考:難病情報センター
吃音症(どもり)
吃音症(どもり)は、話し始めのタイミングに障害が出る症状をいいます。
主に音を繰り返したりひき伸ばしたり、言葉が出てこず間があいてしまうなどがあります。
幼児期に発症することが多く、大半は自然に消失したり症状が軽くなったりするそうですが、まれに成人期まで続く人も。
多くは発症後3年で男の子の6割、女の子の8割が自然に治るともいわれています。
幼児期に、急激に言語が発達するため発症してしまうそうです。
参考:日本財団ジャーナル
吃音症の特性は以下の通りです。
| 吃音症の種類 | 話し方の特徴 |
| 連発(れんぱつ) | わ、わ、わ、わたしは… |
| 伸発(しんぱつ) | わーーーーーたしは… |
| 難発(なんぱつ) | ………………わたしは |
場面緘黙症(ばめんかんもく)
場面緘黙症は、特定の状況下で話せなくなってしまう症状をいいます。
具体的には、家ではおしゃべりができても学校では話せなくなってしまうなどという状態です。
場面緘黙症は数百人に1人の割合で発症し、多くは5歳以下で兆候がみられます。
男児よりも女児に若干多いとされ、不安障害を併発することもあるそう。
参考:済生会
また、ほかの発達障害をもともと持っている子どもの二次障害(※2)として、場面緘黙症を発症することもあります。
※2:二次障害…発達障害をもつ子どもが周囲からの理解を得られないことで、二次的な問題が起こってしまうこと
まとめ
発達障害の種類を一覧でご紹介しました。
発達障害は主に3種類に分けられますが、それ以外にもさまざまな症状が存在したり、また併発したりすることがあります。
このように多くの発達障害の種類や特性があると、もはや「普通の子」の定義とは何なのか、発達障害児を育てる親としては考えざるを得ません。
自分の子どもが発達障害を持っていても、傾向があっても、また身近な人がそうであっても、まずは「受け入れて配慮する」という意識が大切ですね。
よく読まれている記事
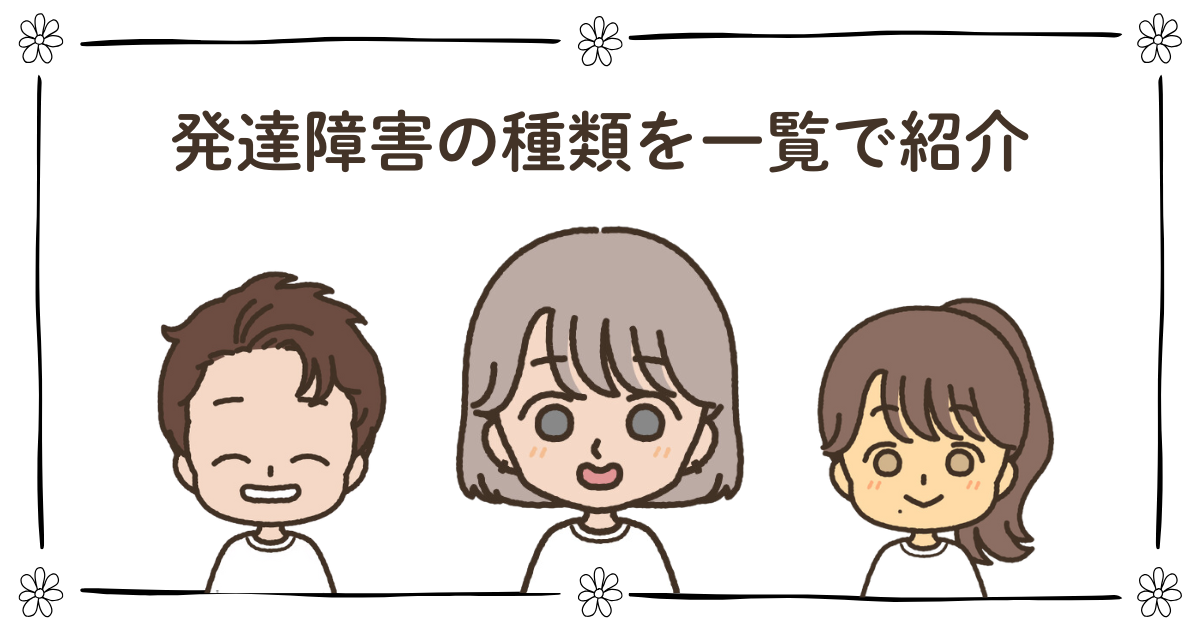

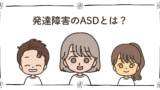


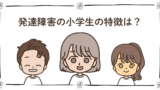
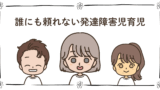
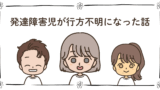

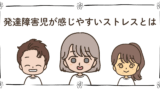
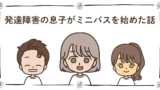
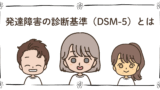
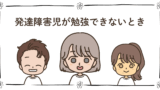
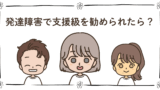
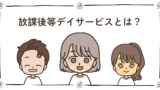
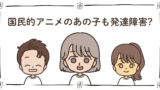
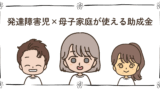
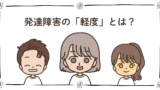

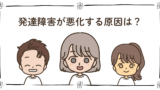
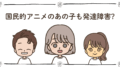


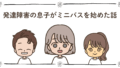
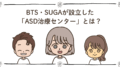
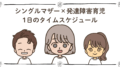

コメント