発達障害児を育てるご家庭では、習いごとをしていますか?
発達障害があると、習いごとも限られてしまうように感じますよね。
発達障害をもつわが家のまめは現在、プログラミングとバスケットボールを習っています。
(英語教育もしていますが、習いごとではないので今回は割愛しますね)
発達障害をもつ息子が突然
「バスケットボールをやりたい」
と言い出したあの日から現在までの、わが家の体験談をご紹介します。

発達障害児の習いごとはどうすべき?

発達障害児をもつご家庭では、
「習いごとはできるのかな?」
と心配されている親御さんがいるかもしれません。
発達の遅れによって、一般的な発達をしている子どもと同じ習いごとができるのか、不安になりますよね。
発達障害児の習いごとは、以下のポイントを意識して探すと良いとされています。
参考:ヨミドクター
わが家でも、上記の3点を重視して習いごとを決めています。
基本的には子どもが「やりたい」と言い出したものを、片っ端から試すようにしています。
それに加えて、わたしが「まめの将来に役立つのではないか」と思ったものも候補に入れています。

でも結局本人が興味を示さないと、毎回連れて行くのも大変だし、イヤイヤやっていて身につくのかも不安。
本人が興味を示したものを、全力で応援するという形に落ち着きました
ほかには、以下のポイントを意識してみても良いでしょう。
しかし、個人的に上記の条件はマストではないと感じます。
なぜなら、上記のポイントに合致する習いごととなると、選択肢が狭まるからです。
1人で集中できる環境や、発達障害に理解のある先生がいる習いごとは、まだまだ数が多くありません。
また、自由度が高い習いごとも魅力的ですが、ご家庭の方針によっては「社会生活に適応できるように」という考えもあるでしょう。
これらの条件を満たすのは、放課後等デイサービスや療育などの専門的な施設が該当すると思います。

習いごとを探す際に意識しても良いと思いますが、絶対条件ではないとわが家では考えます
本人の生きやすさを重視する
わが家で、発達障害をもつまめの習いごとを決める際には、本人の生きやすさを最優先して選んでいました。
以前、スクールカウンセラーの先生からこんなアドバイスをいただいたことがあります。

発達障害児に苦手を克服させようとしても逆効果で、親御さんもしんどくなる。
発達障害児はとにかく得意なことをひたすら続けて、伸ばしてあげると良い
それまで、まめにとって苦手なことを伸ばし、最低でも平均的なレベルまで引き上げてあげようと、いろんな習いごとを試してきました。
まめは字を書くのが苦手であまり上手ではないので、ペン習字をさせてみたり、文章読解力を上げるために公文に通わせたり…
これらはわたしの判断で始めたものなのですが、本人がしんどく感じてしまい、今はすべて辞めています。

結局、本人が嫌がれば足が遠のいてしまうし、無理やりやらせるこちらも気が重くなるしね…
周囲では「スイミングに行きたがらないけど無理やり連れて行く」というご家庭をよく見ました。(理由はわかりませんがスイミングが多かった記憶)
それでも、ものわかりの良い子や「行かなきゃ」ということが理解できる子は、親の意思で始めた習いごとでもある程度は続けられるものなんだな…と感心した記憶があります。
(もちろん賛否両論あると思いますが。)
というわけで、わが家では本人の生きやすさを重視した習いごとを、取捨選択するようになりました。
苦手の克服よりも得意を伸ばす
習いごとに限らず、わが家でまめの教育について考える際には、苦手を克服するよりも得意を伸ばすことを意識しています。
以前、療育の先生と教育について話していたとき、こんなお話になりました。
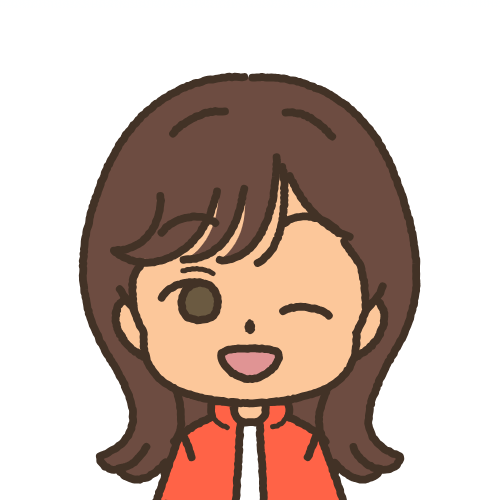
親としては「苦手なことを克服してほしい」と思うかもしれないけど、苦手を克服することが必ずしも明るい未来につながるとは限らないよね

苦手なことがあっても良いけれど、少しでも苦手意識が払拭されればいいなと思うんですが…
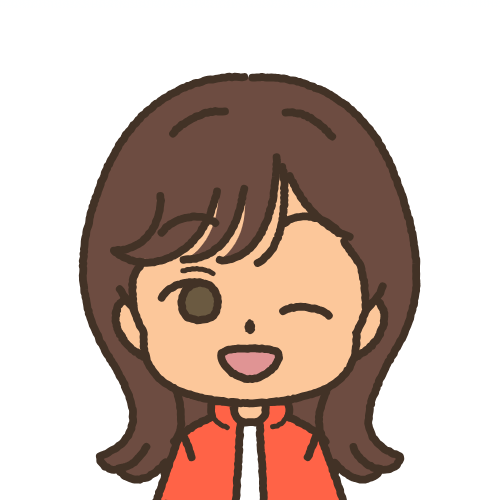
たとえば算数が苦手だとして、つらい思いをして頑張って平均値くらいまで伸びたとしよう。
結果、その子が算数大好きになる可能性ってどれくらいだろう

まぁ平均くらいまで伸びても、好きにはならないでしょうね
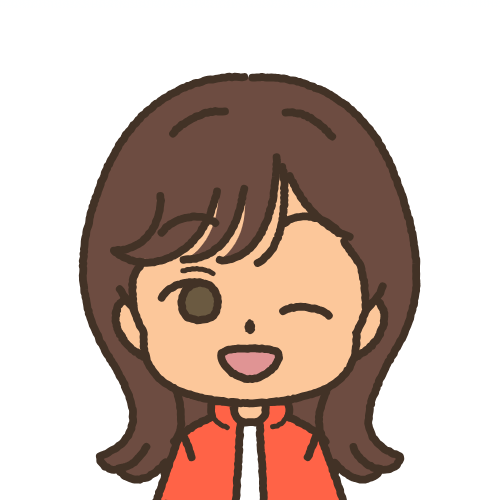
でさ、大人になってその子が「経理の仕事をしたい✨」ってなる可能性も、期待はできないよね…

苦手な算数をやっとこさ克服しただけなので、経理の仕事をしようとは思わないでしょうね(笑)
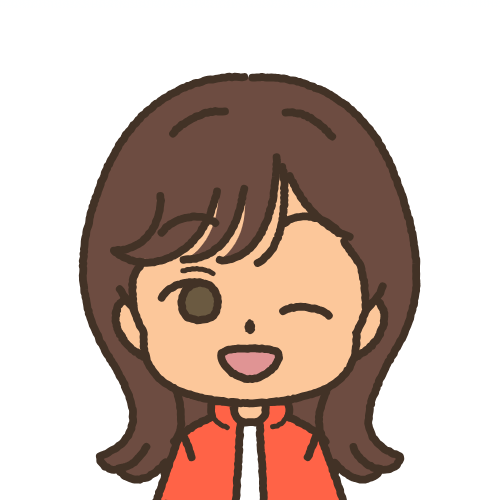
つまり、つらい思いをして克服しても、苦手は苦手なのよ。
苦手なことにお金を払ってくれる人はいないから、要は仕事にもならないわけよ

!!!
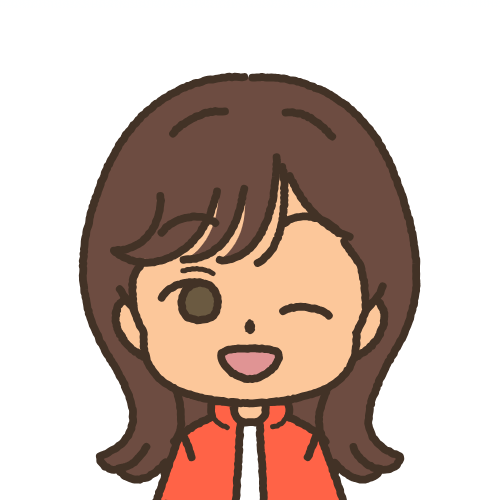
それならさ、苦手を頑張って克服する時間を、得意なことや好きなことに費やしてさらに伸ばしてあげれば、将来そっちでお金もらえるようになるかもしれないよね

確かに、将来のことを考えると「苦手を克服する」より「得意なことを伸ばす」ほうが未来は明るいかも…
苦手はある程度まで伸ばしてあげた方が良い、と考えていたわたしにとっては、目から鱗。
苦手を頑張って克服したところで、将来が大きく変わるわけではないかもしれない
ということに気付いたのです。
もちろん、苦手を頑張って克服したことで自信がついたり、逆にそれが得意になって選択肢が増えたりすることもあるでしょう。
でも、わが家のまめはどうだろうか?
と考えたとき、まめにはムチを打って苦手を克服させるやり方は合わないだろうと思いました。
この話に感銘を受けてからというもの、無理にペン習字で美文字にしなくても、国語ばかりさせないで工作や虫の図鑑を読む時間にしてもいいじゃないか!と思えるようになりました。
本音を言うと、公文の先生が厳しくても根気よく続けてほしかったし、できることなら字は綺麗な方が良いと思いました。

でも、それは親のエゴだとも頭の片隅でわかっていました
「子どものため」か「親のエゴ」か、自分を客観視しないとわからない部分なので、判断が難しいですよね。
特に発達障害があると、将来を過剰に心配してしまったり「何でも平均レベルにしてあげなきゃ」と考えたりしがち。
親御さんが子ども以上に高ぶってしまわないよう、ポイントを絞って冷静に、本当に子どもに合っている習いごとを決めたいですね。
向き不向きが顕著化しやすい
発達障害があると、習いごとに対する向き不向きが顕著化しやすい傾向にあります。
発達障害は、特性によって日常生活やコミュニケーション力に支障があったり、専門的な支援が必要だったりします。
そのため、一般的な発達の子ども向けにデザインされた習いごとだと、性格に合わない可能性があるでしょう。
たとえば塾でずっと座っていることができなかったり、ピアノやスポーツなど家での練習が必要でも、自主練に取り組むのが難しかったり…
発達の特性によって、続けやすい習いごとに出会えないケースもあります。
パステル総研の調査によると、発達障害児を育てる家庭では、以下のようなお悩みがあるそうです。
向いていると感じたものは積極的に続け、向いていないと思ったり本人が行きたがらなくなったりするものがあれば、以下の対応を取りながら様子を見ると良いでしょう。
それでは、発達障害児の習いごとにはどのような種類があるのか見てみましょう。
発達障害児の習いごとはどんなものがある?

発達障害児を育てるわが家の体験談を交えながら、発達障害児の習いごとについて解説していきたいと思います。
読売新聞が提供する健康系サイト「ヨミドクター」によると、発達障害児を育てる家庭で注目されている習いごとは、以下のものだそうです。

英会話や公文というお勉強系よりも、身体を動かすものや、いわゆる「非認知能力」を伸ばすものが多いね!
発達障害児は、DCDとよばれる発達性協調運動障害を併存している場合、運動が著しく苦手な傾向があります。
そのため、スポーツ系は選ばれない傾向にありますが、スイミングや体操など「身体の動かし方」を学べる習いごとが人気なようです。

発達障害があると、チームプレーや先の展開を読むことが苦手なため、サッカーやバスケットボールなどのスポーツからは遠ざかる傾向も感じられますね。
また、楽器やダンス・リトミック系は身体全体で音楽を楽しみ、ストレスを感じにくいとされ、発達障害をもつ子どもでも充実感を感じやすいそうです。

ただ、ピアノは楽譜を読みながら手と足を動かす上に、左右の手で違う動きが求められるため、苦手な子は苦痛に感じてしまうことも。

お試しレッスンなどで片っ端からやってみて、子どもが興味を示すものだけ続けてみても良いかもね
発達障害児の息子がミニバスを始めた話

わが家のまめは発達障害をもっています。
そんなまめが突然

バスケットボールやってみたいな~!
と言い出したのは、小学校3年生のときでした。
どうやらクラスにバスケットボールをやっているお友達がいるらしく、休み時間に一緒にバスケをして「上手でカッコいい!」と思ったそう。
正直、わたしの気持ちとしては
「今のまめにチームプレーのスポーツは難しいのではないか」
という思いがありました。
そして現在、まめは週5回のミニバス練習に欠かさず参加し、一生懸命がんばっています。
まめがバスケットボールに興味を持ち出してから、現在までの体験談を振り返ってみたいと思います。
突然スポーツに興味を持ち始める
もともとまめは、スポーツには一切興味を示さない子でした。
特に集団スポーツは、ASD(自閉スペクトラム症)をもつまめにとっては苦手分野でしたし、球技は「ボールにあたるのが怖い」という理由で近づきもしませんでした。
ドッジボールやサッカーで遊んでも、ボールのまわりには人が群がっているため、まめはいつも遠く離れたところにいました。

ボールや人に視線を向けていればまだマシな方で、幼児期はそのままスーッと抜けて行ってしまうことも…
そんなまめが「バスケットボールをやりたい」と言い出したときには、正直前向きな気持ちにはなれませんでした。
しかし、事あるごとにまめは「バスケやりたい」「バスケ上手になりたい」と言ってくるようになります。
もともと球技が怖いタイプだったのもあり、バスケットボールというのがどんな種目なのか体験させなければいけないと感じたわたしは、ミニバスの体験会に参加することに。

きっとまめはバスケを「ボールを投げてシュートを入れるだけの遊び」だと思っているのだろう、と感じたからです
そして、まめと妹のナツは、ミニバスの体験会に参加しました。

その結果…

バスケってすごく楽しい!もっと上手になりたい!

わたしはボールが飛んでくるのが嫌だったから、もう行きたくない
なんと、まめはバスケという種目を経験してもなお乗り気。
妹のナツはアクティブでバスケ向きかと思いましたが、お姉さんたちやコーチの勢いに圧倒されてしまったようでした。
同じ時期、別の「体育スクール」にも興味を持っていたまめとナツは、体育スクールの体験会にも参加していました。
その2つを経験し、それぞれに「どちらに入部したいか」聞いてみたところ、まめはミニバス、ナツは体育スクールという結果に。

わたしとしては、身体の動かし方を基礎から教えてくれる体育スクールのほうに気持ちが傾いていました
しかし、そんな親の願い通りにはならないのが子育て。笑
まめは

体育スクールもまぁ良かったけど、バスケのほうが楽しかった!!
と、その意思を曲げませんでした。
「可愛い子には旅をさせよ」
結局、わたしは「可愛い子には旅をさせよ」という思いを持って、まめとともにバスケットボールを頑張っていこうと決めました。
しかし、そこに辿り着くまでは多くの葛藤があったのも事実です。
わたしは最後まで、体育スクールのほうに気が変わってくれないだろうかと、体育スクールのメリットを熱く語りました(笑)
でも、まめの気持ちは固まっていたようで、
と、強い意思を見せました。
まめは、ここまで強い気持ちを持ったときには、自分の発言に責任をもって一生懸命頑張る子です。
なので、わたしは親として「お、これは本気だな」と感じました。
実を言うとわたしはバスケットボール経験者で、子どもがバスケットボールをやりたいと言ってくれることは大歓迎だったんです。

ただ、まめに合っているのか?まめにとって楽しい時間になるだろうか?と考えると、手放しで喜べないというのが正直なところでした
しかし、実際に体験会に参加したまめは「もっと上手になりたい」と思えるほど情熱を燃やしていました。
この瞬間、わたしの気持ちは「よし!バスケがんばろう!」という方向に切り替わりました。

まめの気持ちが前向きなうちにバスケの楽しさを知ってもらおうと、マイボールやバッシュなど一気に揃えました!笑

最初にグッズが揃うと「頑張るぞ~!」という気持ちが高まるよね
障害に縛られず好きなことをしよう
わたしは、発達障害がある子にスポーツは難しいと思っていました。
だってルールを理解するにも時間がかかるし、まめは運動機能障害の特性もみられたので、スポーツには不向きだと思ったから。
でも、それって全部わたしの「決めつけ」でした。
誰が発達障害だとスポーツができないと言った?
科学的根拠はある?
ただスポーツを楽しむだけじゃダメなの?
障害があると好きなことすらできないの?

生真面目な自分と共存する楽観的な自分が、グサグサと正論を刺してきました
どこか完璧主義で、人様に迷惑をかけないように…という意識があったわたしは、まめがバスケで「何らかの形で成功しなければならない」と思っていました。
プロになるとかではなく、
- 長く継続する
- 試合に出る
- 上達する
というようなことです。
でも、ミニバスに入ったからといって必ず続けなきゃいけないわけでも、試合に出なければいけないわけでも、また上達しなければいけないわけでもありません。
どうなるかわからないけど、とりあえず始めてみよう!
そんな気持ちで、まめとともにミニバスに入部させていただくことにしたのでした。
ミニバスを始めたその後について

さて、ミニバスに入部したまめですが、なんと毎日練習に励んでメキメキ上達しています。
もちろん、チームメンバーの中ではまだまだビギナーで、試合に出られるような実力はありません。
ルールもよく分かっていないですし、シュートフォームもドリブルもまだまだです。

でも、初めて体験会に参加したときには、ドリブルを2~3回ですらできなかったまめが、今ではボールとともにコートを走れるようになりました。
100本シュートという鬼メニューでは、なんと50回も入るようになりました。
ボールを持てない筋トレ系メニューにも、文句を言わずしっかり参加するようになりました。
誰がここまでの成長を期待したでしょうか?
もしかすると、1週間くらいで「もう行きたくない」と言い始めるかもしれないと思っていたわたしは、毎日一生懸命練習に励むまめを、とても誇らしく、頼もしく思いました。
上達するとか、試合に出るとか、そんなことよりも
スポーツを楽しんでいる
そんな姿をみられることが、何よりうれしかったです。

発達障害があり、苦手なことが多かったまめ。
わたしは苦手なことに果敢に挑戦するタイプの子どもではなかったので、まめも苦手が多くてつらい思いをたくさんしているだろうと思いました。
だから「バスケを始めても失敗体験を積んでしまうだけではないか」と思っていたんです。
でも、実際は全然違いました。
まめは、自分で決めた「バスケを頑張る」という情熱を燃やし続け、チームメイトに頑張ってついていきながら、ベストを尽くしています。
わたしの独断で「バスケはやめて体育スクールにしよう」と誘導しなくてよかった、本人の意思を尊重してよかった、と心から思ったのでした。
まとめ
発達障害をもつ子どもの習いごと、そしてわが家のまめがミニバスを始めたときのお話をご紹介しました。
発達障害を持っていると「一般的な習いごとができるのかどうか」心配になるかもしれません。
発達障害があると、周囲との協調性やコミュニケーション力に欠け、習いごとによっては相性が合わないことも。
もちろん発達障害の程度や、知的障害を併存しているかどうかなど、個人差が大きいのは事実です。
しかし、結局は子どもが楽しめたり、興味の対象が広がったり、人生が充実したりすることが大切なのではないか。
そんな初歩的なことに、まめがバスケに魅了されてから気づきました。
まめのバスケ続報については、今後もお伝えさせていただく予定です。
少しでも、発達障害児の習いごとに悩む親御さんの参考になれば幸いです。
よく読まれている記事

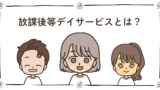
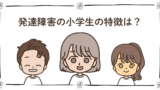
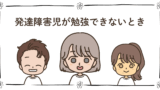
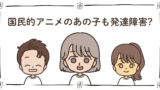
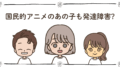


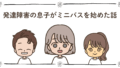
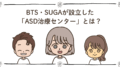
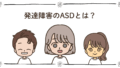
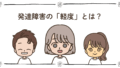
コメント