この記事では、発達障害と癇癪の関係性についてお話しています。
子どもに癇癪があると「発達障害かな?」と心配になってしまうことがあると思います。
結論から言うと、以下のようになります。
- 発達障害をもつ場合、癇癪がある可能性がある
- 癇癪がある場合、発達障害とは限らない
つまり、発達障害が先に判明している場合には、癇癪をもっている可能性があるでしょう。
しかし、癇癪が先に判明している場合には、イコール発達障害とは限りません。
わが家では発達障害児を育てていますが、癇癪がひどかった時期もありましたので、振り返りながら解説していきたいと思います。

癇癪はなぜ起こる?

子どもの癇癪は、手に負えなくて親御さんも困り果ててしまいますよね。
なだめようとしても逆効果で、お手上げ状態ということもあるでしょう。
癇癪は、イヤイヤ期などの子どもが自分の思い通りにならないときに感情を爆発させるもの、という認識があると思います。
しかし、実際にはわたしたちが思うよりも多くの原因が隠れているんです。
癇癪は「よほどのことがないと起きない」と思っている人もいるかもしれませんが、実はこんなにささいなことがきっかけで発動してしまう可能性があるのですね。

イヤイヤ期には逆鱗に触れそうなことばかり…!
1~2歳のまだ言葉がつたない時期には、特に癇癪として感情を爆発させることがあります。
しかし、2~3歳で少しずつ言葉を習得したり、欲求を伝える方法を獲得したりすると
泣き叫ばなくてもママにお願いを聞いてもらえた!
という成功体験を積むようになり、次第に癇癪が落ち着いていくといわれています。

ここまでは、定型発達児(発達障害ではない子ども)のお話です
しかし、言葉を話せる年齢になっても癇癪が収まらない場合には、発達障害の可能性が疑われることがあります。
発達障害には、癇癪を起こす原因と一致する特徴があるからです。
次の項目から、発達障害と癇癪の関連性を見てみましょう。
発達障害と癇癪の関連性は?

発達障害と癇癪には関連性があります。
しかし、お互いに必ず併存するものではありません。
発達障害=癇癪があるわけではありませんし、癇癪=発達障害であるという根拠もありません。
ただ、関連性があるのは事実なので、どのように発達障害と癇癪が起こっていくのか見ていきましょう。
発達障害=癇癪ではない
発達障害がある場合、必ずしも癇癪が伴うわけではありません。
しかし発達障害を持っていると、癇癪が起こりやすくなるのは事実です。
理由は以下の通りです。
発達障害があるからといって、癇癪が必ず起きるわけではありません。
しかし発達障害の特性ゆえ、気持ちが爆発したり本人にストレスがかかりすぎたりすることはあります。
その結果、本人の感情表現が癇癪となってあらわれる可能性があるのです。

わが家のまめが癇癪を起こしていたのも、上記が理由でした
1~2歳までだと、言葉が未発達なので癇癪はよくみられると思います。

もし発達障害があった場合、癇癪のような問題行動を繰り返すことで「まわりから注目してもらえる」「構ってもらえる」と勘違いし、おさまらないことがあります。
言葉やほかの表現方法を獲得する年齢になってからも癇癪が続く場合には、発達障害の可能性が考えられるでしょう。
癇癪=発達障害でもない
発達障害があると必ず癇癪がある、というわけではないように、癇癪がある子が発達障害であるとも言い切れません。
癇癪はさまざまな理由で起きる感情の爆発ですから、必ずしも発達障害が原因であるとはいえないのですね。
しかし、言葉で伝える方法を知っているのに癇癪が起き続けていたり、手が付けられないほどに暴れまわったりする場合には、発達障害の可能性も考えられるでしょう。
絶対ではないけれど、関連性があると覚えておきましょう!
発達障害で癇癪を伴うものは?

発達障害の種類のうち、癇癪を起こしやすいとされているのはASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如多動症)の2つです。
この2つは、コミュニケーションや対人関係において課題がある発達障害。
他者の行動や自分にかかわるものに、過敏に反応することがあります。
だからといって絶対に癇癪があるわけではありませんが、感情のコントロールが難しいため、癇癪となって出現することがあるかもしれません。

わが家のまめはASDとADHDの混合型です。
それゆえ、どちらの要素も含んだ癇癪を経験してきました
それぞれの発達障害がどのような形で癇癪を起こすのか、見てみましょう。
ASD(自閉スペクトラム症)
癇癪を伴う可能性がある発達障害は、ASD(自閉スペクトラム症)です。
ASDをもつ子が癇癪を起こすのは、たとえば以下のような場面があります。
ASDをもっていると、人と関わったり仲良くしたりするよりも「自分のしたいことをしたい」という欲求が強い傾向にあります。
さらに毎日のスケジュールや段取り、着る服、食べるものなどにこだわりがある場合も。
そのルーティンや馴染んだ環境が何らかの形で崩れたとき、パニックになって癇癪が起きる可能性があります。
またASDの子は、適切なコミュニケーション方法を獲得するにも時間がかかる場合があります。
相手に嫌なことを言われたりされたりしたときに、癇癪を起こして気持ちを爆発させることがあるかもしれません。

ASDは言葉の遅れもあるから、うまく伝えられないもどかしさが「癇癪」となって表れることも。
まめは幼児期にASDの傾向が強かったため、療育に通って少しずつ社会性を訓練してきました。
発達障害の程度にもよりますし、ASDは知的障害を伴うこともあるので、癇癪の対処法などもそれぞれだと思います。
わが家の場合は、単純に「伝え方がわからない」「辛抱ができず嫌で嫌でたまらない」という気持ちが爆発していたようです。
そのため、療育の集団クラスでお友達と意見交換をしたり、作戦会議をしたりする中で
という、さまざまな「伝え方」を学んできました。

今までは上記のようなシチュエーションで、何をどのように伝えれば良いかわからなかったまめ。
しかし、相手に意見を伝えたり拒否したりするにはいろんな方法があるんだということを学び、少しずつ実践できるようになっていきました。

内向的な性格もあるので、まだきちんと意見を主張できずダンマリしてしまうこともありますが、幼児期と比べると成長しました!
ADHD(注意欠如多動症)
癇癪を伴う可能性がある発達障害は、ADHD(注意欠如多動症)です。
ADHDが癇癪を起こすのは、以下の理由が考えられます。
ADHDの特性の中に「衝動性」というものがあり、これが癇癪と関連性が高いとされています。
衝動性は、言葉通り衝動的な行動に出てしまう特性のこと。

本人もそのときの行動をよく覚えていないくらい、とっさに身体が動いてしまうものなんです…
衝動的に手が出てしまう、喋ってしまう(静かにしなければいけないときでも)、動いてしまう…
「今はこの行動をすべきではない」と頭ではわかっていても、自分でストッパーがきかないことがあるのです。

この原理で癇癪が起こってしまうと、本人にもどうしようもなく、なだめるのが難しいことがほとんどです。

衝動的に「やりたい!」と思ったことが阻害されたとき、さらに「なんでできないの!?」という反抗が重なって、癇癪になってしまうようです
まめの場合はASDの特性も相まって、何かに集中しているときに「もう行くよ」と言われたり、買ってほしいものがあるのにダメだと言われたりすると、辛抱ができないことがありました。
それでも、出先や他人がいる場所ではあまり起こらず、家族の前だけだったので
まめなりに空気を読んで癇癪を起こしているのかな?
泣き叫んだり暴れたりすることが「恥ずかしい」と認識しているのかな?
なんて思ったりしました。
まめは、小学校に上がるとADHD要素が強くなっていったので、小4の今、衝動性はまだ落ち着いてはいません。
でも、衝動的に癇癪を起こしたり、手が付けられなくなったりすることはなくなりました。
今は衝動性によってカッとなるのではなく、イライラした気持ちを引きずりながら自分の好きなこと(Youtubeを見る、絵を描く、工作をするなど)に没頭するようになりました。
こうすることで、そのうち気持ちが切り替わったり、落ち着いて話してくれたりするように。

「これをすると気持ちが落ち着く」という活動がたくさんあると良いよね!
発達障害で癇癪を起こす場合の対処法

発達障害の特性によって癇癪が起こる場合には、いくつかの対処法があります。
これは、わたしが子ども発達障がいアドバイザーの資格を取った際に学んだもので、実際にまめの育児にも活かしてきました。
もしお子さんに効果がありそうでしたら、ぜひ試してみてください。
反応しない
癇癪の対処法1つ目は、反応しないことです。
これは「無反応」と呼ばれる方法で、簡単に言うと「落ち着くまでそっとしておく」ということ。
一見、子どもの癇癪を無視しているようですが、実は
子どもが自分自身で問題に折り合いをつけられるようにする
という目的を持った対処法なんです。
発達障害がある場合、癇癪や不適切な行動(他害、暴言など)をすることで大人に怒られると

注目してもらえた!嬉しい!
と勘違いしてしまうことがあります。
そして、周囲の気を引きたくて癇癪を繰り返してしまうことがあるようです。
「無反応」という対処法は、問題行動をしても注目されないことを学んでもらう機会にもなります。
しかし、一度や二度無反応をしたからといって、子どもが学んで癇癪をやめるわけではありません。

無反応は、その対応を貫き通すわたしたち親の覚悟も必要なんです
無反応という対応を行った場合には、放置したままにせず、落ち着いたときに「さっきは嫌だったんだね」と共感してあげることが大切ですよ。
このあと詳しく解説しますが、こうすることで子どもが
泣き叫んでも反応してもらえないけど、泣き止んだら反応してくれた!
という成功体験を積むことにつながります。
クールダウン場所に移動する
癇癪の対処法2つ目は、クールダウン場所に移動することです。
クールダウン場所とは、子どもが癇癪を起こしたときに一時的に移動できる場所のこと。
この方法を用いるには、癇癪を起こしていないときにクールダウン場所を決めておくことが必要です。
癇癪を起こしてから突然「クールダウン場所だよ」と言ってどこかへ連れて行っても、余計に不安を掻き立ててしまうでしょう。
あらかじめ「嫌な気持ちになったらここへ行こう」という行動パターンを本人と話し合っておくのがおすすめです。
\ たとえば… /
癇癪を起こしたときに、上記の共通認識があることで、子どもは気持ちを落ち着けやすくなるでしょう。

わが家でも、実際に家でクールダウン方法を話し合って、嫌な気持ちになったときに実践してみました。
この方法は、発達障害のあるまめだけでなく妹のナツに対しても効果的で、子どもたちが自分自身で気持ちを切り替えることが上手になった気がします。
落ち着いたら褒める
癇癪の対処法3つ目は、落ち着いたら褒めることです。
これは、1つ目の「無反応」から「クールダウン場所に移動する」という対処法を経て、ようやく癇癪がおさまったときに褒めてあげるという方法です。
「無反応」の項目で、子どもが癇癪を起こして注目されたいことが理由であるとお話しました。
しかし、周囲の大人が反応しないことで「泣き叫んでも注目してもらえない」と学びます。
そして、クールダウン場所に移動したり自分で折り合いをつけたりして、癇癪がおさまったときに
さっきは〇〇がしたかったんだよね
と、癇癪を起こしていたときの気持ちを代弁したり、共感したりすることで、子どもは
こうすれば注目してもらえるんだ!
と学び、少しずつ「解決法=癇癪」という意識がなくなっていくことが期待できます。


問題行動(癇癪)で注目されるのではなく、適切な行動(落ち着いて行動する)で注目されることを気持ちよく思ってもらいましょう!
発達障害で癇癪を起こす場合の予防策

発達障害の特性で癇癪を起こすときには、予防策があります。
予防策を施すことは親御さんの負担が減るだけでなく、子どもにとっての成功体験を増やしてあげることにもつながります。
少しでも効果があると、子どもの成長を感じて嬉しくなることでしょう。

個人差があるので、必ず効果があるとはいえないかもしれません。
それでも、何が効くかわからないのだから、とりあえずやってみましょう!
視覚補助で見通しを立てる
癇癪の予防策1つ目は、視覚補助で見通しを立てることです。
この方法は、ASDやADHDをもつ子が「急に予定が変わった」「今やりたいのはこれなのにダメといわれた」という気持ちの表れで癇癪が起こる子に、効果があるといえます。
たとえば、その日の予定をイラストや写真で見える化して、これからどんなことが起こるのか予測できるようにしてあげましょう。
発達障害のない大人は、自身の経験や知識からある程度今後を予測できたり、万が一のときの対応を考えておけたりします。

しかし、発達障害のある子どもにはそれが難しいどころか、不安でたまらなくなってしまうことも…!
そんな不安を払拭してあげられるよう、見通しを立てるサポートをするのが効果的。
毎日の予定をイラストや写真にするのは大変ですから、カードをマグネットで貼り付けられるようにするのがおすすめです。
絵が得意な親御さんは、ホワイトボードに可愛く予定を描いてあげるのも良いですね!

特に、いつもと違う発表会や運動会の日だったり、あまり行ったことのない場所に行ったりするときには、見通しを立てて安心感を与えてあげましょう。
短く簡潔に指示をする
癇癪の予防策2つ目は、短く簡潔に指示をすることです。
ASDやADHDをもっていると、長々しい指示を理解するのに時間がかかることがあります。
たとえば、3つ4つのことを一度に指示しても、最後の1つしか覚えていられないことがあるでしょう。
例として「おもちゃを片付けたら箱をしまって、上着を着て玄関まで来て」という指示があったとします。
すると、発達障害をもつ子は次のように感じるかもしれません。

あわわわ…!最後のほう、もはや片付けとか関係なくなっちゃってるよ!!

それが発達障害(特にADHD)の特性でもあるんです。
指示が抽象的すぎて的確に伝わっていないから、関係ないことまであれこれ考えてしまうんですね
親御さんは分かりやすくシンプルに指示を出したつもりでも、発達障害の子には上記のように聞こえている可能性があるということです。
その場合、子どもが指示を理解して適切に行動できるはずがなく、結局怒られて癇癪に発展…
ということが起きがちなんですね。
そうならないために、短く簡潔な指示をすることが大切なんです。
上記の例でいうと、こんなふうに分けるのがわが家では効果的でした。
このように細かく分けて1つずつ指示すると、まめは1つ1つ自分のペースでこなしてくれました。

ポイントは、1つの指示をして行動が完了したら、次の指示をすることです!
発達障害の中でもADHDには「不注意」という特性があり、気が散りやすいので、複数の指示を頭の中で整理しきれないことがあります。
指示が理解できず、適切な行動ができないことで、自信喪失につながったり癇癪が起こりやすくなったりするのです。
すべての指示を理解し、最後まで適切に行動できたら、本人も「これで合ってるんだ!」と嬉しくなりますよね。
そのためには、短い言葉で簡潔に指示することが大切なのだと学びました。
ヘルプサインの出し方を教える
癇癪の予防策3つ目は、ヘルプサインの出し方を教えることです。
ヘルプサインとは、文字通り「助けを求めること」。
何をすれば良いか分からないとき、どこへ行けば良いか分からないときに「分からないので教えてください」とヘルプサインを出せることは、発達障害児が社会生活に適応するために重要なスキルです。
でも、発達障害児に「分からないときは分からないって言ってね」といっても、なかなか実行できません。
まめの場合は療育の助けもあり、次のような方法でヘルプサインを出す練習をしました。
ポイントは、実際にヘルプサインを出す必要のある状況を体験することでした。

家ではなかなかそういう状況に出くわさないので、療育でシミュレーションできたことも大きかったです
発達障害があったり、知的障害を伴っていたりすると、いつどんなときに自分が困っているのか、いつヘルプサインを出すべきなのかが、そもそも分かっていないことがあります。

全部が分からなさすぎて、何が分からないかも分からない状態になることがあるよ…
そんな状態で、自ら判断してヘルプサインを出すことは難しいですよね。
そのため、子どもの困りごとに大人が先に気づいて「今だよ!〇〇くださいって言うんだよ」と背中を押してあげるサポートが効果的でしょう。
ヘルプサインを出せるようになると「今何をしたらいいか分からない…」というパニックに陥ることが減り、癇癪につながりにくくなるかもしれません。

ヘルプサインを出すことは、発達障害に限らずどんな子にとっても大事なスキル。
個人的には、未就学児のうちに教えておくことをおすすめします!

小学校に入ると先生が助けてくれることも減るし、自分から「わかりません」って言わないと置いてけぼりになっちゃうからね…
まとめ
発達障害と癇癪の関連性について、わが家の体験談をもとに解説しました。
癇癪が伴うことのある発達障害はASDとADHDで、偶然にもまめはその混合型の特性を持っています。
それゆえ、双方の特徴を含んだ癇癪を経験してきました。
わが家の体験談や対処法、そして予防法が、なんらかのお役に立てれば嬉しいです。
よく読まれている記事






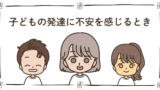
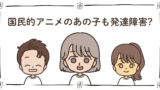

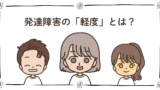

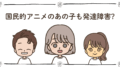


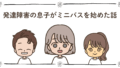
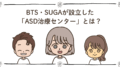

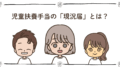
コメント