「発達障害の診断って、どうやって決まるの?」
「検査で数字が出たら即診断されるの?」
子どもの発達に不安を感じている人は、そんな疑問を持ったことはありませんか?
子どもの行動や育てにくさから発達障害を疑ったとき、多くの保護者がまず気になるのが「診断の基準や流れ」でしょう。
しかし実際には、発達障害の診断は単純な数値やテストの結果だけで決まるわけではなく、専門医が複数の要素を丁寧に確認した上で判断します。
診断には医学的な基準がありますが、それを知ることで不安が和らぎ、受診への第一歩を踏み出しやすくなるかもしれません。
この記事では、発達障害の代表的な診断基準「DSM-5」に基づく考え方と、実際に病院で行われる診察や検査の内容、そして親が気をつけておきたい視点についてわかりやすくご紹介します。

発達障害3つの主なタイプ

発達障害と一口にいっても、その中にはいくつかの分類があります。
現在、医療の現場では「DSM-5(アメリカ精神医学会の診断基準)」に基づいて診断が行われます。
主に診断されるのは、次の3つのタイプです。
自閉スペクトラム症(ASD)は対人関係の苦手さやこだわりの強さ、感覚の偏りなどが特徴の発達障害です。
少し前まで「自閉症」と呼ばれていましたが、現在は少し範囲が広がってさまざまな発達障害を包括して呼ぶようになりました
注意欠如多動症(ADHD)は、芸能人でも公表している人が複数いる発達障害。
不注意、多動性、衝動性の3つが主な特徴で、日常生活に支障をきたしている場合に診断されます。
そして学習障害(SLD)は、読み書きや計算など特定の学習領域に著しい困難があるタイプです。
実際に診断を受けるには、単に「当てはまる特徴がある」だけではなく、それが生活や社会的な適応にどの程度影響しているかが大きな判断材料になります。
発達障害の3種類については、こちらの記事でくわしく解説しています。
発達障害の診断基準【DSM-5】とは?
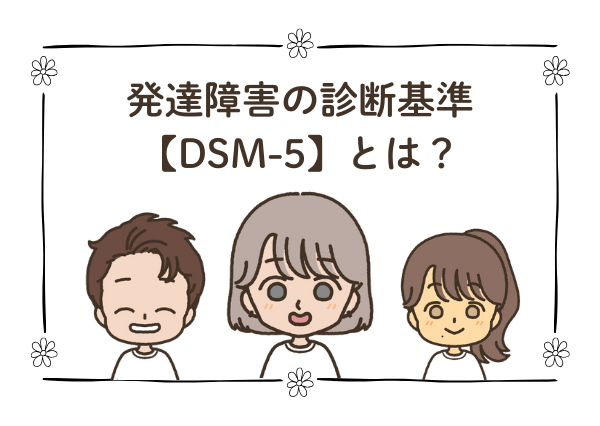
DSM-5とは、発達障害の診断基準となるマニュアルのことです。
日本語にすると「精神疾患の診断・統計マニュアル第5版」という意味で、アメリカ精神医学会が発行している基準。
日本を含む多くの国で、医師や心理士が発達障害の診断においてこの基準を用いているそうです。
DSM-5の目的は?
DSM-5の目的は、精神疾患や発達障害の特性を科学的に分類し、診断の基準を明確にすることです。
医師や専門家が共通の基準で判断するための、ものさしとして機能します。
子どもが支援を受けるうえでの根拠となる「診断名」を決定する際にも使用されます。
DSM-5で何がわかる?
DSM-5を用いた診断では、以下のような特性の有無・程度が明らかになります。
上記のことがわかると、子どもが感じている「困りごと」が明確になり、適切な支援や療育につなげる手がかりになります。
またDSM-5では、それぞれの障害ごとに具体的な診断基準が明記されています。
たとえば、自閉スペクトラム症(ASD)の診断基準は、以下の2つです。
上記のの特徴が乳幼児期から続いていて、日常生活に明確な影響を及ぼしている場合、診断が検討されます。
また、知的発達や言語の発達も合わせて評価され、他の要因との区別も慎重に行われます。
DSM-5の検査にかかる時間は?
「DSM-5を検査するにはどれくらいかかる?」
という疑問も時折聞かれます。
しかし、DSM-5というのは「WISC」や「K式」のような検査ツールではないため、所要時間は定められていません。
そのため、DSM-5に基づいた情報を収集するのに数時間〜数日を要することがあるでしょう。
1回で完結することは少なく、数回の通院が必要になります。
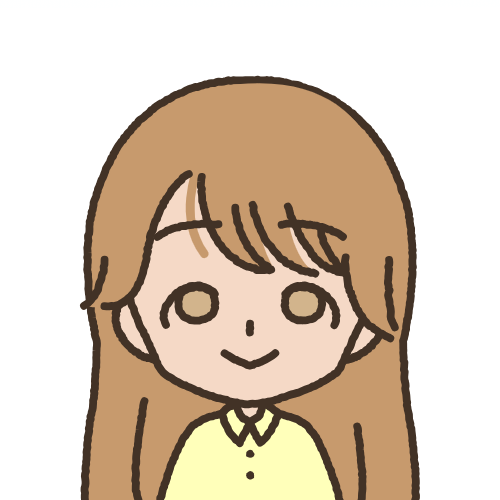
「DSM-5を受ける」という言い方はしないんだね

DSM-5はあくまで診断基準なので「DSM-5に基づいて診断する」という言い方になりますね
DSM-5の対象年齢は?
DSM-5は全年齢に対応しており、乳幼児から高齢者まで使用可能です。
ただし、子どもの場合は発達の過程に個人差があるため、一般的には3~5歳以降から本格的に診断が行われることが多いようです。
ASDの場合、早ければ2歳から診断されることもあります。
ASDの特徴は独特なので、1歳半くらいから兆候(オウム返しする、目が合わないなど)がみられることもありますよ!
DSM-5の結果の見方は?
DSM-5では、各障害ごとに「いくつ以上の症状が○ヶ月以上続いている」と、明確な診断基準が設けられています。
医師はこれに当てはまるかを確認し、該当すれば診断名を付けます。
たとえばADHDの診断基準では、不注意・多動性・衝動性のうち、以下のポイントを注意深く見ています。
診断の流れ|病院で何をする?

発達障害が診断される流れは、まず小児神経科や発達外来などの専門機関に相談することから始まります。
専門家や医師と面談することになると思いますが、最初は保護者からの聞き取りが中心になるでしょう。
子どものこれまでの成育歴、行動の特徴、家庭や園・学校での様子などを詳細に確認します。
保護者の聞き取り中は、別室で子どもを預かり様子を見ることもあります。

別室で児童相談員さんや保健師さんが子どもと遊んでくれたり、おもちゃを貸し出してどんなふうに遊ぶのか見たりしてくれました
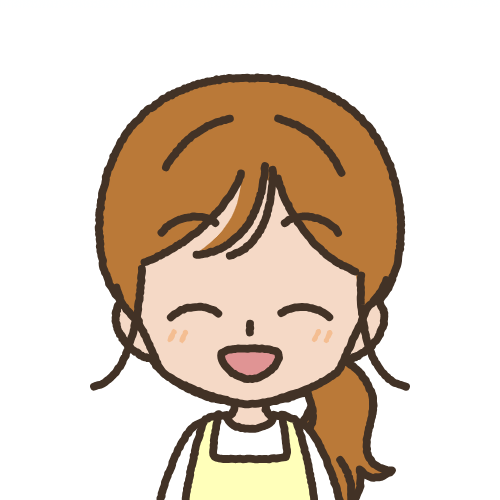
子どもの遊び方で発達の傾向が見えたりするなら、専門家に観察してもらえるのは心強いね!
そのうえで、必要に応じて発達検査(新版K式発達検査、WISCなど)や心理検査、行動観察などを推奨されます。
また、園や学校からの観察記録や、家庭での記録(育児日記・動画)なども参考資料になりますよ。
担任の先生との面談記録や、ふだんの動画などがあれば、専門家や医師に見せてみると良いでしょう。

あ、あの…わたしの場合はお医者さんから「動画とかそういうのはいいです」って言われました(笑)
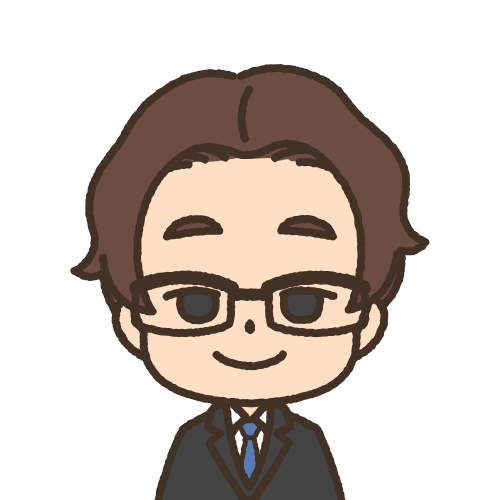
参考資料をどう扱うかは医師次第なので「そんなのいらないよ」と思う医師もけっこういますよ!お気になさらずに…。
診断には、複数回の受診が必要なことが多くあります。
その日、とか翌日、などすぐに結論が出るわけではありません。
医師は、本人と家族の生活に「どの程度困りごとがあるか」を丁寧に見極めながら、支援が必要かどうかという視点で診断を進めていきます。
診断はレッテルではなく「支援への入口」

発達障害の診断は、子どもにレッテルを貼ることではありません。
むしろ、その子に合った支援を受けるためのスタートラインとして位置づけられるべきものです。
診断があることで、学校での配慮や福祉サービス、療育支援などの制度につながりやすくなりますよ。
一方で、診断名がつかないから支援を受けられないというわけではありません。
医師の意見書や保育・教育現場からの要請で、診断がなくても配慮や支援を受けられるケースもあります。
大切なのは、今どんなことで困っていて、どう支えれば暮らしやすくなるかという視点。
診断はあくまで、その手がかりのひとつにすぎないのです。
まとめ
発達障害の診断は、DSM-5という医学的な基準に基づいて行われています。
DSM-5は単なるチェックリストではなく、子ども一人ひとりの困りごとや背景を丁寧に見つめながら判断される基準です。
診断を受けることは決してマイナスではなく、適切な支援につながる第一歩であると認識しましょう!
「気になるけどまだ受診するのは早いかも」と感じるときでも、不安があるなら一度相談してみることをおすすめします。
受診や相談に「早すぎる」ことはありません。
また、診断されてもされなくても、その結果にとらわれすぎないでくださいね。
それよりも、どうすれば子どもがもっと楽に生きられるかを一緒に考えていくことが、何より大切なスタートになるでしょう。
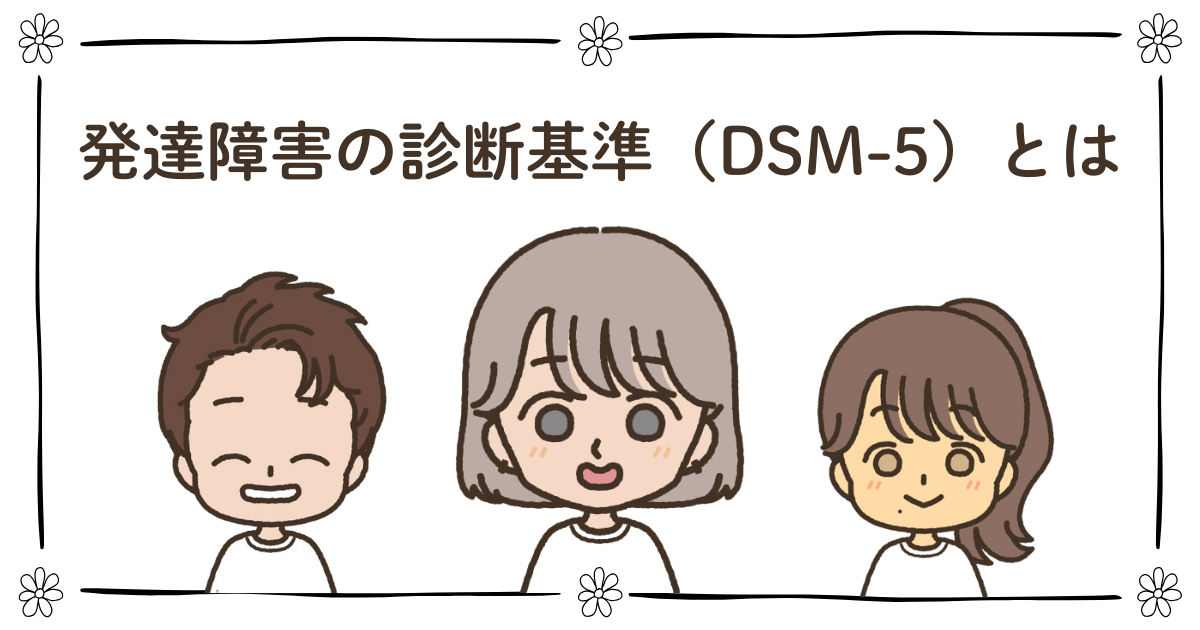


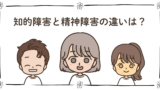
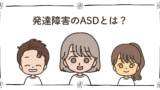


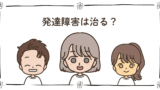



コメント