発達障害をもつ子どもを育てる親御さんは、
「発達障害って治るのかな?」
という疑問を持ったことがあるかもしれません。
実際には、発達障害そのものを完全に治すことは難しいとされています。
しかし、適切な療育やサポートを受けたり、環境を調整したり、教育・心理的な支援を受けることで、症状を改善させることは可能なんです。
症状が改善すれば、日常生活での困難を軽減することにもつながります。
この記事では、発達障害の特徴や改善の可能性、そのためのサポート方法について解説しています。

発達障害は治るのか?

発達障害は病気ではなく、生まれつきの脳の特性や神経発達の違いによって現れる状態をいいます。
病気ではないので「治療で完治させる」という考え方は当てはまりません。
症状の改善や、生活のしやすさの向上が主な目的になることを、念頭に置いておきましょう。
診断を受けた時点で、その特性を理解し、サポートできる環境を整えることがもっとも重要。
早い段階で、発達障害への理解と支援をスタートさせることで、困りごとを軽減したり、学習や社会生活に適応させてあげられるかもしれません。
発達障害は「治す」ものではない。
この前情報をしっかり頭に入れた上で、具体的にどのようにして改善できるのか見ていきましょう。
発達障害は完治でなく「改善」が可能

発達障害は、適切な支援を受けたり環境を整えたりすることで「症状を改善させる」ことが可能です。
発達障害というもの自体は、生まれつきの脳機能の障害なので、根本的に治すことは不可能。
少しでも改善されるならベストを尽くしたい!
そう考えている親御さんは、ぜひ参考にしてみてください。
療育を受けて改善を目指せる
発達障害は、早期発見が改善につながるポイントです。
発達障害には軽度やグレーゾーンという範囲もあるため、乳幼児期だと
子どもだから落ち着きがないのは当たり前だよね
言葉が遅いのは個人差だよね
と、発達障害を疑わずにスルーされてしまうケースもあります。
ASD(自閉スペクトラム症)などは、1歳くらいから特徴が出現するため、診断が早い傾向がありますが、ADHD(注意欠如多動症)やLD(学習障害)は、ある程度大きくならないと判断できないのです。
また、親御さんが発達障害の可能性を否定したいがために「障害ではなく個性だと思うから」といって検査を受けなかったり、支援の道を拒否したりすることがあります。

それこそ「大きくなれば治るはず」と思ってしまうのかな…

発達っ子ママとして気持ちは分かりますが、子どもが何らかのサインを出しているなら、親御さんは真っすぐ向き合うべきだと思います
発達障害の傾向や兆候に早く気が付くことができれば、療育や個別支援といったサポートを取り入れることができます。
これにより、発達障害による困難を軽減できたり、本人がより生きやすく感じるヒントに出会える可能性があるのです。

たとえば、コミュニケーションが苦手な子どもにはSST(ソーシャルスキルトレーニング)を行い、順番やルールを学ぶ支援方法があります。
学習面では、個別学習支援を使って学校の学習をフォローしたり、理解度や習熟度を高めたりすることが期待できます。
また、生活環境をその子向けに整えることも効果的。
過度な刺激や予測不能な変化を減らすだけでも、発達障害の子にかかるストレスが軽減され、行動や学習の安定につながる可能性があります。
長期的な支援で見守ってもらえる
発達障害は、子どもだけでなく大人になっても特性が残ることがあります。
最近では「大人になって検査をしてみたら発達障害の診断が出た」という人も増えてきているんです。
子どもの頃は異変を感じなくても、社会に出てみたら
- 忘れものや遅刻が多い
- 空気が読めないといわれる
- コミュニケーションがつらい
という生きづらさに気付くようになった、というケースが多くあります。
参考:政府広報オンライン
このような特性を感じた場合、大人になってからでも支援を受けることは可能です。
職場や家庭での環境を調整したり、心理的サポートを受けたり、スキル習得のための支援を受け、生活の質を向上させることが期待できますよ。
特性を理解した上で合理的配慮を取り入れることで、大人になってから自立したり、社会に参加することが可能になります。
発達障害は、大人になっても「完治」することは難しいもの。
しかし、生活や仕事で困難を減らすことが、じゅうぶんに期待できるのです。
発達障害を改善するためにできること

発達障害は完治するものではありませんが、改善することはじゅうぶんに期待できます。
しかし「改善すること」にばかり目を向けるのではなく「本人が生きやすいと感じること」のほうを意識したいと、個人的には思っています。
改善がみとめられたとしても、本人が生きづらくつらい思いをし続けていては、なんの意味もありません。
これから、親元を離れても自分の足でしっかり生きていけるよう、幸せに自立してくれることがわたしの願いです。
それでは、発達障害を改善するためにできることを見てみましょう。
環境を整える
生活や学習の環境を整えることは、発達障害の特性に合わせた重要な対策です。
身のまわりを整理整頓したり、これから起こる予定を可視化したり、ルーティンを作ったりすることで、子どもは安心感を得られます。

安心して毎日を過ごせることで、次第に混乱やストレスを減らすことも期待できますね。
学習の順序を明確にしたり、家庭内でのルールをわかりやすく示すことも有効でしょう。
このように、その子を取り囲む環境を整えることは、症状を「治す」ことではありませんが、生活のしやすさや集中力の向上につながり、日常での困難を大きく軽減できます。
個別療育・学習支援を受ける
発達障害の特性に応じた、個別療育や学習支援を受けることで、社会性や学習スキルを伸ばすことができます。
専門家によるアセスメントをもとに、得意な部分を活かしながら苦手な部分を補う指導が推奨されていますよ。
家庭での取り組みやサポートと組み合わせることで、学習意欲の向上が見込めたり、問題行動が落ち着いたりする変化が期待できるでしょう。
早い段階から支援をスタートすることは、学校生活や将来の自立にも大きな影響を与えます。

家庭でのサポート方法
家庭では専門的なサポートをするというよりも、子どもの「できたこと」を積極的に褒めることから始めてみましょう。
過剰に叱らず、得意なことから伸ばす関わり方が重要です。
日常の小さな成功体験を積み重ねることで、自己肯定感を育むことができるでしょう。

また、学校や療育でおこなっている支援方法を家庭で実践することも効果的です。
たとえば1日の予定や週間スケジュールを貼りだしておき、子どもがいつでも「このあと何が起きるのか」を把握できる状態にしておく、などです。
未来の見通しを示すことで、子どもは突然の環境変化によるストレスを全面に受けることなく、心の準備ができます。
たったこれだけのことでも、子どもの心に安心感を与え、予測不可能な状況での不安やストレスを軽減してあげることができるのですね。
家庭で適切なサポートをすることは、療育や学校での学習効果を高める効果もあります。
「発達障害のサポートはすべて専門家に任せるべき」と考えず、家庭では家庭での役割があることを把握することが大切ですね。
発達障害が治ると誤解される理由は?

なぜ、一部の人たちは「発達障害が治る」という情報を信じてしまっているのでしょうか。
それは、まだ「発達障害」という言葉が生まれたばかりであることに起因していると考えられます。
わたしの周りでは「発達障害って、ちょっと変わってるな~くらいのものでしょ?」という考えの人がまだまだ多い気がします。
特に実家の両親や親戚たちからは、

何でもかんでも「障害」って名前を付ければいいってもんじゃない
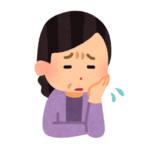
苦手は特訓して克服させないと。発達障害だから~なんて言ってるからどんどんダメになっていくのよ
という意見をもらうことが多くあります。
発達障害は生まれ持った脳機能の障害であり、治療により完治するものではありません。
しかし、昔から発達障害を患った子どもはたくさんいたはずなのに、呼び名がありませんでしたよね。
そのため、昔の人は

昔から変わった子どもはいたけど、みんな一緒に育ったものだ!
今の子はすぐ「発達障害」といって甘えている
という考えが根付いているのだと思います。
でもそれって、本当にその「変わった子」たちが苦しみや生きづらさを克服したということでしょうか?
その子たちの発達障害が完治して、無事に大人になれたということでしょうか?

それは、その「変わった子」だと思われながら生きてきた人たちにしかわからないのではないでしょうか
このような考え方が残っていることで、発達障害という障害自体が軽視されているように感じます。
具体的に「発達障害は治る」と思われている要因について見てみましょう。
メディアや作品での描写
テレビや漫画、映画などのメディアで、発達障害の子どもや支援を受けながら困難を克服し、あたかも「治った」かのように描かれることがあります。
もちろん「支援を受ければ治ります」と直接的な表現をしているわけではありません。
しかし、ドラマなどで「今までできなかったことが最終回でできるようになった」という描かれ方をしていると、視聴者としては

努力してとうとう成し遂げたんだ…!

発達障害があっても、頑張ればできるようになるのね!
というふうに感じやすいですよね。
これにより、発達障害児を育てる親御さんや周囲が「療育や支援を受ければ治る」と誤解するケースがあります。
実際には症状は残る場合が多く、改善と適応の”プロセス”が描かれていることを理解することが重要ですね。
メディアで描かれるのは物語上の演出であり、現実の発達障害は完治ではなく支援による軽減が中心です。
成長や環境調整による好転
子どもが成長する過程で、発達障害の困りごとが軽減されることはよくあります。
生活習慣を変えたり、学習環境を整えたり、ここまででご紹介してきた支援や工夫により、発達障害の改善が叶ったケースですね。
たとえば、通常学級から支援学級に転籍したことで学習面の理解度が高まったり、放課後等デイサービスに通ったことで社会スキルが身についたり…
「以前より問題行動が少なくなった」「ゆるやかに成長している」と感じられる場合があります。

このように好ましい変化を「治った」と誤解してしまうことで、発達障害が完治するものだと思い込む原因になります。
しかし、実際は特性が残ったまま「適応できるスキルや対応策を習得した」というだけの結果なのです。

いや、それだけでじゅうぶん立派な成長だよ!?
診断やラベルへの誤解
くり返しになりますが、発達障害は病気ではありません。
しかし、発達障害は病院で医師から診断されるものなので、そのイメージから「診断=治療対象」と考えられてしまいがち。
発達障害という診断は、その子の特性を理解し適切な支援を受けるための目安であり、病気のように治療で消えるものではありません。
診断名に振り回されず、困りごとを軽減するための具体的な支援方法を重視することが大切ですね。
わが家のケース

それでは、わが家のまめが持っている発達障害と知的障害が、どのように変化してきたのか振り返ってみたいと思います。
結論からいうと、まめの発達障害(当時は発達遅延)を疑い始めたのは乳幼児期のころで、現在小4になったまめは、知的障害の診断がおり支援学級に通っています。
つまり、発達障害と知的障害はほぼ改善していない状態といえるでしょう。
しかし、この10年の間にはさまざまな変化がありました。
一言で「改善していない」というと、何も変わっていないような印象を与えてしまうと思うので、ここから詳しく共有していきます。
社会性の変化
まず、まめの10年間でもっとも変化したと感じているのは、社会性です。
社会性は、間違いなく向上しています。
幼稚園の頃、まだ発達がグレーだった頃には、集団行動が苦手でマイペースさが突き抜けていたまめ。
教室でみんなと一緒に座ったり、お遊戯をしたり、工作をしたりすることはできましたが、ルールのある遊びをすると、ルールが理解できずふら~っとどこかへ行ってしまうことがありました。
特にドロケイやしっぽ取りなど、子どもたちがあちこちに散るような遊びは、まめにとって「みんな自由に遊んでいる」ように見えたのかもしれません。
みんなで遊んでいることをすっかり忘れ、1人で遊具で遊び出したりしていました。
しかし、小学校に入学したころから徐々にマイペースさが抜け、社交性がついてきました。
それまでは1人遊びがメインだったのが、友達に興味を持ち始め、外で一緒に遊ぶようになってきたんです。
しかし、幼稚園時代に友達とのかかわり方をじゅうぶんに学ぶことができなかったためか、距離感の保ち方はずっと課題がありました。

まめの場合、ちょっかいを出したりしつこくしたり、相手の子が「やめて」と言ってもおふざけをやめなかったり…
お友達に不快な思いをさせてしまっていました
それはそれで周囲や先生に謝罪をしながらも、友達に興味を持ち始めていることは「成長の証」として、前向きにとらえるように。
小4になったいまも、相手の表情や場の空気を読み取ることが苦手で、適切な行動をとれないことはあります。
それでも、まめのペースで確実に社会性はついてきて、現在ではミニバスに入部して活動できるまでになりました。

ミニバスといっても上下関係は厳しいし、コーチは怒鳴るし、楽ではない世界です。
それでも、バスケがうまくなりたい一心で、チームになじんで頑張っています!
学習面の変化
学習面は、まめのなかでもっとも優先度の高い課題です。
幼児期から小学校低学年までは、そこまで学習の遅れもみられませんでした。
小4になって学校から指摘され始め、知的障害という診断がおりました。
これに関しては「改善しなかった」「悪化した」というより、まめの知能発達が緩やかだったために、小学校の学習スピードについていけなかったということだと思います。
低学年の学習はそこまで難易度が高くなかったので何とかなっていました。
しかひ3~4年生からぐっと難しくなり、わたしもフォローができなくなっていきました(情けない…笑)。
そして、このまま通常学級で学び続けても良い未来が期待できないということで、支援学級への転籍が決まったという経緯です。
\ 支援学級への転籍についてはこちら /
行動面の変化
行動面においても、まめには間違いなく向上がみられています。
成長にともない、問題行動が減って正しい行動ができるようになっています。
特に、周囲の様子をうかがって「今これをするのは間違っているかな?」と、自分で判断するのが上手になってきました。

この方法は、幼稚園のときに療育で取り入れていたのですが、小学生になりだんだん定着してきました
ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如多動症)を持っていると、その時にすべき適切な行動がわからなくなることがあります。
ASDは自分の世界に入り込んだり、周囲に合わせるのが苦手だったりしますし、ADHDはつい集中力が切れてしまったり、衝動的に「今やりたいこと」を優先してしまったりするからです。
まめもその特性があり、
- 授業中にノートをとる
- 体育の時間に背の順に並ぶ
- 先生が話しているときに前を向く
という、小学生が自然にやっているような行動さえも難しいことがありました。
そんなとき、療育で「まわりのお友達を見て行動してみよう」という声かけが行われていました。
まめが今すべきでない行動をしていると、先生がトントンと肩を叩いてくれて
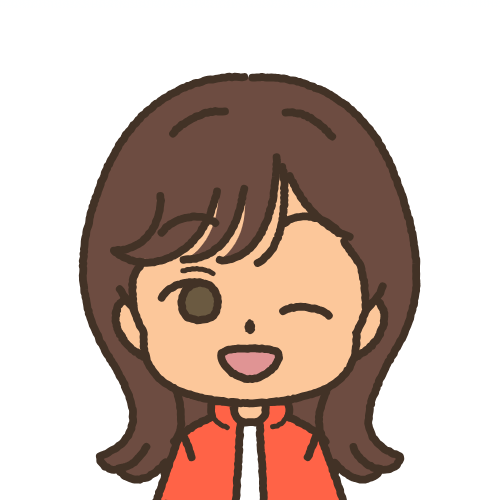
まわり見てみて。みんな何してる?
と、本人に周囲を見渡してみるよう声をかけてくれます。
その声でやっと我に返り、まわりのみんなが自分とは違う行動をしていることに気づきます。
そして、お友達が何をしているか観察して、自分も同じ行動に移る。
という練習でした。
この練習のおかげで、小学校に入学した当初から徐々に
何をすべきかわからなければ、まわりのお友達を見てみる
という行動が自然にできるようになりました。
それでも最初は、自分の「やりたい!」が勝ってしまい、授業中に立ち歩いたり、気になるものがあると列からはみ出たりしていました。
そういった細かい「間違った行動」が減っていき、まわりのお友達を見て
- 今これをやる時間じゃないんだ
- これはあとでやろう
- みんな〇ページを見てるからとりあえず開こう
と、その場にふさわしい行動を自然と見つけ出せるようになっています。
まだまだ集中力が切れてしまうことや、面倒なことに手をつけなかったりするときもありますが、幼児期の自由すぎる行動と比べれば、大きく成長しているのが分かります。

今では、バスケ部の遠征にも安心して送り出せるようになりました!
現地で身勝手な行動をしていることもないそうで、とても頑張っています
本人の気持ちの変化
本人の気持ちの変化も、親として大きな成長を感じています。
幼児期はとにかくマイペースで「なんでも自由にやりたい」という思いが強かったまめ。
それが、小4になった現在は「成長したい」「カッコよくなりたい」「頑張りたい」という、メラメラした向上心を感じるようになりました。
確かに宿題もせずダラダラすることはありますし、時間にルーズな点もなかなか直りません。
しかし、ただただ楽しさを追い求めていた幼児期に比べると、1つひとつの行動に目的や目標を感じるようになってきました。
- 将来こうなりたいから、今これを頑張る
- 試合に出たいから、バスケの練習を頑張る
- 飲食店で働きたいから、料理をしてみたい
というふうに、将来自分が経験できるワクワクを想像しながら「あれやりたい」「これやりたい」と言うようになりました。
前からバイタリティーと体力だけは満ち溢れていましたが、相変わらず常に前向きで明るいまめに、わたしも元気をもらっています。
発達障害が治らなくても幸せに生きられる?

発達障害は、治らないものだとお話してきました。
では、発達障害が治らなかったとしても、その子どもは幸せに生きられるのでしょうか?
もし「発達障害であるうちは幸せになれない」「健常児が手に入れられることでも、発達障害の子は叶わない」と思っている方がいたら、その誤解を解いていきましょう。
自己理解と周囲の理解が必要
発達障害の特性を、まずは本人と周囲が理解することが大切です。
日常生活のストレスを軽減できたり、より生きやすい環境を整えやすくなったりします。
そのために、幼少期は自分の強みや弱みを少しずつ把握しながら、合理的配慮を受けることを目指しましょう。
自分のことを深く理解しながら、自己肯定感を失わずに成長することで、学校や職場、家庭での困難を減らすことが期待できます。
自己理解と周囲の協力は、症状が治ること以上に、生活の質を高める重要な要素となるでしょう。
支援や工夫で自立生活が可能に
療育や学習支援、環境調整、心理的サポートなどを受けることで、発達障害の特性があっても社会で自立して生活することはじゅうぶんに可能です。
ときには仕事や趣味、友人関係で困難を感じる場面もあるでしょう。
しかし、支援を受けながら工夫することで、充実した生活を送れるケースは多くあるんです。
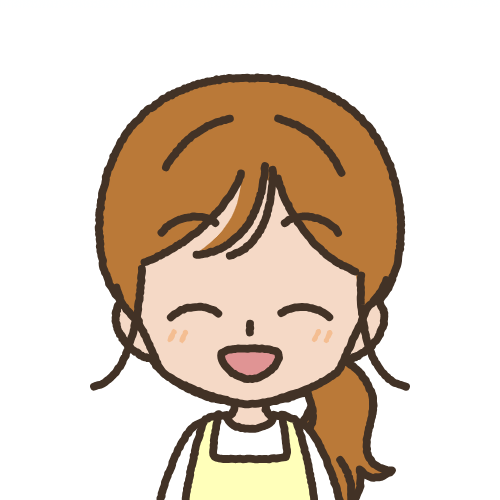
根性論や特訓ではなく、適切な支援を受けて生きやすさを学ぶことが大切なんだね!
強みを活かす生き方を見つけよう
発達障害の子どもや大人には、集中力や独自の発想、記憶力など特性を活かせる強みがあります。
特性に合わせた学習や仕事環境を整えることで、得意分野を伸ばしながら生活することができるでしょう。
特性が残っていても、強みを活かす生き方を見つけることで、十分に幸せな人生を送ることが可能です。
まとめ
発達障害は完治するものではありませんが、療育や学習支援、環境調整によって日常生活での困難を大きく軽減できます。
早期からの支援や家庭での工夫により、子どもも大人も社会で自立しやすくなるでしょう。
症状の改善と生活の質向上を目指して、本人がより幸せに生きられる環境を整えてあげたいですね!
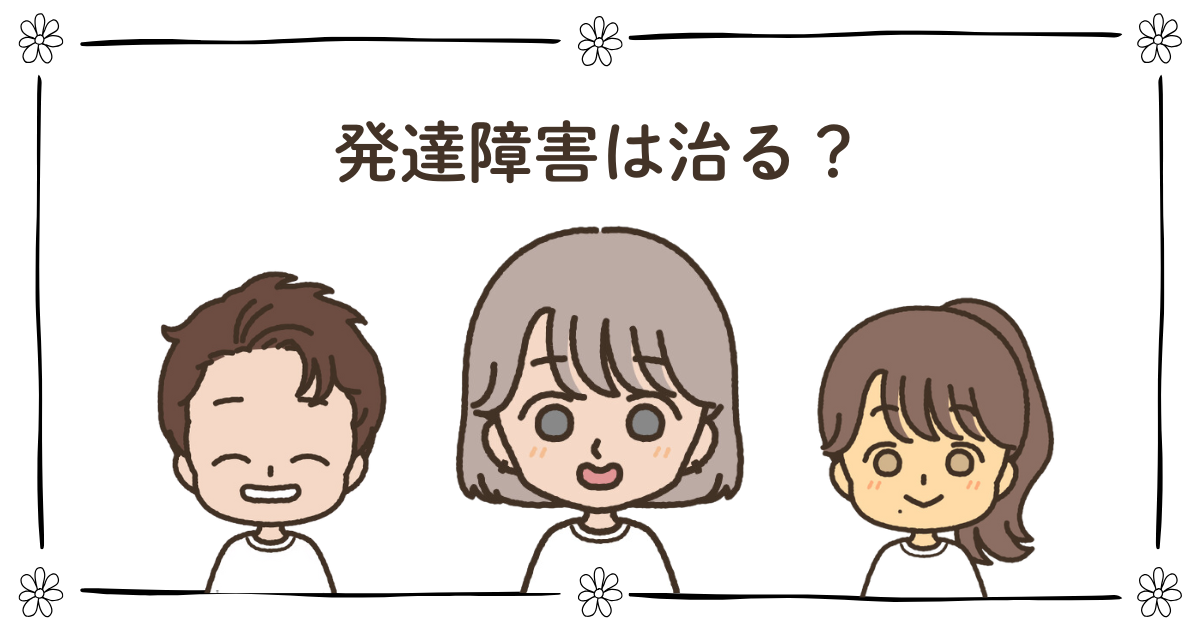


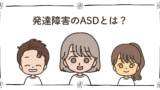

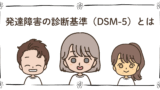
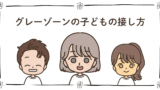

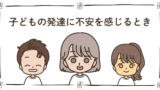



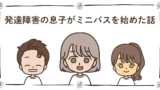
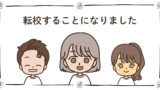
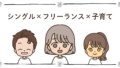
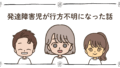
コメント