知的障害と発達障害の違いを知っていますか?
知的障害は古くから知られた言葉ですが、発達障害というのは近年使われるようになった言葉で、まだ完全に定着していないところがありますよね。
そのため「知的障害って発達障害のこと?」「発達障害って知的障害のこと?」と、混乱する人もいるかもしれません。
わが家は発達障害児を育てていますが、知的障害について学ぶにつれて
うちの子ってもしかして知的障害もあるのかな?
と思うことがあり、小児科にかかったことがあります。
そんなわが家の体験談を含め、知的障害と発達障害の違いについて解説したいと思います。

知的障害と発達障害の違い

知的障害と発達障害の違いを一言で説明すると、以下のようになります。

知的障害には知的機能(IQ)が関係していて、発達障害には関係しないのですね
分類の仕方が違う
知的障害と発達障害では、分類の仕方が異なります。
| 知的障害 | 発達障害 |
| 脳の全体的な発達の遅れが原因である 染色体異常などが原因である 4段階に分類される | 特定の脳機能に偏りが生じている 染色体異常などは関係しない 3種類に分類される |
知的障害は明確にIQで判定できますが、発達障害の診断は医師によって異なることがあります。
知的障害は脳の全体的な発達が遅れていますが、発達障害は部分的です。

発達障害は、たとえばASDはコミュニケーション面に課題があったり、LDは学習面で遅れがあったりします。
知的障害はそのように部分的ではなく、全体的に遅れのある障害です
そのため、知的障害と発達障害を統合してしまうと、それぞれが適切な支援を受けられないことがあるのです。
知的障害の4段階は、以下のように分類されます。
参考:厚生労働省
そして、発達障害の3種類は以下のように分類されます。
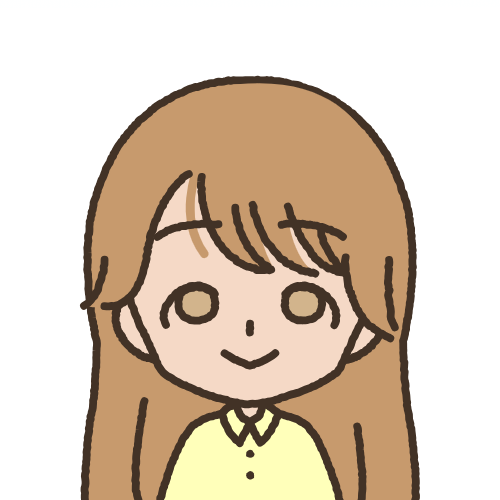
知的障害は「段階」で、発達障害は「種類」で分かれるんだね!
知的障害の中には種類がなく、軽度~最重度という段階で分けられます。
一方、発達障害はさらに細かく分類できるため、種類で分けられます。
発達障害に段階はなく、軽度でも重度でも「発達障害」とされ、同じ支援を受けることになります。

「軽度発達障害」と呼ばれる障害もありますが、現在は厚生労働省の指示により使われなくなりました
診断基準が違う
知的障害と発達障害は、診断基準が明確に違います。
| 知的障害 | 発達障害 |
| IQで明確に診断が可能 グレーゾーンの概念がない 診断基準は普遍的である | 明確な線引きができる数値がない グレーゾーンがある(医師によって違う) 診断基準が時代によって変わることがある |
もっとも分かりやすいのはIQです。
知的障害は、検査によってIQが70を下回ると診断されますが、発達障害の場合は明確な数値が設けられていないため、診断基準がいまだに曖昧です。

そのため、発達障害には「グレーゾーン」がありますが、知的障害にはありません
受けられる支援が違う
知的障害と発達障害では、受けられる支援が違います。
| 知的障害 | 発達障害 |
| 「療育手帳」の交付対象である 生活支援や介護サービスなど 福祉的な支援が充実している 作業所やグループホームの利用など 知的障害に特化した支援がある 精神科以外の診療も医療費助成がある (自治体による) | 「精神障害者保健福祉手帳」の交付対象である 生活介護などの支援は受けにくい 発達障害に特化した就労移行支援や 職業訓練が受けられる 精神科の通院費が1割負担になる |
医療費助成があったり、税金の減免や公共交通機関の割引サービスなどは共通しています。
しかし、知的障害は日常生活や社会生活において全体的な遅れや困難さが認められるため、福祉サービスが特に充実しています。
一方、発達障害の場合は発達障害の特性に特化した就労支援を受けて、就職先のあっせんや訓練が行われることがあります。
知的障害と発達障害を併存している場合、より福祉サービスの手厚い「療育手帳」を取得することが推奨されています
特性が違う
知的障害と発達障害は、主な特性が違います。
| 知的障害 | 発達障害 |
| 特定の分野ではなく 全般的な知的発達に遅れがある | 発達障害の種類によって 遅れがみられる点が異なる (ASDはコミュニケーション面、 LDは学習面など) |
知的障害はIQで明確に診断されるため、全体的な脳の発達が遅れているのが特徴。
発達障害は、種類によって遅れている部分が異なり、遅れていない部分では困りごとを感じないケースもあります。

たとえば発達障害のASDだと、コミュニケーション面で困難さがあってもIQは高い、というケースもありますよ(歌手の米津玄師さんがそうですね!)
要因が違う
知的障害と発達障害は、要因が違います。
| 知的障害 | 発達障害 |
| 先天的要因 出生時の低酸素や循環障害・感染など 出生後の頭部の外傷や 脳炎・脳症・髄膜炎など | 先天的要因のみ |
知的障害にはさまざまな要因が考えられますが、発達障害は先天性(生まれつき)のみ。
しかし、なぜ生まれつき脳機能に障害をもっているのかは、解明されていないそうです。
知的障害と発達障害の共通点

知的障害と発達障害は明確に異なるものですが、共通点もあります。
分けて考えられていますが、実際には知的障害と発達障害が併存している人もいたり、特性の中で共通しているものも。
これが、2つの違いをややこしくしてしまう原因となっているのですね。
知的障害と発達障害は別物だということを前提に、ここからは共通点について解説します。
同じ「神経発達症」の仲間である
知的障害と発達障害は、同じグループの階層下にある障害の種類です。
神経発達症
├─ 自閉スペクトラム症(ASD)
├─ 注意欠如・多動症(ADHD)
├─ 限局性学習障害(LD)
├─ 発達性協調運動障害(DCD)
├─ チック症 など
├─ 知的発達症(知的障害)
青マーカーの障害は主に「発達障害」とされるもので、黄色マーカーが「知的障害」です。
同じ「神経発達症」というグループにいますが、種類が違うものなんですね。
しかし同じグループに属していますので、中には同じ、もしくは似たような特性を持っていることがあります。
日常生活や社会生活への適応が難しい
知的障害と発達障害は、ともに日常生活や社会生活への適応が難しいという共通点があります。
診断基準や要因についての違いはありますが、ともに定型発達の子どもと比べると、社会の中で生きづらさを感じることがあるでしょう。

知的障害・発達障害をもつ本人もそうですが、ご家族にとっても生きづらさ、居心地の悪さがありますよね
併存性が高い
知的障害と発達障害は、お互いに併存する可能性が高くあります。
たとえば知的障害のある人は、発達障害を併存していることがあります。
同じように、発達障害の人が知的障害を併存していることもあります。
しかし、LD(学習障害)は知的障害を伴わない発達障害のため例外です
ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意多動欠如症)においては、知的障害を併発したりしなかったりします。

まめはASD強めのADHD、そして知的障害も併存しています
わが家の体験談

知的障害と発達障害の違いについて、わが家の体験談を共有してみたいと思います。
実はわたしもつい数年前までは、知的障害と発達障害の違いをよく理解していませんでした。
わたしが子どもの頃に学校にいた「知的障害の子」といえば、重度のイメージがありました。
今思えば、軽度の知的障害の子もいたのかもしれません。
しかしコミュニケーションがとれていたため、わたしが「この子は知的障害なんだ」と認識していなかった可能性があります。

子どもながらに、知的障害のお友達は強烈な印象があり、重度の子だけが記憶に残っているのかも
そのため、わが家のまめが発達障害だと分かったときにも、知的障害という考えは浮かびもしませんでした。
重度でコミュニケーションに困難があるというイメージがついていたので、まめはそうではないだろうと思っていたんですね。
しかし成長とともに、そしてわたしが知的障害について勉強するとともに、
もしかしてまめって知的障害がある…?
と考えるようになったんです。
そんなわが家の体験談についてお話してみたいと思います。
【0歳】発達障害の予感を感じる
わたしがまめに対し「発達の遅れがあるような気がする…」と思ったのは、なんとまだ首もすわらない生後2~3ヶ月のとき。
完全なる母親の勘でした。
根拠もないし、なぜそう思ったのかと聞かれても、いまだにわかりません。笑
ただなんとなく、そう思いました。
それが、まめの発達障害に気付いた最初の瞬間です。
【4歳】発達グレーが発覚
乳幼児期は、何も指摘されずにすくすく育ったまめ。
わたしはずっと発達に不安を感じながらも、たくさんの人やお友達と交流させながら育て、3歳のときに幼稚園に入園しました。
3歳で、幼稚園の先生から発達検査をすすめられ、4歳で検査を受けることになりました。
そこでは「発達の遅れはみられるが、発達障害とはいえない」という結果が出ました。
発達障害の傾向がありながらも診断基準は満たさない、いわゆる「発達グレー」であることが発覚します。
【6歳】発達障害の傾向が強まる
まめが幼稚園に通っていた3年間では、ASD(自閉スペクトラム症)の傾向が強く出ていました。
しかし、発達検査を受けても診断は下りず、グレーという結果に。
そして6歳で小学校に入学すると、ASDに加えてADHDの特性が出現し始めました。

新たな敵が現れたような感覚でした(笑)
それまでまめは、お友達との距離感を掴むのが難しかったり、そもそもお友達に興味を示さなかったりしました。
しかし、小学校に入学すると突然「友達と仲良くしたい」「仲間に入りたい」という思いが芽生えるようになったようです。
社会性が少しずつついてきたという喜びを感じる反面、幼稚園でお友達との関係構築をあまり経験してこられなかったので「お友達関係は小学生デビューか…」という不安も。
案の定、衝動性や多動性によってお友達に不快な思いをさせてしまったり、怪我をさせてしまったこともありました。
学習面の遅れは思ったより目立たず、先生の話を聞いていない割には(笑)頑張ってお勉強にはついていっていました。
そして、3年生になった頃からまた少しずつ、変化がみられるようになります。
【8歳】知的障害を疑い始める
「まめに知的障害があるのではないか」と疑い始めたのは、3年生になってからでした。
3年生は、小学校中学年に差し掛かる大きな成長のとき。
1~2年生で許されていたことも徐々に通用しなくなり、先生も1人ひとりの生徒を気にかけなくなります。
たとえば1~2年生では、体育の前の休み時間に着替えるよう指示がありました。
しかし3年生になると「体育の時間までだったらいつ着替えても良い」という柔軟なルールに。

朝のうちに着替える子や直前に着替える子などさまざまでしたが、まめは「いつ着替えるべきか」見通しが立てられないため、いつも遅れてしまっていました…
そして、学習面でも当然レベルが上がっていきます。
「生活科」が「理科」になって、専門的な用語を学ぶようになったり、割り算が始まったり、国語の文章題はさらに難解になっていきました。
そんな小学校中学年デビューを果たしたまめを見ていると、
これって本当に発達障害なのかな?知的障害じゃない?
という疑念が強まっていきました。
そして、小児科の発達外来を受診したという経緯になります。

発達障害児を育てて10年目。ここまでくると、診断名がどうこうというよりは「正しい状態を知ってかかわり方を勉強したい」という思いでいっぱいです
まとめ
知的障害と発達障害の違いや共通点について、解説しました。
明確な違いがありながらも、共通する点もあり、非常にややこしい2種類ですよね。
どちらも診断するのは小児科などの専門機関なので、子どもの状態を見て推測するよりは、適切な窓口に相談するのが最善だと思います。
「疑わしいからまずは様子を見よう」と先延ばしにしていると、つらい思いをするのは親御さんとお子さん本人です。
「発達障害かな」「知的障害かな」と思ったら、まずは自治体の窓口や小児科に相談したり、発達検査を受けたりして、適切なサポートを受けることをおすすめします。
よく読まれている記事
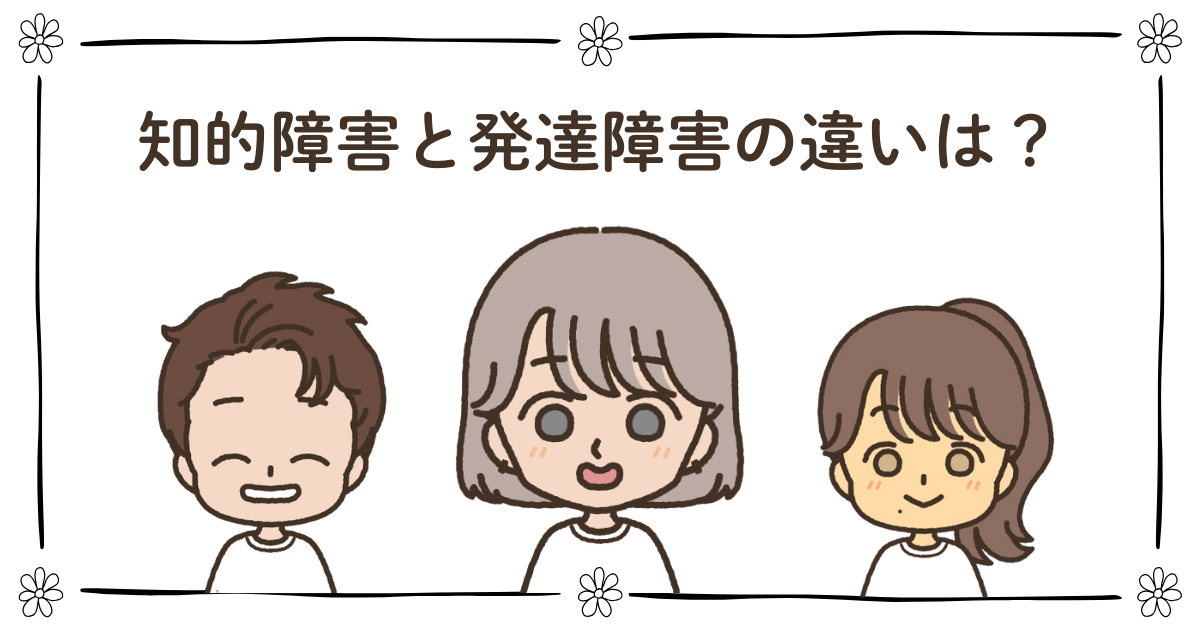
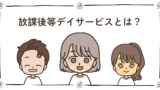


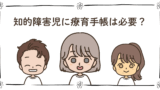

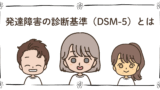

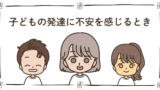
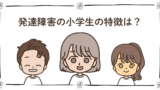


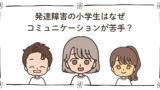
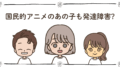


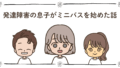
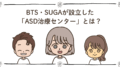


コメント