「ママ友と話が合わない…」
「なんだか避けられている気がする…」
発達障害のある子どもを育てていると、ふとした瞬間にママ友との距離を感じたり、孤立してしまったような気持ちになることがありませんか?
わたし自身も、他のママたちの会話についていけなかったり、無言の視線に傷ついたりして「居場所がない」と感じたことが何度もありました。
この記事では、ママ友関係で孤立を感じたわたしの体験と、その中で少しずつ心が軽くなった考え方をシェアしたいと思います。
今、同じような思いを抱えている方が「ひとりじゃない」と感じられればうれしく思います。

発達障害児ママはなぜ孤立しやすい?

発達障害のある子どもを育てていると、ママ友との会話や関係づくりが難しくなることがあります。
「避けられてる気がする」「話が合わない」「距離を感じる」
そんな違和感の積み重ねが、孤立感を強めてしまうのだと思います。
発達障害児ママが孤立しやすいのは、主に以下の理由があります。
発達障害児を育てていると、そうでない子どもをもつ親御さんとは根本的な「悩み」「生活リズム」「親子関係」が異なる場合があります。
ママ友関係というのは、どうしても似た境遇のママや、子ども同士が仲良くしているママがくっつきやすい傾向にありますよね。
そのため、発達障害児を育てるママは輪に入れないことがあったり、最悪の場合悪口を言われたりのけ者にされたりすることもあるようです。
発達障害児ママが孤立しやすい理由を、詳しく掘り下げてみましょう。
子どもの特性に理解が得られにくい
発達障害をもつ子どもには、少なからず発達特性があります。
軽度・重度という違いはありますが、発達特性はときに周囲の人を困惑させるものでもあります。
他の子にちょっかいを出してしまう、じっとしていられないなど、対人関係の問題も出てくるでしょうし、言葉や運動面の発達が遅く浮いてしまうこともあるかもしれません。

昨今は多様性の時代ですから、発達特性があっても受け入れてもらえる機会が増え、生きやすくなっているとは思います。
しかし、社会がそのように流れていたとしても、狭いママ友関係や幼稚園、学校などのコミュニティの中では、周囲の理解が得られないこともまだまだあります。

正直、発達障害の子どもをもつ人でなければ分からないこともあると思う。
だからこそ、健常児を育てるママさんたちの目が冷ややかだと感じることがあります(もちろん全員ではありません)
発達特性でお友達に不快な思いをさせてしまったり、迷惑をかけてしまったりすれば、当然親御さんは謝罪をします。
しかし、謝罪をしたり気を遣ったりするだけでは距離が埋まらないのが、ママ友関係の難しいところ。
発達特性を怪奇の目でみられたり、避けられたりすることが、発達障害児ママが孤立する要因となることがあります。
話題が合わない
発達障害児を育てていると、子育ての悩みやフェーズがまったく違うことがよくあります。
たとえば、幼児ママと中学生ママでは話題も悩みも全然違いますよね。
発達障害児を育てていると、まさに全然違う年齢のママ友の中にいるような気になることがあるんです。
「どこの習い事通ってる?」
「国語のテストは満点なんだけど算数が苦手で…」
「学級長に選ばれたけど、ちゃんとできるか心配」
健常児を育てるママさんの中には、こんな話題で盛り上がる人がいるかもしれません。
しかし、発達障害児を育てているとそもそもその悩みのフェーズに到達していないことがあるんです。

習いごとどころか療育でいっぱいいっぱいだし、勉強も全般的に苦手。何かに選ばれることもなくて、なんだかその場にいるのが虚しくなって…
子どもは子どもで精いっぱい頑張っているので、責める気は一切ありませんが、ママ友というコミュニティにいると虚無感を感じてしまうことが多々ありました。
距離を置かれる
発達障害児を育てていると、こちらから離れる前にママ友から距離を置かれることがあります。
もちろんそのようなママさんが多いわけではありませんが、中には発達特性を快く思わず、子どもと関わってほしくないと感じる人もいるでしょう。

世の中には口の悪い子や暴力的な子など、発達障害に関係なくいろんな子がいます。
でも「発達障害」がまだあまり知られていないがゆえ、風変わりな目でみられることがあります
「発達障害があって変わった子」とネガティブな印象を抱かれると、距離を置かれることがあります。
わたしもそれで落ち込んだことがありました。
でも、まめはお友達との距離感の掴み方がまだわからなかっただけで、一生懸命お友達とかかわろうとしていました。
いつもニコニコしていて、避けられてもお友達に話しかけたり遊ぼうとしたりするのが伝わってきました。
そんなまめを見ていると、親子で距離を置かれるのは悲しいことでしたが、考えても仕方ないこと。

距離を置かれたなら、そこから頑張って距離を詰め直す必要もありません。
一定の距離感を保ってあいさつ程度に留めたり、深入りするのをやめたりしました。

子ども同士は幼稚園で遊んだり話したりしていたそうなので、ママ同士に距離があっても、子ども社会は子ども社会で別に機能していました
健常児を育てるママさんたちと距離が空くたびに、わたしは
ママ友関係にこだわるのはやめよう
と思うことができました。
それまでは「自分が円滑なママ友関係を築いてこそ、子どもたちの友達関係もスムーズになる」と思っていました。
でも、幼稚園や学校に通っているのであれば、その限りではありません。
ママ友がいなくても子どもは勝手に友達を作ってきますし、幼稚園や学校でのトラブルは先生が仲裁してくれます。
「ママ友がいなければ子どもにも友達ができない」というのは、考えすぎなのだということに気づけました。
悩みを共有しにくい
発達障害児育児の悩みは、想像以上に深いことも多く、気軽に話せる内容ではありません。
「どうせ分かってもらえない」と心を閉ざしてしまうママも少なくないでしょう。
それでも、心置きなく悩みを話せるママ友に出会えれば幸せですが、多くの場合悩みのフェーズや土俵が違うことで、なかなか共有できないようです。

わたしは当初、発達障害児育児の悩みを隠さずママ友に打ち明けていました。
でも、反応に困る相手の表情を見るたび虚しくなってしまって…
発達障害児育児をしていない人に話すべきではないんだ、と思った記憶。
そうはいっても、発達障害児育児の悩みをすべて抱え込んでいては、親御さんがパンクしてしまいます。
そんなとき、発達障害児育児をする上で利用できるサービスや支援制度を活用してみてください。

たとえば療育や放課後等デイサービスなどの支援制度を使うことで、親子そろって支援を受けることができます。

まめが幼稚園児の頃通っていた療育では、毎回先生との面談や悩み共有タイムをもうけてくれました。
「いつでも先生に話せる」と思うだけで、毎日の育児が楽に感じられたのを覚えています
ママ友との関係で孤立してしまったり、悩みを共有しづらいと思ったりすることは、いわば普通のことでしょう。
だって、発達障害児の育児とそうでない子どもの育児は全然違うから。
「孤立してるかも」と感じた瞬間

孤立はある日突然始まるのではなく、小さなできごとの積み重ねで感じるものです。
特に発達障害児を育てていると、毎日幼稚園や学校でどんなことが起きているのか、親御さんの目が届かないことが増えてきます。
先生に聞けばある程度のできごとは知ることができますが、先生が見ていない場所で小さなトラブルが起きているケースもあるでしょう。

発達特性によって子どもがお友達に不快な思いをさせてしまい、それが親御さんに伝わったり、発達特性の強い行動がほかの親御さんの目に触れ「変わった子だ」と思われたり…
小さなできごとが積み重なって「なんかママ友から孤立しているような気がする」と感じるタイミングがありました。
まめが幼稚園児の頃、わたしが個人的に感じた孤立エピソードをご紹介します。
この頃はしんどかったこともありますが、結果ママ友と群れる関係性を持たずに済んだので、いつも心は平和だったと思います。

なので、最終的にはハッピーエンドになると知った状態で読んでみてください!笑
グループLINEに入れてもらえない
周囲のママたちが楽しそうにやり取りしているのに、わたしだけLINEに入れてもらえていなかったことがあります。
「もしかして避けられてる…?」という不安が胸を締めつけるできごとですよね。
正直、まめが年少の頃は
ママ友たくさん作るぞ♡
気軽に遊べるママ友ができるといいな~!
なんて、憧れのママ友たちとのキラキラライフ(笑)を夢見ていました。

でも、子どもの発達特性が強くなればなるほど、周囲の目線が気になるように。
そんな矢先、グループLINEに入れてもらえていないことが発覚しました。

でも、このときにはすでに分かっていました。
あぁそうだよな、うちの子がいたら行事がスムーズに進まないもんね…
誘われないのも当然だよね…と。
なので、ショックで落ち込むようなことはありませんでしたが、子どもの発達特性が理由で交友関係がどんどん狭まっていくことは、なんだか「良いことではない」気がしていました。
だって、発達障害があるまめだってお友達と遊ぶ機会を持って良いはずだし、発達障害だからってずっとこうやってのけ者にされ続けるのは理不尽だと思ったからです。
でも、わたしは発達障害をもたない娘のナツがいます。
もしナツのお友達の中に、ナツが傷つくようなことをする子がいたら…?

発達障害があってもなくても、そういう子とかかわるのは避けるだろう、と思いました
ほかのママさんたちも、きっと同じ気持ちだったんだと思います。
発達障害があって、みんなで一緒にする行事にちゃんと参加できない子は誘いたくない。
注意しても伝わらないから、できればかかわりたくない。
確かにまめも、お友達と遊ぶ機会を持ってもよいはずですが、きっと場所が違うんだ。
そう思って、グループLINEに入れてもらえなくなったことをあきらめました。

結果、まめは療育に通うようになりましたが、療育のママ友の間ではそのような思いをすることがありませんでした。
発達特性のことも包み隠さず話せたし、日ごろの困りごとを笑いに変えることもできました。
子ども同士も楽しく遊ばせてもらえて、まめにとっても刺激的な時間を過ごせました。

グループLINEに入れてもらえないという環境は、きっとわたしたちがいるべき場所ではないんだ。
そう思えたことが、前に進むきっかけになりました
行事のときにぽつんと1人
幼稚園の行事でママたちが集まって談笑している中、会話に入れないことがありました。
わたしの性格上、誰とでも気さくに話せるタイプなので、会話に入ろうと思えばいくらでも入れました。
でも、なんか遠慮してしまうんです。
わたしが会話にお邪魔したら気を遣わせるかな。
話題も悩みも合わないわたしが、ママ友の輪の中に入るのは場違いなのかな。
そんなふうに気にしてしまう自分もいて、結局1人でいるのが一番気楽だったりしました。

でも1人でいたからこそシャッターチャンスを逃さなかったし、無駄話して子どもを見ていなかった…というヘマはしませんでした!笑
小学校に入ると、授業参観でママ友が談笑したり固まって話をしたりすることは、ほとんどなくなりました。
小学生ママは働き始める人が増えるからか、授業参観でも保護者会でも、けっこう忙しそうにしている人が多いんですよね。
仕事を中抜けして来ていたり、きょうだいのクラスに移動しないといけなかったりで、幼稚園の頃ほど「ママ友の談笑」という場面はみられなくなりました。
わたしはそれを、まめが小学校に入学してから知ったので、
なぁんだ、ママ友と談笑できなくても気にしなくてよかったんだ
と、妙に安心することができたのでした。
子どもを悪く言われている雰囲気を感じ取る
子どもの発達特性でほかの子に不快な思いをさせていたり、迷惑をかけたりしていても、なかなか親のもとに情報が入ってこないことがあります。
大きなトラブルになって先生から連絡があれば別ですが、マイナートラブルの場合は学校で解決してくださるので、親に連絡が来ないこともよくあるんです。
しかし、トラブルがあった子どもは親に報告したり、友達同士で噂話をしたりします。
そして「風のうわさ」となって、わたしの耳に入ってきたこともありました。

実は、まめは1回学校でズボンを汚してしまったことがあるんです。
そして、それを見ていた子どもが親に言ったらしいんですね。
子どもが親に言うところまではよくある話なのですが、なんとその親御さんが、ほかの親御さんにそれを言いふらしていたんです。
それも、学年の半分くらいが入部しているサッカー部の親御さんに。
その親御さんほぼ全員に、まめの粗相の話が伝わってしまったんです。

普通、親がそんな噂広めますかね…
本当に信じられませんでした
そして、全然関係のない親御さんからわたしに「まめ君大変だったね、ズボン汚しちゃったんでしょ?」と言われ、わたしは唖然。
「誰から聞いたの?」とは聞けずに「大丈夫だよ、ありがとう」とやり過ごすのが精一杯でした。

その一件からさらに、ほかの保護者から距離を置かれているように感じ始めました。
もちろん、気のせいかもしれません。
しかし、子どもの粗相を言いふらすようなママさんがいたということで、人間不信のようになってしまいました。
もう時間が経っているのでその話は忘れ去られたと思います(そう願っています)が、関わるべきではないママさんに目星がついたのは、大きな収穫でした。
孤立したとき考えてよかった3つのこと

孤立はつらい。
でも、その中で「心を守る考え方」に出会えたこともありました。
子育てをする中で、ママ友というのは心強い存在ですよね。
悩みを共有しあえたり、協力して子育てができたり、つかの間の楽しい時間を一緒に過ごせたりします。
孤独な育児だからこそ「ママ友がほしい」「孤立したくない」と思う人もいるかもしれません。
そんな葛藤と戦っている方に、わたしが常に頭に入れていてよかったと思う3つの考えをシェアしたいと思います。
「ママ友がいなくても子育てはできる」
子どもが生まれたとき、憧れのママ友関係を充実させるため張り切っていたわたし。
しかし、周囲とは育児の悩みも基準も違うのが「発達障害児育児」でした。
まめが4歳(年中)になる頃には、
ママ友、いらないかも
と割り切っている自分がいました。
負け惜しみのように聞こえるかもしれませんが「ママ友がいなくても育児ができる」と思えたことで、わたしにはメリットがたくさんありました。
まず、ママ友との雑談やランチ会に時間を割くことがなくなったので、仕事が充実しました。
そして、まめとお友達の関係性について心配なことがあれば、ママ友の目を気にするのではなく先生に直接相談できるようになりました。

先生は子どもを見るのが仕事なので、ママ友のように「嫌われているかも」と気にすることなく、安心して悩みを話すことができました
「居場所はいくらでもある」
子育てをしていて、夫や実家に頼れないとなると、ママ友にすがりたくなる気持ちは分かります。
物理的に助けてもらうのではなく、ママ友という存在自体が心強かったり、ママ友と過ごす時間で元気になれたりすることもありますよね。
しかし、そこで孤立してしまうのなら、無理にその環境に居続ける必要はないと個人的に思います。
「場違いかもしれない」と思いながらママ友の輪に居続けようとしても、自分の心がすり減っていくだけだからです。
発達障害児を育てていて、ママ友と話が合わなかったり、避けられているように感じたりするなら、それはあなたにはどうにもできないことです。
発達障害児を育てるあなたには、別の居場所がきっとあります。

たとえばSNSで発達障害児を育てるママさんとつながって、やりとりをするだけで心が軽くなるかもしれません。
療育を活用し、同じ療育に通う保護者の方と話が合うかもしれません。

多くの療育ではレッスン中の様子をマジックミラーやモニターで見られるようになっていて、専用の待合室もあるので、そこで保護者同士が談笑することもありますよ
療育では子どもだけでなく親御さんへの支援もしてくれるので、相談しやすい先生がいれば話を聞いてもらうのも良いでしょう。
親御さんの悩みに合わせて、ペアレントトレーニングや講習を紹介してくれたり、子どもの発達に適したアイテムやサービスを教えてくれたりしますよ。
なんだかんだ言って、発達障害児を育てる親御さんにとっては「一般的なママ友」よりも「専門機関で出会う人々」のほうが良い影響があるものなのかもしれません。

個人的には、幼稚園のママ友って噂話とか多かったんですが、療育関係で知り合う人にはそういうタイプがいなかったんです。
子どものことをじっくり話せて、有益な情報交換もできて、わたしにとっては最高の居場所でしたよ
ママ友から孤立してしまっても、ママ友の世界だけがあなたのすべてだと思わないでくださいね。
「家族が味方ならそれでいい」
結局、自分にとっても子どもにとっても「家族」が味方でいてくれればそれが一番ですよね。
わたしは個人的に「健康面」を気にしがちなタイプで、少しの体調不良で過剰に心配してしまうので(笑)子どもが今日も健康だったなら全てOK!と思うことにしています。

今日も色々あったけど、子どもは元気だった。
それだけで今日はとても良い日だった!
1日の最後にそう思うだけで、その日あった不快なできごとも悩みも少し片付くような気がします。
極端な話ですが、ママ友の輪に入れてもらえたりランチに誘ってもらったりするより、子どもが元気なほうが幸せじゃないですか?
結局、どれだけママ友つながりが多いか、絆が強いかよりも
子どもが常に元気で家族が味方でいること
に勝ることってないと思うんです。
現に、ママ友から孤立した経験のあるわたしでも、今思えば小さな悩みだったと思います。
今子どもが元気で毎日笑っている現実のほうがよっぽど嬉しいですし、それが守れるなら「仲間はずれだろうが何だろうが構わない」と思うこともできます。
ママ友関係で悩むことがあっても、ママ友は人生のうちほんの一部でしか関わらない人たちだと割り切って、家族を一番大切にしましょう!
孤立は悪ではなく「見直しのタイミング」かもしれません。
まとめ|孤立したって自分らしくいよう!
発達障害児ママは、ママ友関係で孤立しやすい現実があります。
でも、無理をして誰かに合わせる必要はありません。
あなたを理解してくれる人は必ずどこかにいて、今はまだその場所を探している最中なのでしょう。
子どもにとって一番の安心は、「自分らしく笑えるママ」の存在ですよね。
さまざまな場所や環境に足を運んでみたり、支援制度を利用してみたりして、自分の居場所を探してみてください。

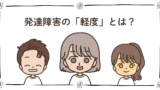


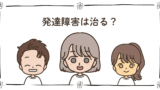
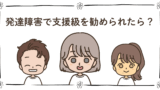


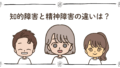
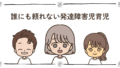
コメント