発達障害児を育てていると「勉強できない」と悩むことがあるのではないでしょうか。
この記事では、発達障害を抱える小学生を育てるわが家から、勉強に関する体験記を綴っていきたいと思います。
わが家で実際に利用したサービスや支援制度、また小児科でいただいたアドバイスなども細かく記しています。
同じく発達障害をもち、勉強ができないというお悩みを抱える小学生を育てるご家庭にとって、お役に立てば幸いに思います。

発達障害児が勉強できないのはどんなとき?

発達障害のある子どもが小学生になると、集団授業や宿題などで「勉強ができない」と感じる場面が増えてきませんか?
特にシングルマザーの場合、日々の家事や仕事に追われがち。
子どもの勉強を十分に見てあげられず、不安や罪悪感を抱くこともあるでしょう。
わが家も例に漏れず、発達障害をもつ小学生を育てるシングルマザー家庭。
発達障害をもつ息子・まめが勉強の壁にぶつかった状況について、シェアしてみたいと思います。
学校の授業についていけないとき
発達障害があると、学校の授業で以下の問題が生じることがあります。
そもそも勉強はつまらないと思う人が多いでしょうし、精神的にも未発達な年齢ですから、ある程度は仕方ないと思えても、親御さんとしては心配になりますよね。
わが家では幼少期から学習面にはそれほど力を入れておらず、遊びや趣味、また非認知能力を伸ばす活動に重きを置いてきました。
そのため、学習面でそれほど優れていなくても気にしていなかったのですが、小学校3年生くらいから暗雲が立ち込めるようになりました。

小学校低学年の学習は難易度も低く、また本人がイメージしやすい内容や規模だったりします。
それが、小学校中学年にあたる3年生くらいから、徐々に規模が大きくなっていきました。

たとえば、それまでは「りんごが3個、みかんが5個」など実際に数えられる問題だったのが、10万、100万と目に見えない数になると、わけがわからなくなるようです(それは納得…
特にまめはASD(自閉スペクトラム症)の傾向があり、学習の際には「具体性のあるもの」が提示されるかどうかが、理解のポイントになります。
たとえば社会の授業でいうと、自分が住む町の歴史や町名の由来など、自分の興味や生活に関与した内容は、比較的すぐに学習することができました。
しかし、その範囲が「自分の住む町」から「日本全国」に広がると、行ったことのない場所や見知らぬ土地の話なので、一気に定着率が落ちるんです。
それが顕著に感じられたのが、小学校3年生のときでした。
3年生になると、上記のように学習レベルが一気に上がるうえに、先生の手厚いフォローもなくなっていきます。

学校は、クラス全体が大体同じペースで進むことを重視しているので、個々の能力向上にはそこまで協力できないそうです
自分が子どもの頃は、多少授業内容がわからなくても先生が休み時間に教えてくれたり、少し多めに宿題を出してもらいキャッチアップしたりして、何とかなってきました。
でも、同じことが発達障害児に適用するわけではないのだ…と実感しました。
家庭学習がうまくいかないとき
発達障害児が勉強できないと感じるのは、授業だけではありません。
そう、小学生には宿題という難関がありますね。
授業はクラスについていかなければいけないけれど、宿題は親御さんが見るだけなので、一見「ハードルが低いのでは?」と思うかもしれません。
しかし、わが家では宿題こそ1日の中でもっともギスギスする時間でした。

小4になった現在はだいぶマシになりましたが…本当、宿題の時間が親子にとって憂鬱でした
まめはASD傾向があるので、学校や宿題よりも「自分のやりたいこと」が最優先というタイプ。
そのため、一般的に子どもが思うであろう「宿題はやりたくないけど、やらなきゃいけないからやる」という考えが、発達障害児には通用しないのです。

そんなのわがままだ!障害を言い訳にしている!という意見もあると思いますが…
そんなわけで、まめは帰宅後宿題に手をつけるまでの時間が果てしなく長かったです。

やっと鉛筆を握ってくれたと思ったらお絵描きをしていたり、宿題に取り掛かる直前に「やっぱりおやつ先に食べてもいい?」と机から離れてしまったり…
(ちなみに「おやつ先に食べてもいい?」とは言いますが、じゃあそのあと宿題をやるかといったら、やりません笑)
宿題は、家庭学習を少しずつ習慣づけるのに重要な取り組みであり、学校の復習を兼ねるので定着率アップも期待できます。
でも、発達障害児にとってはそれ以前の問題。
学習習慣とか定着率などという前に、まず「宿題をやる」という意識を持ってもらうことが、すでに高い壁でした。
\ 大好きなバスケは毎日練習するんですけどね…/
「発達障害=勉強できない」ではない

発達障害をもっていると、勉強できないという悩みを抱えやすいのが現実です。
しかし、発達障害児はそれぞれ異なる認知特性を持っており、苦手なことや得意なこともさまざまなんです。
そのため発達障害児が勉強できないというのは、イコール怠けている、努力不足というわけではないということを覚えておきましょう。
発達障害にはさまざまな種類がありますが、ここではASD・ADHD・LDという3つの種類について見ていきましょう。
ADHD(注意欠如多動症)の場合
発達障害の中でADHD(注意欠如多動症)を持っている場合、以下の面で困りごとが多いとされます。
これらは本人の努力不足ではなく、脳の特性によるものです。
ADHDは注意が散漫しがちで、周囲のさまざまな刺激に集中力が妨げられがち。
そのため、学習の理解というよりも「45分の授業をちゃんと受ける」ことが難しいケースがあります。

まめも小学校に入学したての頃は、授業中に立ち歩いたりお友達の邪魔をしたりすることがありました…
授業に集中できなかったり、先生の話を聞いていなかったりすることで、徐々についていけなくなる可能性があります。
支援級で個別配慮してもらったり、放課後等デイサービスで細かくフォローアップしてもらったりすることで、学校の授業に集中できないデメリットを少しでも解消することができるかもしれません。

集中できないだけで学習面の理解力があるなら、家庭学習や親御さんのフォローでうまくいく可能性も…!
ASD(自閉スペクトラム症)の場合
発達障害の中でASD(自閉スペクトラム症)を持っている場合、以下の面で困りごとが多いとされます。

まめはASDの傾向が強いので、とにかく「興味のないことはやらない」というのが大きな壁でした!!!
ASDには、曖昧な指示や抽象的な言葉(「あれ」や「さっきの」など)を理解するのが難しい傾向があります。
まめの場合そこを特訓しようにも、そもそも勉強に興味がないことが致命的でした。
ASDにとって最優先事項は「自分の好きなこと」。
勉強に興味がなければ、勉強に関して努力してくれることを期待するのも難しいのです…!
わが家ではこの困りごとがもっとも深刻でしたが、低学年の間は学習レベルも高くないので、わたしもそこまで問題視していませんでした。
しかし、高学年になって「低学年の学習の定着率が低い」と指摘されてしまったことで、学習面に特化した放課後等デイサービスを利用することにしました。
LD(学習障害)の場合
読み・書き・計算など、特定の学習分野だけに強い困難がある場合は、LDの可能性もあります。
適切な支援があれば、学習を進めることができる発達障害といわれています。

勉強ができないことも、今では「発達障害」と呼ぶんだね…!
昔から一定数、特定の学習分野に苦手意識を感じる子どもはいたそうです。
しかし、まだ「発達障害」という名前が普及していない時代には「怠けている」「勉強嫌い」「知恵遅れ」などといわれ、つらい思いをした子もいたことでしょう。
現在はLDという名前で認知され、その子に合った方法でフォローアップする支援方法も実践されています。

LDもまだあまり知られていない名称ですが、学習面にだけ著しい遅れを感じる場合には、専門機関に相談してみるといいかも
シングルマザーとして直面した学習の壁

仕事・家事・育児すべてを一人で抱えていると、どうしても勉強を見る時間は限られてしまいます。
「毎日宿題を見てあげたいけど、身体が足りない…」
そんな自責の念を抱えてしまう方も多いでしょう。
わが家も例に漏れず、発達障害児を育てるシングルマザー家庭。
しんどかったのは、主に以下の壁を感じたときでした。
習いごとはほぼすべて子どもたちが希望するものだったので、本人に辞める意思がない限り続けようと思っていました。
その結果、土日も合わせてほぼ毎日何かしらの習いごとがある状態に…。

特にバスケは週4~5日あるから忙しいよ!

可能なものはオンラインにしたり工夫を凝らしているけど、それでもバッタバタです…
学習面でどうにかしなければいけない問題がある中で、習いごとを優先するのが間違っているというのは、百も承知でした。
本当であれば「習いごとはひとまず辞めて、今は勉強のほうを何とかしよう」と言いたかった。
でも「本当にそれでいいのか?」と自問自答し、踏みとどまっていました。

もちろん勉強は大事だし、発達障害があればなおさら手厚いフォローは必須。
でもバスケやプログラミングなど、本人が情熱を燃やしていることを辞めさせるのは、何か違うと思ったんです
その結果、習いごとと学習面フォローを上手に調整しながら、なんとか頑張ってみることにしました。
習いごとの曜日を変えたり、週4~5日あるバスケは少し回数を減らしたり、都合の良い曜日に通えそうな放デイに変えたり…

ASDで「好きなこと」が最優先であるまめに、自由時間も与えられるよう、とにかく頭も身体もフルで働かせました。
その中で、わが家が実践して効果のあった方法をご紹介します。
わが家で効果を感じた学習方法

子どもの勉強の悩みに正面から向き合うのは、本当に大変なことです。
シングルマザーであればなおさら、時間も身体も足りません。
そんな中、わが家で効果を感じた発達障害児の学習方法をまとめてみました。

再現できそうなものがあれば、ぜひ試してみてください!
宿題の量を調整してもらう
学校と相談し、宿題の量を調整してもらうことができれば、そのように交渉することをおすすめします。
わが家ではまめが小3のときに、先生から
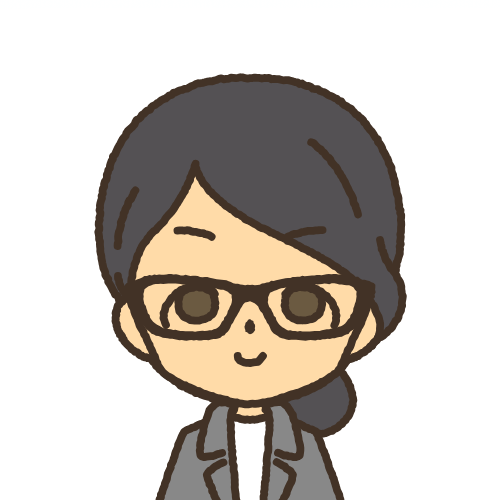
宿題がしんどそうなら、量を半分にしてみましょうか
と提案してもらい、ありがたくそのようにしてもらうことにしました。
今までやっていたページの半分に減ったことは、まめにとって大きな変化だったようで
「これしかやらなくていいの!?」と気持ちが楽になったようでした。
また、小4からは担任の先生の意向により、宿題の量が自由になりました。
「漢字ドリル」か「計算ドリル」のうちどちらか、もしくは両方を、好きな量だけ取り組むというスタイルです。

小4になると習いごとで忙しい子もいるので、それぞれの予定に合わせて柔軟に取り組めるようにするため、とのことでした
まめもバスケがある日は漢字を2つだけ復習したり、時間がある日は1ページドカン!とやったり、自分で調整しながら取り組んでいました。
発達障害の程度や特性にもよりますが、このように「自分で裁量を決められる」スタイルが合っている子もいて、わが家にとってはありがたい制度でした。

クラス30人が全員、同じ量の宿題を同じくらいの時間で終わらせられるわけではありません。
一般的な知能の子どもが30分ほどで終わらせられるような宿題でも、発達障害がある子は数時間かかる可能性もあります。
そうなったら、発達障害の子はクラスのレベルに合わせて数時間がんばらないといけないのでしょうか?
それでは、発達障害の子には自由時間がなくなりますし、学校でも家でもずっと机に向かっていることになるでしょう。
本人の負担になるどころか、そのような学習習慣がついても身にならないでしょう。
特にASD(自閉スペクトラム症)傾向のある子どもにとって、優先度が高いのは常に「好きなこと」です。

「好きなこと」ができないのに「やらなければいけないこと」だけをやるというのは、ASDの子どもにとって想像以上につらく、苦しい時間なのですね。
宿題の量を調整し、少しでも好きなことに割く時間を作ってあげることが、発達障害児の子どもの学習にとって大切なポイントです。
宿題のレベルを下げる
発達障害児の宿題においては、学校に相談し、現在習っている単元よりもレベルを下げたものを用意してもらうことも重要なポイントです。
発達障害児が勉強できないという壁にぶつかっている場合、今現在習っているところを一生懸命勉強しても意味がないことがあります。
理由は、それより前の学年の学習が定着していない可能性があるからです。
たとえば、1年生で習った内容が定着しないまま2年生になったところで、2年生の学習が理解できるようにはなりません。

1年生の足し算・引き算がわからなければ、2年生の九九なんてもっとわからないもんね…
そのため、今習っている単元を宿題に出すよりも、レベルを下げた内容の宿題を用意してもらうほうが効果的なことがあります。
内容は同じだけれど、1学年下のレベルに下げるというイメージです。

このあたりは親御さんが難しく考えなくても、学校に相談すれば先生たちが「学習指導要領」を把握しているので、主導してくださると思います
タブレット教材を活用する
わが家のまめは「書くこと」を異様に嫌うタイプで、宿題の内容が嫌だというより「鉛筆を持つことがもう嫌」という感じでした。
そのため、タブレット教材になるとけっこう進んでやってくれたんです。
学校の先生にはその旨を相談してあったので、宿題の代わりに学校支給のタブレットに入っている九九ゲームをしたり、漢字をなぞって遊ぶゲームをしたりすることも。
学校支給のタブレット以外に、自宅でタブレット教材を取り入れてみたり、学習アプリをインストールしたりしてみました。

アプリは無料のものから手軽に試せる価格帯のものがたくさんあるので、飽きずにいろいろ遊べてよかったです◎
学校の先生も「宿題は必ず書いて覚えなければいけないわけではない」として、本人の頭に入りやすい方法で学ぶのがいちばん効果的だ、と提案してくださいました。
わたしは個人的に書いて覚える派だったので、タブレット教材で補えるか不安でしたが、結局その子に合った方法でなければ定着するものもしないんだな、と学んだ出来事でした。
ご褒美を設定する
わが家のまめは当時、マイクラにハマっていました。
わが家ではもともとタブレットやテレビゲームで遊ぶ時間を制限していて「○○が終われば15分、△△をやれば15分」という感じで、15分ずつ与えていました。

〇〇と△△をまとめて終わらせれば、一気に30分できるという日もありました
こんなふうに「宿題が終わったらマイクラやっていいよ」というご褒美設定にすることで、まめは進んで宿題をやるようになりました。
さらに、ここまででご紹介してきた方法を組み合わせて…
このようにすれば、一気に子どもにとっての「宿題」というハードルが下がります。
まずはこのような方法で、うまくいくか様子を見てみても良いかもしれません。
発達障害児の勉強は支援機関や制度を利用しよう

学習の悩みは家庭だけで抱え込まず、支援機関の力を借りることも大切です。
特にわが家のようにシングルマザーだったり、パートナーの力を得にくいワンオペ家庭の場合は、親御さんだけでサポートしようとしても限界があるからです。
わが家でもすべての制度を利用したわけではないのですが、アドバイスいただいた方法や、実際に使っていた支援サービスなどをまとめてみたいと思います。
放課後等デイサービス
放課後等デイサービスでは、個別支援計画に基づいた学習支援を受けることができます。

発達障害児の学習面フォローは、個人的に放課後等デイサービスが一番良いと思います
それぞれのご家庭によって事情が違うので、あくまでわが家で感じた点として…
このようなメリットがあります。
わが家では、通っている小学校に支援級がないため、支援級に行く場合には転校を伴わなければなりません。
それなら送迎サービスを使って、放課後等デイサービスを利用してみようという結果に至りました。

すでに習いごとがあって忙しかったですが、送迎してもらえるし、何より助成金で安く学習フォローをしてもらえるところが嬉しかったです
放課後等デイサービスは月に利用できる日数が決まっていて、最高23日通うことができます。
わが家の場合、通う放課後等デイサービスの責任者の方と面談した際、最高日数を申請できる申請書の書き方を教えてもらえました。

書き方といっても裏技ではなく、要はその放デイが「月23日来ても良いですよ」といえば最高日数で申請できるそうです
MAXで通える受給者証が手に入れば、夏休みなどの長期休暇中もほぼ毎日放デイに通えるので、家庭としては大助かりでした。
放課後等デイサービスについては、こちらの記事でくわしくお話しています。
また、放課後等デイサービスに通うことに決めたわが家ですが、その後支援学級への転校も決定しました。
放課後等デイサービスは週1だったので、さすがにそれでは学習フォローが足りなかったのと、学校生活を充実させるためには転校が最善策だということで、決定しました。
\ 転校についてはこちら /
特別支援学級・通級
通っている学校に支援級や通級があれば、気軽に転籍することができます。
支援級だと完全に通常学級から離れて授業を受けることになりますが、通級であれば特定の教科や時間だけ教室を移動して授業を受けるかたちです。
まめの学校には、支援級も通級もありませんでした。
まめが小学校に入学した時点で、徒歩で通える範囲内に支援学級のある学校がなかったため、わが家では選ばなかった方法です。
しかし、まめが小3になったとき、ちょうど隣の小学校に支援学級が設置されました。
そして、まめはその学校にある支援学級に転籍(転校)することになりました。
支援級や通級には、それぞれメリットとデメリットがあります。
くわしくはこちらの記事でまとめていますので、参考にしてみてくださいね。
学校の先生や支援コーディネーターとの連携
担任の先生との情報共有や、支援コーディネーターによるアドバイスも有効です。
まめの小学校には、月に1回スクールカウンセラーの先生が来てくれるので、面談を予約して相談していました。

しかし、学校との共有に関しては限界があると感じました。
まめがお世話になっていた小児科の心理士の先生によると、学校は個人のスキルアップや学習において協力できる範囲が限られていることが多いそうです。

そりゃそうですよね、先生は1人で30人を見てるんですから…
さらに、小学校高学年になると先生のフォローはほぼなくなり、学習面における「報告」のみになることもあります。
学校での学習はもちろん学校で管轄しますが、授業についていくことができない場合には、学校から家庭へフォローをお願いすることもあるようです。
そのため、学習面でのフォローや強化を図る場合には、学校の先生だけでなく支援コーディネーターやスクールカウンセラーなど、専門家の力を借りることも必要だと感じました。

でも「支援コーディネーター」ってどこにいるんだろう?
支援コーディネーターは、主に学校内の特別支援教育担当の先生や保健室の先生、教育委員会の職員などが該当します。
わが家のように、スクールカウンセラーの先生が支援コーディネーターの役割を果たしている学校もあります。

学校と保護者間でのやりとりがうまくいかないとき、支援コーディネーターが仲介してくれます
発達障害児の学習面でお悩みの親御さんは、学校だけでなく支援コーディネーターにも話を聞いてもらうことで、より専門的な解決策にである可能性があります。
まめの担任の先生は「小学校教員は放デイや発達障害児の支援制度などには詳しくない」と言っていました。
支援コーディネーターの方が間に入ることで、スムーズに支援につながることができるでしょう。
同じ悩みを持つシングルマザーの方へ

発達障害のある子どもにとって、従来の「当たり前の学習スタイル」が合わないことは少なくありません。
それでも、やり方を変えれば「できるようになる」こともたくさんあります。
発達障害児が勉強できないと悩むのは、もしかすると「できない」ではなく「やり方が違う」だけかもしれません。
子どもは「できた!」という経験を積み重ねることで、少しずつ前に進めます。
学校ではクラス単位で授業が進んだり、先生が1人ひとりの生徒につきっきりで教えることができなかったりするので、どうしても発達障害児には合わないやり方になりがち。
だからこそ、学校以外の支援制度を活用して、子どもに合ったオーダーメイドの学習環境を与えてあげましょう。
完璧を目指しても良いことはありませんし、勉強ができるようになったり好きになったりするのは簡単なことではありませんよね。
まずは
「少しでも勉強を前向きに捉えてくれるように」
「自己肯定感が下がらないように」
することを目標に、子どもに合った環境や方法を見つけていきましょう!
まとめ|「できる」を一緒に探していこう
発達障害児が「勉強できない」と感じるのは、特性による影響が大きいことがあります。
シングルマザーでも工夫と支援を活用すれば、子どもに合った学習スタイルを見つけられるかもしれません。
「うちの子なりの学び方」を一緒に見つけていくことが、親子にとって一番の学びになるでしょう。
この記事でご紹介した方法や支援先を参考に、子どもが一歩一歩ステップアップできる方法を模索していきましょう!
よく読まれている記事

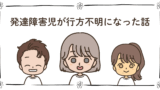

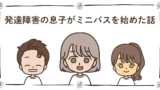

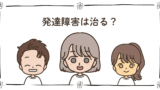
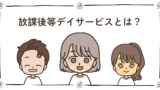
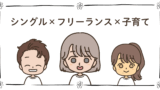

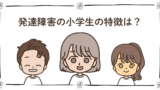
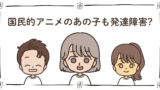
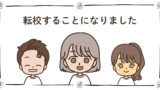
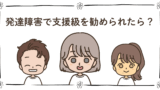
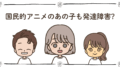


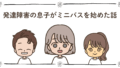
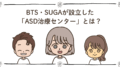
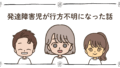
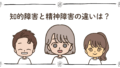
コメント