子どもの発達障害が発覚してから「療育」という存在を知る人もいるのではないでしょうか。
この記事では、療育とは何をするところなのか、メリットや効果についても解説します。
わが家では、発達障害の息子(小4)を育てています。
息子とわたしが経験してきた療育という世界について、体験談をまとめてみます。
\ 療育とは何をするところなのか知りたい!/
という方は、ぜひ参考にしてみてください。

療育とは何をするところ?

療育とは、障害のある子どもやその可能性のある子どもに対し、自立や社会参加を目指す支援を行う場所です。
乳幼児から高校生までを対象にしており、年齢によって施設や呼び方が変わります。
| 療育の呼び名 | 特徴 | |
| 未就学児 | 児童発達支援 | 自立した日常生活を営むために 必要な訓練、創作活動、作業活動、 地域交流などをする |
| 小学生~18歳 | 放課後等デイサービス | 上に同じ |
| 幼稚園・保育園・ 学校での利用 | 保育所等訪問支援 | 専門の支援員が施設を訪問し、 子どもや職員に専門的な支援を提供する |
参考:ブレインクリニック
さまざまな運動を行う
療育では、身体全体を使ったさまざまな運動を行います。
大きく分けると、以下の2つです。
粗大運動は、立ったり座ったりジャンプしたり、身体全体を大きく動かす運動のことです。
赤ちゃんがする寝返りやハイハイも粗大運動に含まれるため、人間が生きていく上で必要不可欠な運動といえます。
一方の微細運動とは、お絵描きや工作、パズルをはじめとする、手先・指先を使う運動のことです。
箸を使ったり、小さなものをつまんだりするのも微細運動で、粗大運動よりも難易度が高いのが特徴。

療育で行うアクティビティは、この2種類の運動を組み合わせた遊びやゲームがあります。

ぼくのお気に入りは「しっぽ取り」と「障害物リレー」だったよ!

集団療育は広いホールで行われるので、まるで運動会の種目みたいにダイナミックな遊びもやってくれました
ストレス解消を兼ねている
療育で行われるアクティビティは、子どもの発達を促す効果とともにストレス解消も兼ねています。
療育では読み書きや板書の練習をする時間もありますが、そればかりでは子どもにとって面白みがなく、退屈さを感じさせてしまうかもしれませんよね。
そのため、遊びやゲームを通してストレス解消を兼ねながら、1日を通して行うアクティビティのバランスをとっています。
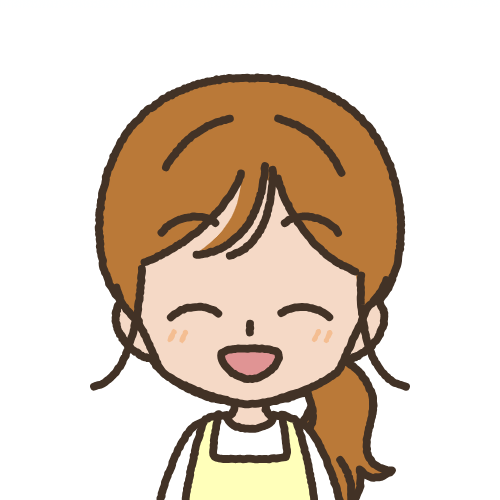
子どもの発達だけでなく心の安定にも気を配ってくれるんだね!
療育においては、厚生労働省がガイドラインを発表しており、以下の5つを網羅する支援を提供することが義務付けられています。
このうち「健康」とは、身体と心両方の健康を守ることが定められています。
つまり、発達を促す取り組みばかり行って、子どもにストレスをかけてはならないのですね。

調べてみると、多くの療育で子どもにとってストレス解消になるアクティビティを取り入れているみたいです!
1人ひとりに合わせた支援を提供する
療育最大のポイントは、通う子ども1人ひとりに合った支援を提供する点です。
療育を利用するには、各施設もしくは親御さんが「個別支援計画」という書類を作成する必要があります。
その書類の内容をもって、療育を受ける証明書である「通所受給者証」が交付されるからです。
幼稚園、保育園、学校は1クラスに何十人も在籍する集団生活となるため、なかなか子ども1人ひとりに目が行き届かないことがありますよね。

わが家のまめは、周りがよく見えない上におとなしいタイプだったので、困り感が先生に伝わりづらく、余計に置いてけぼりにされてしまっていました…

「今何をするの?」って先生に聞くのも恥ずかしくて、つい好きなことをしちゃってたよ
まめが集団生活に適応するためには、なるべく人数の多い集団へ入れるのが良いだろうと思っていました。
しかし、あまり適応できていないまめの様子を見て「マンモス幼稚園に入園させたことが間違いだったのかな」と思うことも。
療育に入った当時はコロナ禍だったこともあり、多くても4~5人くらいのクラスで、こぢんまりとしていました。

療育は、個別療育と集団療育という方法があり、まめが通っていた療育では両方のクラスがあったので、個別(先生とマンツーマン)と集団(4~5人のクラス)を曜日によって使い分けながら通いました。
個別も集団もある療育に行くなら、両方を経験してみると良いと思います!
まめの場合は、集団療育でほかのお友達から良い刺激をもらうことができたり、お友達とルールのある遊びをすることで少しずつ協調性がついたりしました。
そして、個別療育では先生が丁寧に子どもと向き合いながら、集団療育で学んだことをじっくり実践する機会を与えてくれました。

個別療育と集団療育を組み合わせることで相乗効果が生まれ、目に見えて成長を感じられました!
幼稚園や学校ではここまでの個別フォローには対応していないため、療育に通ってよかったと思う理由の1つです。
療育の目的は?

療育の目的は、障害をもつ子どもが将来社会で自立して生活できたり、日常生活や社会生活を円滑に過ごせたりすることです。
厚生労働省のガイドラインでは、以下のように定められています。
児童発達支援は、障害のある子どもに対し、身体的・精神的機能の適正な発達を促し、日常生活及び社会生活を円滑に営めるようにするために行う、それぞれの障害の特性に応じた福祉的、心理的、教育的及び医療的な援助である。
参考:厚生労働省
ひと昔前だと発達支援というのは、重度の知的障害や身体障害をもつ子どもに対する支援という認識があったかもしれませんね。
現在では、軽度の知的障害や発達障害をもつ子どもも対象となっています。
場合によっては、知的障害や発達障害と診断されていなくても、療育を受けられることがあります。

わが家のまめは、診断がついていない状態で療育に通うことができました
本人の意思が最重要視される
療育は、子どもの心身の健康を確保した支援内容で、日常生活や社会生活を円滑に過ごせるようにすることが目的とされています。
そのため、何より重要視されるのは子ども本人の意思。
児童福祉法では、以下のように定められている規定があります。
児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
子どもの意思に反した療育を行うことは、法に違反するものなのですね。
本人だけでなく家族への支援も行う
療育では、障害のある子どもの円滑な日常生活、社会生活のための支援が提供されます。
しかし、支援を受けられるのは子ども本人だけではないことをご存知ですか?
児童発達支援法では、療育において子どもを支援することだけでなく、子どもが育つ環境、すなわち家庭や家族関係が安定していることも重要視します。
そのため、子どもだけではなく家族への全面的な支援も、療育のプログラムに組み込まれているのです。
わが家ではまめが通っていた療育で1年間、以下のような支援を提供していただきました。
療育に行くたびに、明るく優しい先生たちが出迎えてくれただけで、わたしにとっては心のオアシスのような場所でした。
まめも楽しい療育時間を過ごすことができましたし、当時年少さんだった妹のナツも、療育で貸し出してくれるおもちゃのおかげで退屈せずに待つことができました。

本当に、家族3人まるっとサポートしていただいた感覚です
療育のメリットや効果は?

療育に通うことで得られるメリットや効果について解説します。
わが家でもお世話になった療育。
わが家で利用していたのは、未就学児向けの児童発達支援施設だったため、幼稚園卒業と同時に療育も終了しました。
そして小学生になった今、
療育に通っていて本当によかった!!!
と心から思っています。
子どもの発達に不安を感じていたり、療育に入るかどうか決めかねていたりする親御さんには、ぜひ療育のメリットを知ってほしい!
というわけで、わが家の体験談を交えながら療育のメリットや効果をお話していきます。
社会性を学べる
療育に通うことで、生きる上で必要な社会性を学ぶことができます。
社会性とは「明るい子になる」というコミュニケーション能力ではありません。
何をすればいいか分からないとき誰かに質問すること、できないことを「できない」と伝えること、人に感謝すること…

これから子どもが社会で生きていく上で必要な、人とのかかわり方を学ぶことができるのです。
まめはおとなしい子どもだったので、わたしは「無理にコミュニケーション力や社会性をつけなくても…」と思っていた時期がありました。
まめはお友達と話すのも苦手そうでしたし、友達と遊ばなくても1人で遊べれば良いじゃないかと思ったんです。
でも、今なら分かります。
その考えではいけなかった。
療育に通って、まめは「友達と協力してゲームに勝つ」「友達と作戦会議をしてチームプレーをする」という楽しさを知りました。
幼稚園では、ルールのある遊びがよく理解できずに、参加できなかったまめ。
しかし療育できめ細やかな指導のもと、先生や友達と遊ぶうちに、少しずつ社会性がついていきました。

療育では、まめが友達に対して何と声をかけたらいいかわからない時にも、先生が「〇〇だよって言えばいいんじゃない?」とすかさず助け船を出してくれて、スムーズにコミュニケーションがとれるようになりました

幼稚園では1クラス30人くらいいたから、困っていても誰にも気づいてもらえず、恥ずかしくて何も言えなかったから、いつも1人だったんだ💦
療育では、幼稚園や保育園よりも丁寧に子どもとかかわってくれる親密さを感じました。
特に発達障害や知的障害をもつ子どもの親にとっては、この「きめ細やかな対応」が感じられやすいと思います。
就学準備ができる
療育に通うことは、就学準備としても良い時間でした。
まめが年長になると、療育では本格的に小学校への準備クラスというのが始まりました。
そこでは、読み書きや算数を少しずつ始めてくれるだけでなく「給食当番ごっこ」や「板書ごっこ」「連絡帳ごっこ」「提出物ごっこ」など、小学校で経験することを遊びとして取り入れてくれました。


給食当番ごっこでは、給食着を着て配膳係をやったのが楽しかったよ!
給食着がカッコよくて、早く1年生になりたいな~と思った!

親としては、板書や連絡帳の書き方も遊びの中で教えてくださって、本当にありがたかったです。
小学校に入ったとき「これ療育でやったやつだ!」って分かるから、不安材料も少なくなりました!
発達に不安があると「小学校に入ってから大丈夫かな」と心配になりますよね。
療育に通うことで、小学校入学後に子どもが感じる衝撃や不安をやわらげるために、小学校生活の疑似体験もさせてもらえます。
小学校に入ると、幼稚園・保育園よりも自分でやらなければならないことが増えるし、親の目は行き届かないし、親も子も不安ばかり。
療育のレッスンに組み込まれている就学準備は、間違いなくまめの小学校生活を明るく楽しいものにしてくれました。
生きづらさを解消できる
療育で適切な支援を受けることで、子ども本人が感じる「生きづらさ」「居心地の悪さ」を解消することにつながります。
療育は、子どもの障害の特性や性格に合わせた方法で支援や、子ども1人ひとりに適した関わり方を提供してくれます。
発達障害をもつ子が生きづらさを抱えているのは、周囲との常識や認識にズレがあるから。
療育では、そんな子どもたちが「人と違う部分」を矯正するわけではありません。
障害の特性や性格を受け入れ、理解し、肯定した上で、その子が社会で生きやすくなるようなコツを教えてくれます。
たとえばわが家の場合、まめは積極的にお友達と関わろうとしませんでした。

いつもマイペースに好きなことだけしていたため、集団活動のときに1人だけ違うことをしている…なんてことも。

たとえばみんな先生のお手本を見ながら画用紙を切っているのに、勝手に画用紙に絵を描き始めたり…
その結果、まめだけ周りと違う作品になってしまいます。
先生は怒りはしませんが「集団行動ができない子」だと評価しますし、お友達からも「なんで今日のテーマのものを作らないの?」「なんで1人だけ違うことをしているの?」と言われていました。
そこまで悪いことではないものの、やっぱり集団生活の中で統一した行動ができないことは輪を乱す要因になりますし、何より本人が
という生きづらさを感じることにもなります。
幼稚園では、先生が「みんなと同じものを作ってね」と声をかけるだけで、具体的なフォローはもちろんありません。
しかし、療育の集団クラスでまめが同じ行動をすると、先生がすかさず「適切な行動」を教えてくれました。
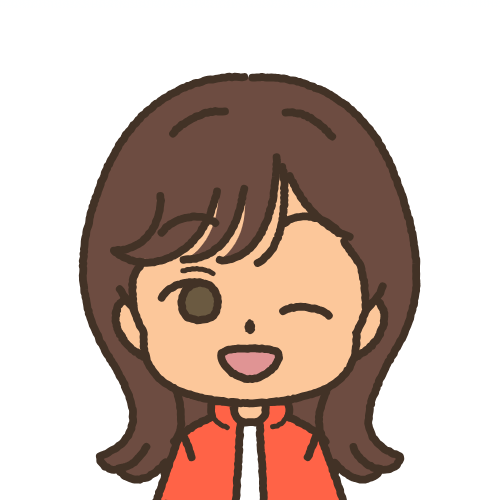
まめ君は何を作ってるの?カッコいいね!あとで飾ろう!
でも見て、まわりの子何作ってる?〇〇を切ってるね!
今は〇〇を作る時間だから、みんなのを見てまねっこしてみようか
療育の先生は、まめに
何をすれば良いか分からなければ、隣の子を見てみよう!
というライフハック(?)を教えてくれました。

いや、冗談抜きでコレは、発達障害児にとって立派なライフハックなんですよ…
まめは集団指示が通りにくく、また視覚優位(※)なので声での指示を理解するのに時間がかかってしまいます。
※3年後、発達検査で聴覚優位に変わっていました
そのため「まわりの子が何をしているか見て、同じ行動をするのが正しいときもある」ということを教えてくれました。
実際、わたしたちも「今何ページを読んでるんだろう?💦」と焦ったとき、隣の子のページをチラ見したことがありませんでしたか?
そんなふうに、まわりを見て同じ行動をすることで、少しずつ「集団行動」ができるようになっていきました。

まめは時間がかかりましたが、少しずつ「今はみんなと同じことをしたほうが良いのかも?」と考えられるようになり、まわりをチラチラ見ながら行動できるように!
療育では、こんなふうにしてまめの「生きづらさ」を解消してくれました。

発達障害をもつ子が感じる生きづらさは、本人にしかわからない苦しみや葛藤があると思います。
わたしは親ですが、まめが感じる生きづらさのすべてを理解するのは難しいし、いまだに自分と考えが違いすぎて戸惑うことも。
でも、生きづらさを感じているのはほかでもない本人なんですよね。
子どもの人生をより生きやすいものにし、幸福感を感じてもらうためにも、療育の効果は大きいと感じました。
自信がつく
療育に通うことで、子ども本人が自信をもって生きられるきっかけがたくさん生まれます。
療育では子ども1人ひとりをありのまま受け入れ、笑顔と自信にあふれた大人になれるような道しるべを示してくれます。

発達障害のある子は自信をなくして、ひどい場合は自傷行為や二次障害(非行や不登校など)が起きる可能性も。
そうならないためにも、自信を持ってもらうことは本当に大切なんです
発達障害をもつ子は、幼稚園や学校で生きづらさを感じたり、できないことが目立ったりすることがあると思います。
特に、一般的な発達過程の子どもたちにはできることが、発達障害のある子には難しかったりするからです。
こういったことが、発達障害をもつ子には想像以上に難しいことがあります。
それは怠け者だからではなく、努力が足りないのでもなく、発達障害というのが脳機能の障害だからです。
そのため、みんなができていることができないという理由だけで、発達障害をもつ子に「失敗体験」を積ませてはならないのですね。
でも、幼稚園や学校によっては合理的配慮がなされず、
「あの子はいつも失敗ばかり」
「みんなと同じことができない」
というレッテルを貼られることにもなるでしょう。

最悪の場合、子どもたちの間だけでなく保護者の間でもそういう噂が広まり、悪口を言われることも…(実体験です)
そんなとき、療育のきめ細やかであたたかい対応と支援が、子どもや親に自信と安心を与えてくれたことは、言うまでもありません。
幼稚園では怒られっぱなしで、お友達からも「なんでできないの?」と言われがちだったまめ。
でも、療育ではまめの個性が受け入れられ、得意なことや好きなことを最大限に褒めてもらいながら、問題行動を起こしたときには
「今日はこれでいいけど、次はこうしてみようよ!」
「こうしたらみんなが嬉しくなるよね!」
という声かけをしてもらえました。
怒られずに前向きな言葉をかけてもらうことが、まめにとってどれだけ安心感のある環境だったか…

今思い出すだけで目頭が熱くなるほど、療育での毎日は愛情に溢れていました
家族全員がサポートを受けられる
意外と知られていない療育のメリットなのですが、実はサポートを受けられるのは子ども本人だけではありません。
児童発達支援のガイドラインでは、子どもとその家族への総合的な支援が義務付けられているのです。
参考:こども家庭庁
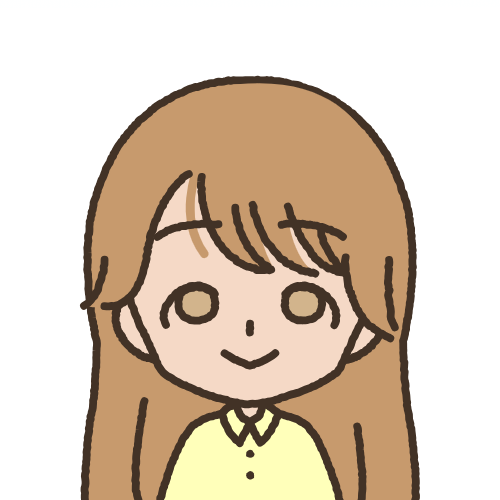
家族のサポートって、具体的にどんなことをしてもらえるの?
あくまでわが家が通っていた療育の話ですが、以下のようなサポートを提供してもらっていました。
療育では、まめの発達だけでなく家庭がきちんと機能しているかどうかも気にかけてくれました。
まめの妹・ナツを連れて療育に送迎していたのも先生たちは知っていたので、ナツとも積極的に遊んでくれたり、おもちゃを貸してくれたりして、わたしがゆっくり待機できるよう気を遣ってくれました。
まめの進路(通常級か支援級か)を迷っていたときにも、さまざまな選択肢を与えてくれて、
通常級じゃないと知識がつかないなんてことはないし、支援級だからって将来の進学をあきらめる必要もない!どこだって、何だって道はある!
という大事なことを、わたしに教えてくれました。
療育で家族へのサポートが義務付けられているのは、子どもが家庭や家族から大きな影響を受けると考えられているからです。
療育では子どもだけを支援するのではなく、子どもの家族も支援して、その家族や家庭を安定させることで、子どもの発達に良い影響を与えると考えています。
療育は誰でも入れる?

療育は、誰でも入れる制度ではありません。
療育を受けるために必要なのは「通所受給者証」(通称・受給者証)という証明書です。
受給者証が交付されるためには、医師の証明書や専門機関からの意見書など、必要な書類が多くあります。
こちらの記事でくわしく解説していますので、参考にしてみてくださいね。
しかし先ほどもちらっとお話したように、まめは「発達障害」「知的障害」という明確な診断がついていない状態で、療育を利用することができました。
もともと、まめが療育を利用することになったのは、幼稚園の先生に勧められたからでした。
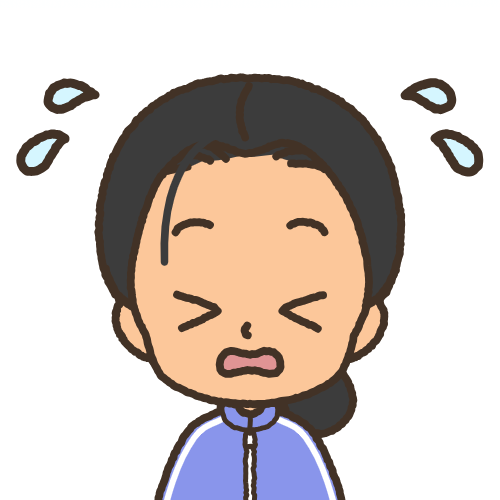
集団生活に適応できない、身支度に時間がかかる、先の見通しが立てられないなどの特性が目立ちます。
一度、発達検査に行かれてみてください…
幼稚園の面談でこのような指摘があり、発達検査を受けることになったまめ。
しかし、その翌年に受けた発達検査では「発達障害」という診断がおりませんでした。

幼稚園に勧められた時点で100%発達障害だろうと思ったのに、ここまで来て診断が下りないなんてことある!?と驚いた記憶…
しかし、幼稚園の生活で困りごとがあるのはまぎれもない事実。
幼稚園の先生に指摘された内容を引っ提げて、療育探しを始めました。
医師の診断は下りていない装備の弱い状態でしたが、どこの療育からも断られませんでした。
その中で、わが家の希望していた集団療育を行っている施設に決定。
施設長と面談をして、子どものことを知ってもらい、
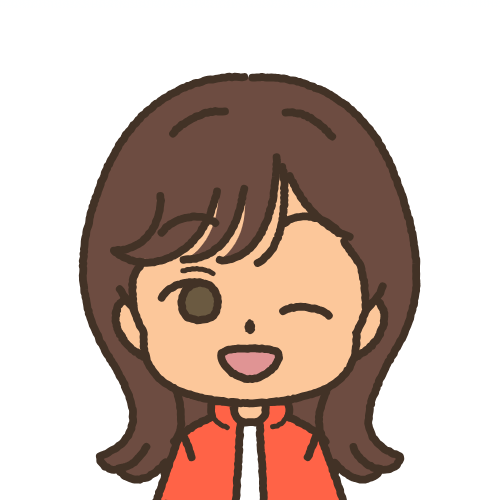
ではまめ君の入所を決めて、受給者証を一緒に申請していきましょう!
という運びになりました。

受給者証の申請には必要な書類がたくさんあるのですが、療育の先生が一緒に作成してくれたのでとてもスムーズでした!
わが家で療育を選んだポイント

わが家で療育を選んだポイントは、まめの課題だった
同年代のお友達とのコミュニケーション
を伸ばせるかどうかでした。
まめは、家族や先生とのコミュニケーションではそこまで困りごとがなかったのですが、同年代のお友達への興味が薄く、壁を感じていました。
家族は気遣いのいらない関係性だし、先生は子どもの言いたいことを適切に汲み取ってくれるので、コミュニケーションが楽だったんだと思います。
でも、同年代のお友達ってそうはいかないし、衝突したりケンカになったりすることもありますよね。

まめはそういう「スムーズにいかないコミュニケーション」に向き合うのが苦手で、お友達とはあまり遊ばないタイプでした
そのため、お友達とのトラブルやちょっとした言い合い、友達関係のいざこざなどを適切に経験することができなかったんです。
そんなわが家では、まめが同年代のお友達の輪の中でコミュニケーション力を鍛えられるよう、集団療育をしている施設を重要視しました。

見学した施設は、どこもきめ細やかな療育を提供していて魅力的でしたが、中には個別療育に特化した施設もありました。
わが家で最終的に決定した療育施設では、ほぼ毎日集団療育を行ってくれました。
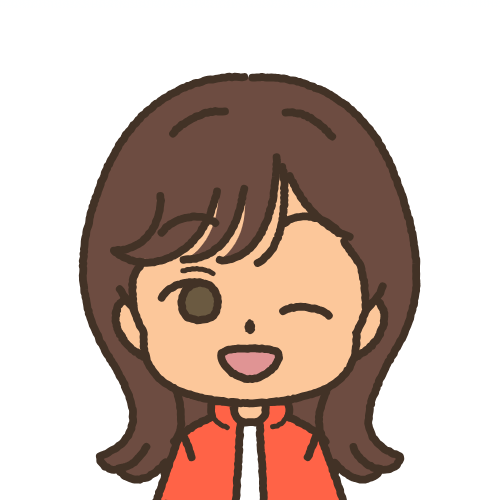
まめ君が集団療育で学んだことを実践する時間もほしいので、週1回だけ個別療育を入れてもいいですか?
とのことで、もちろん了承。
まめはにぎやかな集団療育を楽しんでいましたが、個別療育は個別療育で気分転換になったようで、どちらも取り入れてみて大正解でした◎
「どの療育が良いのか分からない」
「それぞれの違いを説明してほしい」
とお悩みの際には、計画相談支援サービスを活用することをおすすめします。
計画相談支援とは、障害福祉サービスの利用を希望する人向けに、個々のニーズに合わせた支援を紹介してくれるサービスです。

お住まいの自治体窓口に「計画相談支援」と問い合わせれば、案内してくれますよ◎
療育っていくら親が見学しても、せいぜい「施設の雰囲気」とか「どんな先生がいて、どんな子どもが通っているか」ぐらいしかわからないんです。
もちろんそれらも、療育を決めるポイントではあるのですが、
本当にうちの子に合っているのかな…
と不安になることもあるでしょう。
そんなときは、各ご家庭や子どもに合った療育を比較し紹介してくれる「計画相談支援」を活用してみてください。
家庭でも「療育メソッド」を活かしてみよう

療育に通ってみると、家でも活かせるメソッドを取り入れていることに日々感心させられっぱなしでした。
療育で行っている取り組みやアクティビティを自宅で実践するのはハードルが高くても、声かけや対応の1つ1つを意識してみるだけで、子どもへの関わり方をアップデートすることができました。
わが家で役に立った療育メソッドは、
自分で気づかせて適切な行動に移させること
でした。
まめはお友達や周囲の人に興味を示さない子どもだったので、その場その場でマイペースに行動してしまい、適切な行動をするのが苦手でした。
みんなが並んでいるのに1人だけ教室で遊んでいたり、身支度の時間なのにボーっとしていたり…
必ずしもみんなと同じ行動をする必要はありませんが、集団生活をする上では「適切な行動」がありますよね。
今何をすべきなのか、そのときの「適切な行動」とは何なのかを、自分で気づかせるという方法を療育で教えてもらいました。
この方法を教えてもらったことで、小学校に入ってから自然とまわりを見ることができるようになったり、適切な行動に自分で気が付いたりできるようになりました。
難しいやり方はなく、適切な行動をしてほしいときに「〇〇ではなく△△をして」と指示するかわりに、以下の方法を用います。
こうすることで、まめの場合夢中になっていた行動を一旦やめて「あっそうだった!」と気づいてくれるようになりました。

あくまでまめにとって良い方法だったという情報であり、個人差があります
療育の先生いわく、
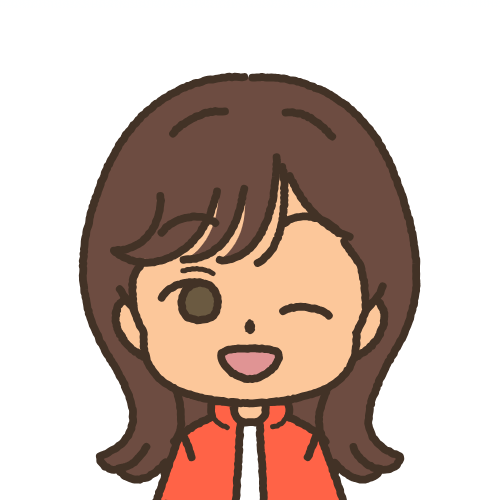
「今これをやるんだよ」と教えてあげるのも良いんですが、自分で気がついて適切な行動に移せることで、少しずつそれが癖付いて定着していきますよ!
とのことで、まめには効果抜群な方法だったんです。
療育の先生はみんなに同じアプローチをしているわけではなく、まめの個性や特性を見て、この方法を採用してくれたんだと思います。
もし療育に通うことになったら、家庭でできる声かけや意識できることを、ぜひ先生に聞いてみてください!
子ども1人ひとりに適切な方法を紹介してくれると思います。
実はあまり知られていない療育

わが家のまめは、幼稚園のときに療育にお世話になっていました。
しかし、まめは目に見えて発達障害や知的障害とわかるわけではないので「療育に通っている」とお友達に言うと

療育!?知的障害とか身体障害の子が行くところじゃないの?
と、よく驚かれたものでした。
相手は悪意があってそのようなリアクションをしているわけではありませんが、実際に療育を利用している人からすると複雑な気持ちですよね。
「発達障害」という言葉が世間に浸透して間もないため、療育や発達センター、放課後等デイサービスなどの知名度もまだまだ低いようです。

かくいうわたしも、子どもが発達障害じゃなかったら療育を知らなかったかもしれないし…
療育は、意外なことに診断名が明確についていなくても通うことができ、子ども1人ひとりに合った教育を施してくれる施設です。
診断名がついていなくても、発達に不安があればぜひ療育を検討してみてはいかがでしょうか。
子どもの集団生活や日常生活がより楽に、充実感のあるものに変わっていくでしょう!
まとめ
療育が何をする場所なのか、効果やメリットについて解説しました。
療育は、発達障害や知的障害のある子ども、また重度の障害をもつ子どもが支援を受ける場所…
というイメージがあるかもしれませんが、実はより幅広い子どもが利用できる福祉サービスです。
子どもだけでなく家庭全体を支援してくれるサービスなので、療育に通うことで家族の生活や保護者のメンタルが安定することも期待できます。
子どもの発達に不安を抱える保護者の方は、ぜひ自治体の窓口で療育について伺ってみてください!
よく読まれている記事




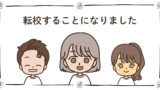
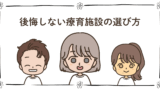
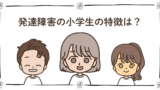

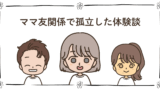
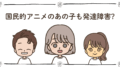


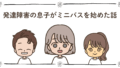
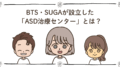

コメント