わが家の発達っ子・まめがWISCという知能検査を受けた際のお話です。
結論からいうと、まめはWISCの結果「知的障害がある」という判定が出ました。
もともと発達障害があり、今後の学習や学校生活について方向性を決めていこうと思っていた矢先の出来事でした。
発達障害児を育てる親御さんや、発達に不安な点がある親御さんにとって、有益な情報になればと思います。
- WISCってどんな検査?
- WISCを受けるとどんなことがわかる?
- わが家の体験談
- 知的障害発覚後のわが家の決断

WISCを受けたら知的障害が発覚

わが家のまめは、2025年にWISCを受けました。
その結果、まめには知的障害があることが発覚しました。
WISCでは、総合的な結果としてIQが70(75とする場合もある)を下回った場合、知的障害があると判定されます。

ただし、WISCで出たIQだけで「完全な知的障害」と診断されるわけではなく、ほかにも診断基準があるようです
まめのIQは69だったため、数値としては知的障害があるという判定になりました。
まめがお世話になっている小児科いわく、総合的に「知的障害がある」と診断されるまでには、WISC以外に加点されるポイントがあるそうです。
それが、WISCを受けたり先生が診察をする際の受け答えやコミュニケーション力です。
WISCはあくまで「知能検査」なので、対話やコミュニケーション力までは測ることができません。
知的障害があるかどうかは、知能+コミュニケーション力を総合的に見て判定されるそうです。
まめの場合、WISCではIQが70を下回っていましたが、受け答えはしっかりしており、コミュニケーション力は問題ないという判定を受けました。

先生の質問に的を得た答えができるかどうか、質問の意図を理解できているかどうかをチェックするそうです
まめはシャイな性格だということもあり、先生に質問されてもモジモジしてしまいましたが、先生はそういった”気質”と”受け答えの能力”を分けて考えてくださったようです。
そういうわけで、まめは「知能検査では知的レベルだが、コミュニケーション力は平均的」という判定を受けました。

なんだか判定が中途半端でよくわからないね…!

そうなんです…
まめは昔からグレー判定が多くて、いつも中途半端な状態。
わたしもこの先どう動けばいいか悩んでしまいました
WISCってどんな検査?

まめが受けて知的障害が発覚したWISCとはどんな検査なのか、ご説明していきます。
WISCは「ウィスク」と略して呼ばれ、正式名称を「ウェクスラー式知能検査」といいます。
「ウェクスラー式知能検査」には複数の検査方法があり、WISCはその中の1つなのだそうです!
WISCは、同年齢集団内での相対的な位置をIQで表し、知能水準を示します。
それでは、WISCが具体的にどのような項目で、どのような結果が出るようになっているのか見てみましょう。
WISCを受けてわかること
WISCは本来、発達障害や知的障害を診断するためのものではありません。
WISCは、子どもにとっての得意不得意を把握し、関わり方や伸ばすべきところを知るための検査です。
WISCでは、以下の項目についてのIQ(偏差知能指数)を調べることができます。
- 全検査IQ(総合的なIQ)
- 言語理解指標
- 知覚推理指標
- ワーキングメモリ指標
- 処理速度指標
それぞれどのようなことが分かるのか、詳しく見ていきましょう。
全検査IQ
全検査IQは、ほか4つの指標の得点を合わせ、全体的な認知能力を算出したものです。
平均を100とし、70を下回ると「知的障害」と判定されます。
言語理解指標
言語理解指標は、言語による理解力・推理力・思考力に関する指標です。
語彙力、文法理解、情報処理能力を評価するもので、言語的コミュニケーションを通して推論する力を調べます。
いわゆる、耳で聞いて情報を処理し、それに適したアウトプットをする力です。
知覚推理指標
知覚推理指標は、視覚的な情報を把握し推理する力に関する指標です。
新しい情報に対する解決能力や対応力にも影響するとされ、模様や絵の概念などを通して、目から入ってくる情報を処理する能力を評価します。
ワーキングメモリ指標
ワーキングメモリ指標は、一度習った知識を記憶し、必要なときに情報を操作する能力に関する指標です。
読み書きや計算などの学習内容を頭の中に記憶し、実生活やテストなどの際に情報を取り出して使う力のことです。
処理速度指標
処理速度指標は、視覚情報を処理するスピードに関する指標です。
シンプルな課題をどれだけ迅速に処理できるかを評価し、注意力や集中力、タスクをすみやかに実行する力に影響します。
WISCの検査内容
WISCの検査内容について、詳しくは明かされていません。
わが家がWISCを受けたときにも、まめだけ個室に案内され、わたしは待合室で待機していました。
そのため、具体的にどんな出題がされていたかは不明です。
WISCを受けて算出される指標の項目から考えると、以下のような出題があるようです。
参考:LITALICOジュニア
検査が終わったあと、まめに聞いてみると

似てる絵を探す問題とか、マークを探す問題があった
と言っていました。

検査には1時間半くらいかかったので、どんな問題だったかよく覚えていないほどに疲れ切っていました(笑)
先生は「WISCは長くかかる検査なんですが、まめ君は集中してよく頑張ってくれました」と言ってくださいました。
WISCの所要時間は1時間~1時間半ですが、子どもの様子に合わせて休憩を挟んだり、追加の検査が必要になったりすることもあるそうです。
WISCを受けるまでの流れや費用
WISCは、医療機関やカウンセリングルーム、市町村の教育支援センターなどで受けることができます。
わが家はWISCを受ける前から、小児科の発達外来に通っていたので、そこで
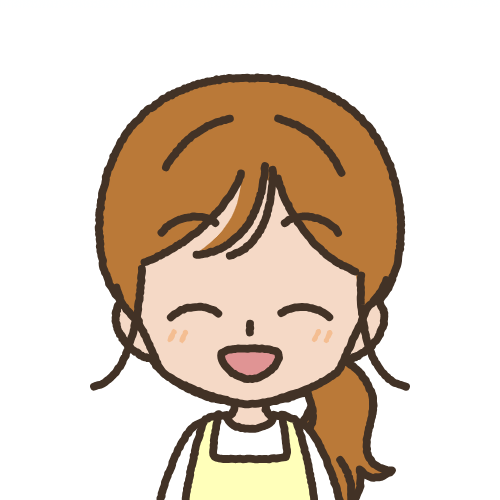
今後のために、WISCを受けておきましょう!
と提案していただきました。
費用は、どこでWISCを受けるかによって異なるそうですが、わが家で受けた小児科では5,500円(税込)でした。

WISCをはじめ発達外来での診察は助成金が出ないので、全部実費でした…!
場所によっては保険が適用されたり、公立の支援センターなどでは無料で受けられたりすることも。
しかし、民間のカウンセリングルームなどでは、逆に10,000~20,000円に及ぶこともあります。
わが家では、たまたま通っていた小児科でWISCを実施していたのでそこで受けることになりましたが、WISCだけが目的の場合には、より安いところで受けたいですよね。
費用については、お住まいの自治体に問い合わせてみてくださいね!
わが家でWISCを受けるまでの経緯

わが家でWISCを受けることになったのは、まめが小学4年生に上がるに向け、より細かなプランを立てたかったからです。
小3で、もともと持っていたASDとADHDの傾向が強く出るようになり、学習面でも大幅な遅れがみられるようになったまめ。
小4といえば、小学校高学年にあたります。
このまま通常学級に在籍していて良いのか、通級や支援学級を利用すべきなのかを見定めるために、WISCの検査を受けることにしました。
以下にて、まめの幼児期からWISC実施までの経緯をまとめてみたいと思います。
小2まで診断がつかずグレーのまま
まめは幼児期に発達検査(新版K式発達検査)を受けたことがあります。
そこでは、まめは発達障害ではないという結果が出ました。
先生からは、同学年の子たちよりも9~10ヶ月の遅れがあるだけだといわれました。

まめは3月生まれなので、正直その程度の遅れは認識していました
幼稚園から発達の遅れを指摘され、幼稚園で受けたK式発達検査。
しかし、結果は「発達障害ではない」ということで、まめは小学校も通常学級に進むことになったのです。

このとき、通常学級と支援学級のどちらにすべきか決めるため、幼稚園の先生や療育の先生と何度も面談を重ねてきました。
そして、どの先生からも
支援学級である必要はない
というアドバイスをいただいたことで「それなら通常学級で頑張ってみようかな」という結論に至りました。
わたしとしては、まめが0歳のころからなんとなく「発達に遅れがありそう」「なんらかの検査で引っかかりそう」と思っていました。
おすわりまでは順調だったものの、ハイハイからは成長ペースがゆるやかになり、言葉も遅かったまめ。
しかし9ヶ月検診でも、1歳半検診でも、3歳児健診でも、指摘されることはありませんでした。

今振り返っても、あんなに特性が強かった(わたしから見ると)のに、なぜ一度も指摘されなかったのか不思議でなりません(笑)
このとき保育園でも通っていて、園生活に支障があれば、すぐにでも療育につながれたかもしれません。
しかし、まめは幼稚園だったため3歳まで自宅保育でのんびり過ごしていて、
保健師さんや小児科で指摘されないなら、まぁいいか
と思っていたのも事実です。

そして幼稚園に入り、いよいよまわりのお友達と比較して「遅れている」と感じるようになったり、先生からお叱りを受けることが増えていきました。
そして、年中さんから「ことばの教室」に通い始め、年長さんで療育につながることができた…という経緯です。
それでもなお、まめに正確な診断名がつくことはなく、そのまま公立小学校の通常学級に進学することになりました。
小3で知的障害を疑い始める
小学校に入ったまめは、それまで強かったASD(自閉スペクトラム症)の特性が弱くなり、ADHDの傾向が強くなっていきます。
そのため、お友達と適切なコミュニケーションがとれず不快な思いをさせてしまったり、授業中に立ち歩いてしまったり、困りごとが増えていきました。
しかし、1年生の後半になると少しずつその行動が落ち着いていき、どうにかこうにか2年生になることができました。

2年生ではお友達トラブルが減り、授業中も座っていられるようになりました。

少しずつ成長している…!
と感動しながら見守っていた2年生の1年間。
授業内容もまだ難しくはなく、まめもついていけているようでした。
しかし、3年生になって状況が一変します。
3年生は、小学校の中で「中学年」に割り振られ、1~2年生で許されてきたことも通用しなくなる学年。
先生のフォローはなく、ほぼすべてのことを自分で考え選択しなければなりません。

たとえば3時間目に体育がある日は、朝のうちに体操着に着替えても良いし、2時間目のあとに着替えても良いそう。
ただ、着替えるタイミングは本人次第で、先生は声かけをしません
まめは「3時間目に体育がある」ことを認識していたとしても、着替えなんてすっかり忘れてしまうタイプ。
そう、わが家にとっては魔の小3ともいえる、人生の転機だったのです…!
先生から学校生活の様子を聞くたびに、わたしは

まめは、ASDやADHDだけでなく「知的障害」があるのではないか…?
と考えるようになりました。
そして小3の2学期、かかりつけの小児科にある「発達外来」に相談してみることにしました。
発達外来を受診し各検査を受ける
わたしの住む地域では、医療機関や発達センターなどあらゆる場所で発達検査を実施していました。
その中でも、慣れ親しんだ先生や看護師さんのいるかかりつけの小児科が最適と判断し、そこに通うことに。

現在も月に1回のペースで通っています!
小児科で受けたのは、今回お話した知能検査「WISC」と、自閉スペクトラム症を検査する「PARS-TR」の2種類。
WISCで知的障害が発覚し、PARS-TRでは「自閉スペクトラム症の傾向がある」という結果が出ました。
幼児期にはASD(自閉スペクトラム症)の特性が強く、今もその傾向はあります。
しかしそこまで強くはなく、現在は年齢相応の友人関係を築けていることから、コミュニケーションに関しては問題ないとのこと。
そして、WISCで知的障害があると判定されたので、まめは
学習面においては支援が必要であり、コミュニケーション力は平均的
という結果になったのでした。
今後は、この結果をふまえた学習計画を立てていくことになります。
知的障害発覚後のわが家

WISCで知的障害が発覚したまめ。
もともと知的障害を疑って受けた検査だったので、その結果に驚いたりうろたえたりすることはありませんでした。
しかし、実際に「知的障害あり」と結果が出ると、何もせずにはいられません。
さまざまな選択肢を持って、少しずつ今後に向けて準備を始めました。
わたしの性格上、ショックな出来事が起きてもすぐに切り替え行動するタイプであり、まめの知的障害発覚もほとんどダメージはありませんでした。

ただ、うわ~忙しくなるぞ~~~というゲンナリ感はありました(笑)
そんなわたしが、まめの知的障害発覚後に行動したことをまとめてみます。
学校に報告&面談
WISCで知的障害が発覚し、すぐにしたことは、学校への報告です。
ちょうど年度切り替えだったので、新しい担任の先生へのご挨拶がてら検査結果を共有。

ご挨拶”がてら”サクッとできるような軽い報告ではないんだけどね…笑
小1から小3までのおおまかな学校生活や学習面の遅れを共有し、4年生になってからの学習プランについて相談させてほしい旨をお伝えしました。
小学校は、幼稚園や保育園と違って子どもの様子がまったくといっていいほど見えない場所。
先生との連携は大切だと身をもって感じました。
合理的配慮や家庭でのフォロー
WISCで知的障害が発覚しましたが、本人の意思により現在の学校に在籍したまま支援をしていくことになっていたので、
を強化することになりました。
合理的配慮はこれまでも担任の先生にお願いしてきたことで、まめの場合は以下のような対応をしていただいてきました。
小3になってからは、授業中に立ち歩くことはなくなってきたので、今後の合理的配慮は学習面がメインになりそうです。
今回のWISCの結果をふまえて、小児科の先生からは以下のようなアドバイスをいただきました。

小学校6年間のカリキュラムを全部終わらせるよりも、復習と定着を重視してゆっくり学習していきましょう
教科書の中の1つのユニットでも、さらに細分化してスモールステップで進めていくのが、今後の目標。
その学習方法を、今の学校で取り入れられるのかどうかが論点でした。
このあとくわしく解説しますが、まめが通う小学校には支援学級が設置されていないので、合理的配慮といってもかなり限られてきてしまいます。
この学校でどこまでしてもらえるのか…探り探り、先生と連携していました。
転校を選択肢に入れる
WISCで知的障害が発覚し、これまでぼんやり考えていた「転校」という選択肢が少しずつ現実味を帯びてきました。
というのも、わが家から通える学校は合計4つあり、その中に支援学級のある公立小学校があるのです!
今は学区内の小学校に行っていますが、通学距離もさほど変わりませんし、ミニバスでお世話になっている小学校なので、まめにとっても縁のある場所。
ただまめ本人としては、なるべく今の学校にいたいそう。
そのため、まめの意思と学習計画の兼ね合いで決めることになりそうです。

現段階では転校の予定はありませんが、今の学校での学習スタイルが苦痛に感じるようなら、隣の学校の支援学級を申請してみたいと思っています!
※2025年7月追記
まめは、支援学級のある小学校に転校が決まりました。
まとめ
わが家で知的障害が発覚した、WISCという発達検査について解説しました。
もともとWISCは、発達障害や知的障害の有無を調べるための検査ではありません。
子どもの得意不得意を把握し、何を伸ばすべきかを数値で算出するための検査です。
まめも、WISCを受けたことで知的障害が発覚し、今後どのように学習フォローをすべきかプランニングする機会をいただきました。
子どもの学習や学校生活におけるサポート方法を見出すためにも、WISCは効果的な検査といえるでしょう。
検査費用がまばらなので、お住まいの自治体に問い合わせてみることをおすすめします!
よく読まれている記事



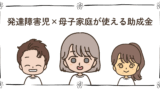
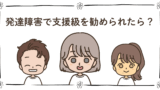
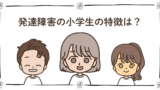

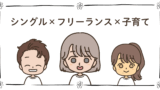
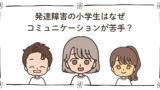
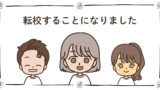
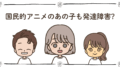


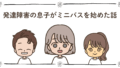
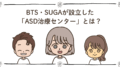
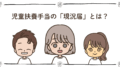
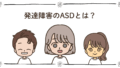
コメント